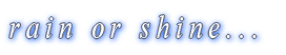
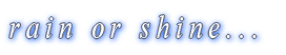
この想いはずっと変わらない。
透き通るような蒼天の日も
空が泣く日も
白銀が天から降る日も
風が二人の間を駆け抜ける日も
この鼓動が止まるその刹那まで永遠に。
だから――
柔らかな雨が静かに降る秋の日の午後。
士度は音羽邸の居間で一人、本のページを捲っていた。
パラリ・・・
雨の音に紛れて、ページを捲る乾いた音だけが少し湿った空気を漂わせる居間に時折控えめに響く。
メイドが先ほど置いて行った珈琲のぬくもりが、少し冷えた空気に挨拶をしていた。
不意に・・・・士度は何かに気がついたかのように本から顔を上げると、
眼を閉じ、耳を澄ました。
バイオリンの旋律が聴こえてくる――
防音のレッスン・ルームからの音も、士度の兎聴擬にかかれば程よく耳に響くのだ。
耳に届くのは、何度も何度も繰り返される同じメロディー。
時にゆっくりと、時に速く、あるときは一音一音を確認するかのように強弱をつけて。
その音は徐々に激しく、大きな波を打つかのように奏でられた。
彼女にしては珍しく、焦りと苛立ちが音に出ているように感じられた。
やがて奏者もそれに気がついたかのように、音色は再び努めて優しく奏でられたが・・・その音符の羅列が唐突にピタリ、と止まった。
そして静寂が訪れる。
士度はゆっくりと眼を開き――虚空を暫し見つめると、
その視線を再び本へと戻した。
明日は月末のコンサートの音合わせがあるというのに・・・
どうしても躓いてしまう小節があり、マドカを大いに悩ませていた。
これは技術的な問題ではなく、気持ちの問題だ。
指は正確に音を捉えるのだが、バイオリンから紡がれるフレーズにどうしても違和感を感じてしまうのだ。
何度繰り返し練習しても、いくら音の出し方を変えてみても・・・納得できるような音を出すことができない。
気がついたら焦る気持ちを音色に乗せてしまう始末で。
マドカの秀眉が悲しげに顰められ、彼女は弓を楽器から離した。
そしてバイオリンは深い溜息と共にケースの中へ横たえられた。
音に気持ちがついていかないことだって、時にはあることだ。
その原因がさっぱり分からないことだって、珍しくはない。
こんなときには気分転換が必要。
お昼寝をしてスッキリしたり、温かいハーブ・ティーで身を暖めたり、違うジャンルのCDを聴いてみたり・・・。
他には・・・
重い気持ちを抱えたまま、
マドカはレッスン・ルームの扉を開けた。
雨の匂い微かに廊下に広がっていた。
練習に集中しすぎて、自分は雨が降り始めていたことにも気がつかなかったようだ。
マドカは外で待たせていたモーツァルトを呼ぶと、尻尾を振ってやってきた彼の頭を撫でて、そのハーネスを手にした。
<ドコヘ、イクノ?>
愛犬が無邪気に訊ねてくる。
「雨が降っているから・・・・士度さんはお庭じゃなくて二階のお部屋にいるのかしら?」
マドカが首を傾げると、
<シド、ナラ・・・イマニ、イタヨ?>
とモーツァルトがマドカを見上げた。
「じゃあ・・・居間まで・・・お願いね?」
少女と一匹は若者が静かな時を過ごしている部屋を目指した。
キ・・・と音を立てて、居間の扉が控えめに開いた。
中の気配を探るように、彼女はそっと居間へ足を踏み入れる。
俯いていた士度が――ゆっくりと顔を上げる気配がした。
「練習は・・・もう終わったのか?」
彼の穏やかな声に導かれる仄かな安堵感を擽ったく思いながら、マドカはモーツァルト共に士度の傍へ歩み寄る。
「ちょっと休憩です・・・」
マドカははにかみながらそう言うと、ハーネスから手を離し、両手を士度の膝の方へと流した。
するとその手にコツン・・・と当たるものがある。
「本・・・ですか?」
「ああ、この間お前が書斎から出してくれた・・・ハーブの事典だ。西洋の草花に俺は疎いからな・・・。
マドカが育てているものや庭にあるものも載っていて・・・中々面白い。」
――俺が本を読むなんて、珍しいだろう?――
自嘲気味にそう言う士度にマドカは慌てて首を振った。
「でも・・・士度さん、ときどき書斎で本を探してるじゃないですか?
それに、庭に寝転びながら読んでいることもあるってメイドさんが言ってましたよ?」
本に弾かれた両手を躊躇いがちに後ろへ組みながら、マドカは士度に微笑みかけた。
「・・・動物事典とか植物事典とか・・・・絵とか写真が載っているものばかりだぜ?
活字ばかりだと眠くなっちまうし・・・それに分厚い本だと飽きたら枕にできるしな。」
少し気恥ずかしげに、しかし彼にしては珍しく冗談めかしたことを言ったので、マドカからクスクスと笑いが漏れた。
しかし彼女は――士度の目の前に立ったままだ。
彼の隣の席は空いているのに・・・。
「マドカ・・・?座らねぇのか?」
士度がポンポン・・・と空いている側のソファを叩いた。
するとマドカの顔がサッと桃色に染まった。
「あ・・・あの・・・えっと・・・・」
そしてマドカは口元に手をあて、逡巡するような表情をすると恥ずかしげに俯いてしまった。
士度は目を瞬かせた。
「その・・・士度、さん・・・・」
顔を真っ赤にしながら、尚も言いあぐねているマドカの耳に、
士度の膝に乗っていた事典が、ポスン・・・とソファに置かれる音が聞こえた。
「来いよ、マドカ。」
ほら・・・・
そう言うや否や士度はマドカの手を取ると、驚くマドカを余所に彼女を自分の膝へと導いた。
マドカは士度に導かれるままに、トスン・・・と横向きに抱っこをされる形になった。
――彼の膝の上に座りたい――
そんな子供じみた願望を図らずとも彼に見透かされて、
マドカはなんとも面映い気持ちになり、彼の膝の上で極まりが悪そうに俯いてしまう。
すると――士度の大きな手が彼女の頭をそっと引き寄せ、
自分の胸へと凭せ掛けた。
「甘えたって、いいんだぜ?お前は俺に・・・・いつでもさ。」
――遠慮なんざ、するなよ・・・――
そう優しく耳元で囁かれ、マドカは刹那目を瞠ると、
途端泣き出しそうな顔をしながら士度の胸元に頬を押し付けた。
そんな彼女の背中を、士度は優しく撫でてやる。
悲しむ子供を落ち着かせるように、ゆっくりと、慈愛を込めて。
「・・・・どうした?練習、上手くいかなかったのか?」
優しく触れる彼の掌と心地好く響く彼の声が、マドカの瞳から涙を引き出した。
マドカは濡れた瞳のままコクコクと頷きながら、士度のシャツを握り締め、その貌を彼の胸元に埋めた。
「・・・・そうか。」
自分の腕の中で肩を震わせる彼女をさらに引き寄せ、士度は抱く腕に少し力を込めた。
ポトリ・・・と小さな雫が士度のシャツを濡らした。
彼女が奏でる天上の音色と「神の耳」とも謳われるその天賦の才故に――
「天才」という称号が彼女には付いて回っていること士度は知っていた。
そして彼女はその称号に溺れることも、甘んじることもせずに、
常に謙虚な態度と――そして自分に厳しく、誰にも負けない努力と練習量によって、“音”というものを探求しているということも。
日常生活の中では常に穏やかな微笑を湛えている彼女の、もう一つの顔――
“プロ”の音楽家としての一面、そしてその姿勢を、共に暮らすことによって士度は垣間見てきた。
彼女の凛々しくすらあるそんなもう一つの側面も――士度を強く惹きつけた。
そんな彼女を見守るうちに――
マエストロとしてのマドカが背負っている目に見えぬプレッシャーが、時々彼女に重く圧し掛かっていることに士度は気づいた。
その細い肩に、繊細な心に常に付き纏う、外からの感情――羨望と期待と妬み。
そして彼女自身の――誇り。
マドカはそれらに屈するような精神の持ち主ではないということは士度自身よく知ってはいたが、
音楽に向き合う彼女の姿が時折――苦しく、悲しげに見えることがあった。
そんなとき彼女は、音を奏でることを止め――
そして彼女は無意識に――いつもより少し甘えるような素振りを見せ、士度に触れたがる。
士度の肩口に頬を頭を持たせかけたまま他愛のないお喋りをしたり、
気がついたら彼の膝を枕にして微睡んだり、
不意に
そんな風に士度と共に暫く穏やかな
やがて彼女は来たときよりもスッキリしたような顔をして、練習する為に戻っていくのだ。
そして士度の耳に再び天の音色が聞こえてくる―-。
音羽邸独特の優しい憩いの空間の中で時折感じる小さな曇り空――
初めてそれを目の当たりにしたとき、士度は少し意外に思ったが、彼女の性格と環境を知るにつれ、合点がいった。
その才能故に侵食してくる期待と、自負と、責任感――
昔の自分の心の奥底に潜んでいた、あのざらついた感情と同じものを、きっと彼女も時折感じている・・・・。
「父様も、先生も、観客の皆さんも、お友達も・・・・皆、私の演奏が好きだと言ってくれるんです・・・・」
不意に、マドカが士度の膝の上で小さく呟いた。
――それは、とても、嬉しいこと・・・・――
ほんの少し、苦しそうに。
「でも・・・・・」
「――俺さ、言葉足らずだからよ。」
――やっぱり、同じような事しか、言えねぇけどよ・・・・――
言いあぐねたマドカの言葉に、士度の声が重なった。
彼女はその声に聞き入るように、耳をそっと彼の胸元に押し付ける。
「俺も好きだぜ・・・?マドカの音。」
士度の真っ直ぐな声に、彼女の瞳が刹那、瞠られる。
そして彼女は士度を不思議そうな表情で見上げてきた。
そんな彼女の表情に苦笑しながら、士度が謝罪の言葉を述べようとしたとき――
「不思議・・・・」
マドカの桜色の唇がゆっくりと動いた。
やがてそれは優美な笑顔へと変わる。
「不思議ね・・・・同じ言葉なのに士度さんのは――とても素直に心に響くの・・・そしてどうしようもなく・・・安心するの・・・・」
最後の方は少し恥ずかしげに語尾を小さくしながら、マドカは再び士度の胸元に身を預けた。
照れ隠しのように小さく身じろぐマドカに、士度は抱擁に少し力を入れることで答えた。
「・・・・こんな膝でいいならよ、いつでも貸すからさ――」
彼女の柔らかな髪を撫でながら穏やかな声で士度は言う。
――だから遠慮なんざ、するな・・・・――
マドカが士度のシャツを強く握り締めた。
士度の腕の中の彼女の体温が、少し上がったような気がしたのは気のせいだろうか?
「・・・・ひとつだけ、お願いしても・・・いいですか?」
俯いたまま、遠慮がちにマドカが声を発した。
めったに無い彼女の言葉に、士度は目を見開いた。
――何だ・・・?――
問いかけるような、興味深そうな視線を頭上から感じながら、マドカは恥じらいを押し殺すと、精一杯の勇気を振り絞る。
――お願いですから・・・――
「わ・・・私だけの・・・・『特等席』にしてください・・・士度さんのお膝は・・・・」
「・・・・・・・」
一瞬の沈黙の後、士度は俯きながらククク・・・小刻みに肩を揺らした。
「もう・・・!笑うところじゃないです・・・!!」
マドカは士度のシャツに顔を隠し、赤面しながらも精一杯抗議する。
「・・・・お前、ホント、可愛いよな。」
笑いながら何気に紡がれた彼の滅多に無い言葉に、彼女の体温はさらに上昇し、その貌は再び朱色に染まる。
弾む鼓動を押さえつけようと、マドカはもう一度身体を士度に密着させた。
すると彼が彼女の手に徐に指を絡めてきた。
そして顔を上げようとするマドカの頭を、空いた手で優しく制した。
「お前だけだぜ、マドカ。」
繋がれたマドカの手がピクリ、と動いた。
「――お前だけだ。」
その声に導かれるようにして降りてきた一筋の雫を、
マドカは拭わぬまま、ゆっくりと目を閉じ、頷いた。
耳元で脈打つ彼の心臓の鼓動は、規則正しく優しく心に響いてくる。
時折窓を叩く雨の音さえも――今は耳に心地好かった。
しばらくして――
女主人にお茶の時間を告げようと入ってきたメイドに、士度は人差し指を口に当てながら合図を送った。
膝の上の姫君のあどけない寝顔は――見る者に和やかな笑顔を誘った。
甘く優しい匂いに鼻腔を擽られ、マドカは目を覚ました。
いつの間にやら彼の膝の上で寝入ってしまっていたらしい。
「目ぇ覚めたか?」
目を擦りながら士度の胸元から身を起こすマドカの耳に届くのは安らぎの声。
マドカは寝起きの自分に少し恥じ入りながらも、小さくコクリと頷いた。
すると手に暖かな感触が・・・・。
「ちょうど人肌程度の温度になったからな・・・ほら、これで冷えている指も温まる。」
ミルクが入ったマグカップを士度がマドカの手に包むようにして持たせたのだ。
「ありがとうございます・・・」
本当は、左手の指は冷えていなかったけれど。
彼がずっと握っていてくれたから。
それにあなたの体温に暖められて、洗われて――私を苛んでいた心の澱が嘘のように消えている・・・――
「・・・・温かいです。」
(このミルクも、あなたの身体も・・・心も・・・・)
肌に残る温もりに心が暖かくなっている幸せを抱きしめながら、
マドカは舌を潤すミルクと蜂蜜の甘さを、ゆっくりと嚥下した。
「だろ?蜂蜜も溶かしてもらったから、身体にもいい。」
背を預けてきたマドカの髪を弄りながら言った士度の台詞に、マドカの動きがピタリと止まった。
「・・・・メイドさん、ここに来たんですか?」
そもそも
「・・・・?ああ、ミルクを頼んだら持ってきてくれたぜ?」
――何でだ?――
微かに頬を染めながら士度を見上げたマドカに、不思議そうな声が降りてきた。
マドカは目を瞬かせた。
彼のこの反応は――
(士度さんが少しずつ・・・変わってきている?)
この屋敷の中で、
いや、もしかしたら変わってはいないのかもしれない。
―自惚れでなければいいのだけれど―
――それはとても嬉しいこと――
マドカは柔らかな微笑を湛えながら、残りのミルクをゆっくりと飲み干した。
そんな彼女の様子を士度は優しい眼差しで見つめている。
「気分、良くなったみたいだな。」
「ええ・・・!今ならいい音が出そうです・・・!練習、してきますね?」
マドカは少し名残惜しそうにしながらも、士度の唇に触れるだけのキスを落とし、
――ありがとうございました――
と呟くと彼の膝から降り、モーツァルトを呼んだ。
「ああ、また後でな。」
士度の言葉に晴れやかな笑顔が返ってきた――
そして居間の扉が静かに閉まる。
再び一人になった士度は、少し痺れた足を組み直し、ソファの背もたれに身を預けた。
夜の気配を漂わせ始めた空気が士度の頬を優しく撫でた。
そうさ、この想いはずっと変わらない。
――例えばお前が泣きたいとき、心が曇ったとき、俺が傍にいてやりたいと思う気持ち――
―自惚れでなければいいのだが―
それでお前が安らいでくれるのであれば――いつでも惜しみなくお前に温もりを与えたいという想い。
透き通るような蒼天の日も
空が泣く日も
白銀が天から降る日も
風が二人の間を駆け抜ける日も
この鼓動が止まるその刹那まで永遠に。
だから――
お前は
俺に遠慮なんざ、するな。
いつでもまた今日のようにやってきて――
――そして最後には俺に笑顔を見せてくれ――
誰よりも愛しく、守りたいその笑顔を。
士度はソファの傍らに放り出されていた事典を手に取ると、読みかけだったページを捲った。
ややすると、廊下の奥の扉が閉まる音がした――
彼は眼を閉じ、耳を澄ました。
バイオリンの旋律が聴こえてくる――
耳に届くのは、何度も何度も繰り返される同じメロディー。
それは優しく軽やかに弾むように心に響く癒しの音。
――彼女本来の――
安らぎの音。
士度はゆっくりと眼を開き――虚空に眼を細めると、
その視線を再び本へと戻した。
雨は相変わらず降り続いている。
しかし聞こえる雨音は柔らかだ。
今の彼女の旋律のように。
そんな雨の音に紛れて、ページを捲る乾いた音だけが
薄暗くなった居間に再び控えめに響いた。
Fin.
"rain or shine"―晴雨にかかわらず:どんなことがあっても
士度×マドカで、少ししっとりめのお話が書きたかったので・・・。
彼と彼女のある日の風景。
実験的に、似たような、または同じような文章を繰り返し使ってみました。
好き嫌いが割れそうですが;
たまにはこんなSSも…。