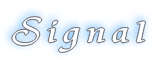
It is easy task to make up my mind to have nothing more to do with her.
彼女と縁を切ることは簡単だ――
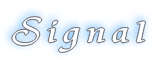
<Dr.Christmas!!>
忙しなく行き交う職員と看護師と医師でごった返す廊下の向こう側で知った声が聞こえたが、
士度は無表情に、綺麗さっぱり無視をした。目の前にいる――白衣から胸が零れそうな看護師が苦笑しながら、彼に次のカルテを渡してくる。
<次は…カーテン4号の30代の女性…足部痛・胸部痛、体温は38度、血圧110/80、脈拍110。>
――発痛時にタルボセットを服用したと本人は言っているけれど…
看護師の言葉を耳に収めながらカルテの既往歴の欄を目を通し、士度は片眉を上げた――知ったサインが、そこにある。
そしてタイミング良く――済ましたカルテをラックに置きに通りがかった同僚の卑弥呼を、目配せでこちらへ呼び寄せた。
<Dr.Christmas!!>
何?――士度に軽く返事をしながら、卑弥呼はただでさえ雑然としているERの中で大声を上げているもう一人の人物に向かって眉間に皺を寄せた――またあの馬鹿が…――しかし彼女の大きな眼はすぐに、士度の手の中にあるカルテへと集中する。
<このMrs.ハミルトン、昨日に続いてまた来たぞ…Dr.クルスが診てる。鎮痛剤を出しただけだ…。この間の
同僚の言葉に、卑弥呼の口角が不適に上がった――先日、Dr.クルスとは腹部痛の患者の所見を巡って(よりにもよって)患者の目の前で散々口論し、結果ER部長のDr.クロードに嫌味たっぷりに共々お灸を据えられたばかりなのだ――結局、所見の方も双方共倒れ、二人が口論している間に士度が診立てた虫垂炎の所見が当たり――Dr.クロードの許可を貰い、新人ながら緊急
どうだ?――
患者のカルテを差し出しながら、士度が処置を卑弥呼に促す。
<実際に患者さんを診てから改めて決めるけど…主訴と既往歴から…まずは血算、胸部X線写真、点滴…場合によってはモルヒネ投与かしら?>
ご名答――
<Dr.Christmas!!>
ますます近づいてくる声にまるで何の反応も示さずに、士度はカルテをそのまま卑弥呼に渡した。
士度の後ろに迫る声の主に冷たい視線を送りながら、卑弥呼は同僚にわざとらしく目を丸くしてみせる――士度は小さく、肩を竦めた。
<血算は特に網状赤血球値を調べた方がいいな…鎌状赤血球症の疑いがある。この患者はお前に任せるぜ。>
俺も手が空いたら様子を見に行くさ…――了解…!――二人はパンッと軽く互いの掌を合わせると、「そうそう、部長が午後の脳外の手術の見学、よければどうぞって…」――アンタ、買われてるわよ…――そう優しく言い残し、ヒラリと白衣を翻しカーテン4号へと消えていった。
<Thanks....>
<……
様子を見ていた看護師のからかう様な言葉に重ねて、
<でも医者と看護師は恋愛対象外なんだろ、Dr.Christmas!!>
――さっきから何度も呼んでいるのに、何だよ…お前は!!
先ほどから煩いくらいに大声で年間行事名を連呼していた当の本人が、ポンッと士度の肩にゴツゴツした手を置いてきた。
<誰ですか、Dr.Christmasって…>
士度は煩わしそうに軽く肩を上げ、さり気なくその手を払った。
いくら日系とは言え、短い名前に
――目の前にいるこの金髪に無精髭のデカイ医師が…
<…何ですか、このカルテは……>
ざっと目を通すと――そこには日本人女性らしき名前と、診断の欄に“鋭的外傷(切創)”の文字が。
<いや、これ、さ…診察3号に居る軽い外傷の女の子なんだけど生粋の
Dr.クルスは士度の代わりにヘヴンの手にあったカルテをひったくりながら悪びれもせずに言ってのけた。
<……あなたが女性の患者を譲ってくるなんて…明日は雨ですね…>
――それに大学の第三外国語は(ナンパ目的で)日本語を取ったって言っていませんでしたか?
<試してみたんだけどなぁ…やっぱりお前みたいな財閥の坊ちゃんが話すような英才教育的日本語じゃないと通じなさそうなお嬢さんだったからなぁ…?>
士度の冷めた言葉に、Dr.クルスも皮肉たっぷりに返答してくる有様で――士度は小さく片眉を上げると、不毛な会話はこれで終わりとばかりに――クルリと踵を返し、押し付けられたカルテ片手に3号診察室に消えていった。
<…財閥の坊ちゃん?彼が…?>
二人のやり取りを呆れたように見守っていたヘヴンが驚きの表情を隠さずにクルスを見上げた――
<そうだよ、知らなかった?Dr.Christmasはまだ此処に来たばかりだからねぇ…彼の爺さんがあのMRD財閥の総帥で、パパがMRD総合病院の院長兼外科部長、ママは小児科医なんだぜ?で、奴は総帥に溺愛されている将来有望なお孫様ってところで…一族に干渉されるのが嫌だから外科医の免許取立ての今は
――坊ちゃんは坊ちゃんなりに気苦労が多そうだねぇ……
カルテに目を通しながらクルスは隣の彼女に溜息混じりに説明してやった。“FUYUKI”の苗字はこのシカゴの医療界では伊達じゃない――知る人ぞ知る、医療・学問・芸術・環境分野における研究機関を携え、その成果もトップをひた走る日系財閥の――創設者の名前だ。
<MRD財閥って…私も看護学校に在学中に、そこの奨学金貰ったわ…>
――そういえば、“FUYUKI”って…気がつかなかったわ……
でも、そんな詳しい情報、どこから訊いたの?まさか本人からでもあるまいし――そんなヘヴンの言葉にクルスは、さぁ…と冷や汗混じりに笑いながら――診察してくるよ――と逃げるようにその場を辞した。まさかこの間公園でナンパして―― 一緒にお茶をした可愛い女の子が、MRD総合病院の美人看護師だったなんて――この気の強い恋人には、口が裂けても言えはしない。
クルスは渡されたカルテに従って、シャッと軽快な音を立てながらカーテン2号を開けてみた。
<Mr.セミマル、どうされ・・・・>
ましたか・・・――待たされ過ぎたせいか、具合が悪いせいなのか――難しい顔をした初老の男性がDr.クルスを睨みつけている。
やっぱりもっと日本語を勉強しておくべきだったのかもしれない――Dr.クルスの脳内を人知れず駆け巡ったその思いに気がつく者は、相変わらず医師と患者と看護師と職員でごった返す午後のERの中で――残念ながら一人もいなかった。
「お待たせ致しました、Miss.…Otowa?」
診察3号の診察台に左腕を乗せ、不安そうに目に涙を浮かべていた彼女は――士度の流暢な日本語を聞くや否や心からの安堵の表情を彼に向けた。
「良かった……日本語がお上手なんですね……Dr.クリスマスは……」
私、昨日、アメリカに着いたばかりで…英語は全然駄目なんです……――目の前にいる――見るからに温室育ちのお嬢様は、恥ずかしそうに頬を染めながら呟いた。士度の頬が刹那、僅かに痙攣した――あの馬鹿がつけたあだ名の余波がここにも・・・・
「……Dr.冬木です、よろしく。」
士度は白衣の胸元についている
初診の段階で既に洗浄してある傷は――親指の付け根から手首にかけて、細く長く引かれた紅い切創――見るからに痛々しいが、大事な神経や筋肉、腱は傷つけてはいないようだ。
ただ、少し大きな傷口故、縫合しなければならないが・・・
「何か…大きな刃物で切ったのですか?」
後から入ってきた看護師に縫合セットの注文をしながら、士度は音羽嬢に尋ねた。
「はい…あの…お昼にフランスパンでサンドイッチを作ろうと思って…パンを切っていたら…パンが逃げて…」
「パンが…逃げて?」
目の前にいる医者の顔に疑問符が浮かんだことに、彼女は気がつかなかった。
「はい、それで…パン切りナイフで……あの……手が動かなくなるとかは…ないでしょうか……?」
患者の語尾が少し震えた――そう言えば途中で引き継いだ為、彼女の職業を訊いていなかったが……
「指の運動も良好で傷も浅いですし、幸い神経や腱まで傷は達していませんので、傷が癒えれば今まで通りに動かせますよ。抜糸を入れても全治二週間程でしょう……」
ホッと――安堵の溜息が彼女から漏れる。濡れ羽色の真っ直ぐに長く美しい彼女の髪も――どこか安心するようにゆらりと揺れた。
士度はカルテに所見を書きながら片手間に――何か手を使われるお仕事なのですか…?――と、世間話でもするように訊いてみた。
普段は患者の職業など、あまり興味がないのだか――今日はなんとなく。
すると、やっと笑顔が戻った患者から、少し明るい声が飛び出してきた。
「あの…私、バイオリニストなんです。日本の音楽院を卒業したばかりなんですけれど…恩師の紹介でシカゴの交響楽団に招待して頂いて…来月から練習が始まるので……怪我、大したことなくて…本当に良かったです……」
愛らしく、春の日差しのような笑顔で彼女は微笑む――麻酔の準備をしながら、士度は久し振りにどこか新鮮な空気の中で――患者に接する雰囲気を味わっていた。
雑念が入る余地が無いほど毎日毎日仕事に明け暮れて――帰ってからは食事をして、眠るだけの毎日。
休みの日は――愛犬とジョギングに出たり、読書をしたり、好きなクラシックを聴いたり――ただ、それだけだ。
若い女性の患者なんて、日に何度も診察しているのに――久し振りに職場で日本語を話したからだろうか、朝から続いていた煩雑な忙しさの中に、心地良い涼風が吹いたような心持に士度を誘った。
「・・・・少し、チクリときますよ。」
麻酔の注射片手に士度が無表情にそう言うと、音羽嬢は慌てて顔を逸らし――ギュッと眼を瞑った。
士度の口元が小さく弧を描いた――カルテの生年月日から逆算してみれば、まだ18歳――自分とは六つも違う、やっと大人になったばかりの娘さんだ。
しかしその歳で日本の音楽院を卒業となると――あのお堅い国では珍しく、彼女も飛び級組なのだろうか――
――そんなことを考えながら、士度は手早く麻酔を済ますと、相変わらず怯えた面持ちでそっぽを向いたままの彼女に構わず――手際良く縫合を開始した。
縫う事は――得意だ。自分は恐らくこの院内では誰よりも――抜糸後の痕を残さないよう縫合することができるだろう。
チラリ・・・・と音羽嬢の視線が士度の手元に向けられる。
やがて――手を縫われているのに痛みを感じないのが不思議なのだろうか、それとも、縫合シーンが珍しいのだろうか――彼女の視線は完全に自分の手に固定された。
傷が閉じられていく過程をジッと見つめながら――時折、黙々と作業をこなす目の前にいる若い医者に視線をこっそりと――移しながら。
「あの・・・・私・・・・・この病院に日本人の先生がいらっしゃるなんて、知らなくて・・・・・」
残すところ三分の一まで縫合が進んだ頃、沈黙に耐え切れなくなったかのように――少しおどおどと音羽嬢が声を掛けてきた。
「・・・・?あぁ、正確に言うと、私は日系三世です。」
士度は刹那、視線を彼女に向けた後、再び縫合に集中しながら言葉を続けた。
「祖父が日本出身で、昔、アメリカに移住してきました。もっとも、嫁いできた母も日系人だった為、私の外見は日本人そのものですが――生まれも育ちも国籍も
だから日本語を話すのは本当に久し振りで・・・――若い医師が漏らした自嘲気味な言葉に、音羽嬢は目を丸くした。だって、彼は――
「
あぁ、それは・・・――パチン・・・と糸を切りながら、士度は苦笑する。
「日本人の誇りを忘れてもらっては困ると、日本語は幼いころから徹底的に習わされましてね・・・・所謂第二言語ですよ。正直、今のように敬語を話すのは特に苦手ですね・・・・」
いつになく、今日の自分は患者に対して饒舌だな・・・――そんな自分を不思議に思いながら、士度は縫合した跡に薄く化膿止めの薬を塗った後、音羽嬢の手に器用に包帯を巻いていく。
「そうなんですか・・・・あの・・・ドクターの・・・・先生の方が私よりも年齢が上とお見受けしますので・・・・!!お話するのが窮屈でしたらぜひ敬語は無しで・・・・」
どこか幼い彼女の進言に、それでも士度は珍しく――小さな笑みを作った。
「またいつか――もし、プライベートでお会いするような機会がありましたら、そうしましょう。」
――そう、これは社交辞令だ。
所詮は医者と患者――よっぽどの事が無い限り、院外で出くわすことなんか・・・・この広いシカゴでそうそうあるわけなんて無い。
終わりました、Miss.オトワ――
それでも彼女は――士度の言葉に嬉しそうに破顔すると、――ええ、ぜひ・・・・!ご縁がありましたら、宜しくお願いします・・・!――そう言いながらペコリと頭を下げるのだ。
「お大事に。」
この言葉も、平等に。
「どうもありがとうございました・・・・」
そして彼女は――真っ白な包帯に包まれた左手を、どこか大事そうに空いた手で触れながら、再び柔らかな笑顔で士度に向かって一礼すると、優雅な動作で診察室から出て行った。
カルテにペンを走らせながら、士度も彼女に軽く目礼を返した――すると、音羽嬢と入れ替わるように、息を切らせた卑弥呼が診察室へ飛び込んできた。
<手ぇ空いた!?左胸部銃創患者が運ばれくるわ・・・!!>
来て!!――卑弥呼の言葉と同時に士度が診察室を飛び出すと――すでにERの搬入口から、救急救命士と医師に慌しく付き添われた血塗れの患者がストレッチャーに乗せられ、緊急処置室に運ばれていく途中だった。
<左呼吸音無し、心肺蘇生して脈拍46の徐脈、脈拍微弱、頚静脈怒張・・・・!?猿回し!!後ろ・・・・危ねぇ・・・・!!>
<・・・・!?オイ・・・!!>
担当の
士度は反射的に、倒れてきたその痩躯を庇った――ストレッチャーは急ブレーキをかけたが――ドンッと鈍い音がして何かに弾かれたようにその金属の塊は止まった。
<Dr.冬木!?> <士度・・・・!!>
低く短い呻き声と――苛立たしげな舌打ちと共に士度は身を起こすと――
<俺に構うな!!患者が死ぬぞ!!行け!!>
そう言いながらストレッチャーを叩き、前進を促した。
<・・・!!Dr.クドーはDr.冬木とそのお嬢さんの処置を・・・!!Dr.クルスは私のサポートを・・・・!!>
やがて間髪を入れずの王医師の指示のもと――再びストレッチャーは処置室に向かって走り出す――慌てて後に続くヘヴンやクルスを目の端で見送りながら、士度は左腕に走る鈍痛にもう一度呻き声を上げた――
<そっちの子は?彼女もどこか怪我をした?>
士度の白衣ごと――昨日下ろしたばかりの真新しいシャツを処置用の鋏で切り裂きながら、卑弥呼はチラリと彼の腕の中にいる女性に目をやる。
<いや・・・・気を失っているだけだ・・・・大方血塗れの患者を目の前にして目を回したってとこだろう・・・・・>
銃創なんざ・・・日本人には免疫さらさらねぇからな・・・・――
そう呆れたように呟きながら、士度は自分の腕の中で青い顔をしている音羽嬢の顔を視線を向ける――どこか透明で、澄んだ美しさを持つ、彼女の貌。
日本人じゃなくても――血を見て目を回すなんざきっと――生粋の箱入りお嬢さんだ。
<・・・・全治一週間ね。>
立てる?――看護師からアイシングを受け取りながら、卑弥呼が士度の左腕にくっきりと浮かび上がった青痣に向かって溜息を吐く。
<・・・・俺も同じ所見だ・・・・>
士度は騒ぎを聞きつけてやってきた大柄の看護師に音羽嬢を託し、点滴を打つように指示を出しながら――壁に掛けてある時計に目を向け、眉を顰めた。
<脳外の見学は、今日は無理ね・・・・>
Dr.クロードなら分ってくれるわよ・・・――彼の無事な方の手を引くことで立ち上がることを助けながら、卑弥呼は静かに同僚を慰める。
<そうだ・・・・な・・・・>
どのみちこの腕じゃ―― 一週間は手術のサポートに入れない。
<女の子を助けたんだもの・・・名誉の負傷よ。>
珈琲でも飲んで、少し休みなさい――カーテン3号に運ばれていく――未だ意識が戻らない音羽嬢の姿が士度の視界を掠めたが、彼の足はそのまま卑弥呼と共に休憩室へと向かった。
当たり前のことをしたまでだ――
きっと彼女じゃなくても、そうしてた。
軽傷で済んだのも、普段の鍛え方が違うからだ――ただ、それだけのこと。
何よりもあのまま彼女がストレッチャーに轢かれてしまっては・・・・せっかく巧く縫合した腕の切創が台無しになってしまうところだったのだ。
当たり前のことを、したまでだ。
<お疲れ様でした、Dr.シド。>
退勤の名札を返すと、受付の男性職員がにこやかに挨拶をしてきた。
<あぁ、お疲れ・・・・>
士度は受付と軽く挨拶を交わし外へ出ると――夜の冷えた空気の中で、大きく伸びをした。
今日は確かに、本当に、かなり――疲れた。
ストレッチャーに轢かれた後、一休みしたはいいが・・・・その後そのまま夜勤のシフトに入って、すぐに集団食中毒の団体様がやってきたり、近所で火事が発生し、負傷者が雪崩れ込んできたり・・・・腕の打撲なんざ忘れる程の忙しさだった――そして今は丁度、日付変更線が変わる時刻。
銃創患者の血を見てぶっ倒れたお嬢さんも、先程意識が戻って退院したという――きっと近いうちに――抜糸の頃にまた会うことになるだろう・・・・・。
帰って・・・・熱いシャワーを浴びて、ブランデーでも引っ掛けて寝るとしよう・・・・明日は午後からの出勤だ――そんな事を考えながら士度が地下鉄の駅へ向かおうと一歩踏み出しかけたとき――
クスン・・・・――誰かがすすり泣く音がした。
辺りを見回して見ると・・・・・搬入口のベンチで、見たことのある彼女の姿が・・・・
「Miss.オトワ・・・・?」
どうしてこの時分にまだこんなところに彼女がいるんだ――そう思いながら声を掛けると――彼女は救われたように顔を上げたが――その愛らしい貌は直ぐに再び涙に濡れてしまう有様で。
「Miss.....一体どうしたのですか・・・・」
すると、とんでもない答えが返ってきたのだ――
お家の住所が分らなくなっちゃいました・・・・――と。
所属するはずの交響楽団が発行した保険証は仮の物で――住所なんざ書いてなかった。
昨日、シカゴの空港に降り立ったばかりの彼女は着いた翌日に手を負傷し、パニックになり――取るものも取り敢えず大急ぎでタクシーに飛び乗り――ただ傷を見せてホスピタルと告げて――ERに着たわけで。
目が覚めて、冷静になって思い返してみれば、出国直前に決まったばかりの新居の住所も場所も、まるでろくに覚えてなどいなかったのだ。
ただ、覚えているのは・・・・緑の屋根の、小さな二階建てのお家。近くには似た様なお家が一杯。お隣りのお家には黒い猫さんが・・・・。
そして通りの名前の頭文字は・・・・GとB・・・・。
「・・・・信じられねぇな・・・・」
こんな夜中に、もちろん探せる訳がなく・・・・。士度は呆れついでに面倒くさい敬語もかなぐり捨てた。
もう勤務外だ院外だ。英語は皆目喋れないわパンを逃がすわ血を見てストレッチャーにダイブをするわ・・・・挙句の果てには帰るお家が分らないときたもんだ。
「ごめんなさい・・・・ドクター・・・・ごめんなさい・・・・」
地下鉄の隣の座席で小さくなって・・・涙声を出している彼女に、士度は溜息混じりに呟いた。
「“士度”・・・・でいい。勤務時間外にまで“ドクター”なんざ呼ばれると、疲れがとれねぇよ・・・・」
ぶっきらぼうだが、どこか優しい声に――音羽嬢は少し安心したようだった。
「ありがとうございます・・・・私・・・・下の名前は“マドカ”です・・・・“Miss”を付けられて呼ばれるのにはなんだかまだ慣れないので・・・・!?」
グ〜キュルル・・・・・
可愛らしい音が、二人だけの車両に響いた。
「腹・・・・減ってるのか・・・・」
笑いを噛み殺すような声に居た堪れなくなり、マドカは真っ赤になりながら顔を両手で覆う。
「・・・・・パンを切り損なったので・・・・朝、ヨーグルトを食べたきり何も・・・・」
食べてないんです・・・・――細い喉が恥ずかしそうに小さな声を絞り出した刹那、電車が駅の名前を告げながら止まり――徐に士度が立ち上がった。
「降りるぞ・・・・」
マドカも慌てて彼の後に続く――降りた駅の目の前に並ぶのは、どこか少し高級感が漂う、住宅街。
淡い外套が並ぶ静かな小道を、士度は歩を大きく進めながら――静かに歩いていく。
マドカも彼に遅れまいと、少し歩を早めながら懸命についていった――時折、視線を上げると目に映るのは――無表情でいて精悍な、彼の貌。
大丈夫・・・きっと、大丈夫・・・・・明日、一緒にお家を探してくれるって言ったもの・・・・――彼はきっと、いい人だわ・・・・・・
歩くこと10分程――小さな眩暈がマドカを襲い始めた頃、二人はようやく士度の家へ着いた。
おい・・・・大丈夫か・・・?疲れてるなら、シャワーを先に浴びるか・・・・?――そんな士度の声さえも、遠くに聴こえる程―― 一日の疲労感がドッとマドカの躰を覆っていた。
待ってろ、今、タオルを・・・・・シャワー・ルームは
しかし、まず目に入ったのは――フカフカの・・・・・
<マジかよ・・・・>
バスタオルとハンドタオルを手に戻ってきた士度は、寝室のダブルベッドの端っこで――無防備に眠る音羽嬢の姿に、頭を抱えた。
余程疲れていたのか――小さく、愛らしい寝息を立てながら、彼女は深い深い夢の中。
<まったく・・・・襲っちまうぞ・・・・・・・>
心にもない事を呟きながら――そのままでは寝にくかろうと、士度は彼女のブラウスの襟元と袖のボタンを外してやり、寛げてやる――彼女の白い肌が、診察室で見たときよりもより扇情的に、彼の視界に飛び込んできた――
<・・・・・・・・>
靴を履いたまま、その痩躯だけをベッドに預ける姿勢だった彼女の靴を脱がし、起こさぬよう、その身をベッドカバーの上にそっと横たえると――ロングスカートの流れが、彼女の細く形の良い脚のラインを滑らかに浮かび上がらせる――
キシリ・・・・と、士度が体重を掛けた分だけ、ベッドが鳴いた。
そして彼は、長く、少し節くれ立った男らしい指を彼女の白く、柔らかそうな頬へと伸ばした――
しかし、その指は――刹那の距離で躊躇うようにピクリと動き――
彼女と縁を切ることは簡単だ――
理由があるにせよ――無防備に・・・・今日出会ったばかりの男の家に足を踏み入れ・・・・無防備にそのベッドで眠る彼女を組み敷いて――男の
それとも――
翌朝、彼女の無知と無計画さを非情にも説いて、さっさと追い出してやるのもいい――
彼女と縁を切ることは――至極、簡単なことだ――
数分後――彼は予備の毛布と共に居間のソファに寝そべっていた。
腹を満たしたシェパードが、不思議そうに主の様子を伺ってくる。
<今日ハ、女ト一緒ニ寝ナイノカ・・・?>
<別に・・・・ただの・・・・今日会ったばかりの迷子の女だ・・・・それに女だからって手当たり次第に食う趣味はねぇよ・・・・>
欠伸混じりの気怠そうな声と共に、毛布を手繰り寄せる音がする。
<フーン・・・・>
確かに・・・・士度が今まで連れてきた女とは毛色が違うしな・・・・――愛犬トマもうつった欠伸をしながら、自らも寝の体勢に入り・・・・目を瞑る直前にもうひとつ訊いてみた。
<シャワーハ?浴ビナイノカ・・・?>
<・・・・・シャワーの音で女が起きたらまた飯だ何だで面倒くせぇだろ・・・・明日だ、明日・・・・・・>
もう寝るぞ・・・・――
そしてリモコンの電子音の後――広い居間は暗闇と静寂に包まれる。
トマがもう一度、大きな欠伸をした。
<・・・・・・・・・・>
士度は暫くの間、真っ暗な天井を見つめていたが――
やがて彼は――翌朝のことについて考えることを、綺麗さっぱり放棄した。
その夜――マドカは久し振りに、心地良い夢の中にいた。
飛行機のエコノミーシートとも・・・・マットレスを買いにいけなくて仕方なく寝そべった硬い床とも違う、柔らかなベッドの上で、羽毛の毛布に包まれながら―-
手を切って沢山沢山、血が出て――絶望の淵に立たされたことなんて、遠い遠い昔のようだった。
夢の中でマドカは――もしかしたら、米国での生活に・・・・思ったよりも早く慣れることができるのかもしれない――そんな風に、フワリと宙にでも浮かぶ気持ちで感じていた。
だって・・・・二日目で早速・・・・優しい人に出会えたから。
きっと・・・・良いお友達になってくれる・・・・そんな気がする人だから。
Fin.
ついに・・・・趣味が暴走・・・。
英語と医学用語でツッコミ処有り有りの場合は・・・・素人管理人にコッソリアドバイス下さると嬉しいですv(o_ _)o))
◇ブラウザを閉じてお戻り下さい◇