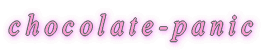
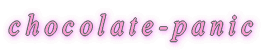
本日快晴なり。
「おはよう、小鳥さん・・・!」
琴音は窓辺で小首を傾げながら囀る小鳥に朝の挨拶をすると、涼やかな空気を吸い込み、鏡の前でもう一度ターンをした。
よし、今日のコーディネートもバッチリだ。
そしていつも通り、隣にいる兄を朝食に誘おうと思ったのだが・・・ふとカレンダーを見て、ドアノブにかけるはずだった手を躊躇いがちに下ろす。今日は・・・ギリギリまでそっとしておいてあげよう。
いつもは琴音よりも早く朝の支度を終えているはずの士音の部屋は、今日ばかりはシン・・・と静まり返っていた。
そして琴音は机の上に用意しておいたギフトボックスと大きな袋を手に取ると、鼻歌を歌いながら一人階下へと降りていった。
「はい、士度さん・・・!ア〜ン!」
「・・・・・」
モーニング・ルームに入ってすぐ琴音の目に飛び込んできたのは、母親が満面の笑みで父親の口元にチョコレートを差し出す甘い光景。新聞を開いた格好で、促されるままに黙ってチョコレートを口にする父親も、相変わらず分かりにくい表情だが、まんざらでもなさそうだ。
「今年は抹茶味にしてみましたv美味しいですか?」
「・・・・悪くねぇな。」
「・・・!!じゃあ、もっと食べてくださいな・・・!」
「・・・マドカ、朝飯・・・」
朝食そっちのけで嬉々として夫にチョコレートを差し出す妻の姿に、士度は小さく溜息をつきながらも、彼女の手作りチョコレートをもう一つ咀嚼した。ああ、もうこのチョコレートだけで朝から腹一杯になりそうだ・・・。
「・・・ママ、パパ、おはよう・・・」
朝から万年新婚夫婦のバカップル振りを見せ付けられた琴音は、娘の存在を無視していちゃつく両親にやっとのことで声をかけた。
「あら、琴音。いつの間に降りてきてたの?おはよう。」
母親はキョトンとしながらも、娘にいつも通り素敵な笑顔で朝のご挨拶。続いて父親からも少し元気の無い「おはよう」の一言が返ってきた。
「・・・士音はどうした?」
いつもは二人揃って降りてくるはずなのに、今日は息子の姿だけが見当たらない変化に気がついた士度は、新聞を畳みながら琴音に訊ねる。
「えっと・・・・ね、ほら・・・・今日は2月14日だから・・・・」
―でも、皆勤賞がかかっているから、ギリギリには降りてくると思うけれど・・・―
「そうか・・・」
士度は少し気の毒そうな顔をしながら、適度に冷めた珈琲を一気に飲み干した。
士度のカップが空になるのと同時に、脇に控えていた執事が、すぐさま珈琲を満たしにやってくる。
その二杯目が空になるのも非常に早かった。
「士音は今年、いくつチョコレートをもってくるのかしらねぇ・・・」
一人のほほんとそう言うマドカに、
「ホント、今年は私たちもいくつチョコレート・ケーキを作れるのか、想像ができませんわ。」
メイドがコロコロと笑いながら相槌を打った。
「あ、パパ・・・!これ、私から!」
琴音はマドカに良く似た満面の笑みと共に、一緒に持ってきた大きなギフトボックスを、徐に士度に差し出した。
士度は苦笑しながらも、娘からの毎年恒例のプレゼントを礼を言いながら受け取る。
「今年の隠し味はワサビよ・・・!」
ゴホッ・・・
再び珈琲に口をつけていた士度が大いにむせた。
「あらあら、士度さん・・・大丈夫?」
隣に座っているマドカが慌てて士度の背中をさすり、執事は珈琲の追加を淹れるために足早にその場を辞した。
「さ、食べてみて・・・!」
「琴音・・・」
キラキラと目を輝かせながらこちらを凝視してくる娘の眼差しを一身に受けつつ、士度は恐る恐るその“外見はまともな”チョコレートに手を伸ばした。
結局、士音は朝食の時間には降りてこず、出掛ける時間ギリギリになってやっと玄関に姿を現した。
「お前・・・なんて顔をしてるんだ・・・」
ほら、シャンとしろ・・・・士度はそう声をかけながら、シャンプーの最中の猫のような顔になっている息子の肩を叩いてやる。
「・・・父さんこそ、今朝は何だか顔色が悪いよ?」
同情と共感を含んだ士音の声に、士度は力なく笑うしかない。自分は今日はきっと、朝から晩まで珈琲三昧だ。
そして士音は力無く「いってきます・・・」と言うと、琴音に手を引かれながら学校へと向かった。
メイドが用意してくれた、サンタが持つような白く大きな袋を手にして。
「いってらっしゃい〜!」
士度の隣ではマドカの明るい声が息子の背中を押している。
―頑張れ、息子よ。これも修行だ・・・―
士度は力なく袋を引きずる息子の後姿を、眉を下げながら見送った。
![]()
士音は自分の下駄箱の前まで来て、回れ右をしたくなった。
確か学校にお菓子を持ってくることは禁止をされているのではなかったのか?
特に毎年毎年2月13日の朝礼のときには、校長先生が口を酸っぱくして言っていることなのに・・・。それなのにどうして俺の下駄箱は、俺の上履きが見えないくらいに、カード付きの赤白青色とりどりの箱で埋もれているんだ・・・?
「今年も凄いわね・・・あ〜あ、一年生の子まで・・・・ほら、士音ちゃん、予鈴が鳴っちゃうから早く詰めちゃおう?」
琴音は下駄箱から転がり落ちているチョコレートの箱を確認しながら、ぼんやりと突っ立ている士音に声をかけた。
「あ〜・・・うん・・・・」
士音は覇気無く答えると、袋を広げて大中小のギフト・ボックスを琴音と一緒に無造作に放り込み始めた。
「おう、冬木・・・!大変だな!もうすぐ予鈴が鳴るぞ!」
ジャージ姿の六年生の担任が、カカカカカと笑いながら下駄箱の前を通り過ぎていった。
(じゃあ手伝ってくれよな・・・!)
士音は眉を寄せて心の中で悪態をつきながらも、黙々と作業を続ける。
袋が半分くらいまで一杯になった頃、ようやく二人は教室に向かうことができたのであった。
「あ、士音!おはよう!」
教室に入って一番に迎えてくれた孝太の明るい挨拶に士音は少し救われた気分になる。しかし、自分の机の上の有様を見て・・・・士音はがっくりと膝をついた。チョコレート・ボックスが士音の机の上に山のように盛られている。机の中にまで小さな箱が押し込まれ、椅子の上にも処狭しと積み重ねられている。
「おや、士音君・・・もう袋が半分埋まっていますね!僕が数えたところによると、士音君の机の上には23個、机の中には12個、椅子の上には19個のチョコレートがありました。袋の中身をあわせると、きっと去年の73個の記録を大幅に超えますね・・・!」
―おめでとうございます・・・!―
秀一の明るい声が士音の頭の上で木霊し、鈴香はニコニコしながら手を叩いている。
士音はハハハ・・・と力なく笑いながら、自分の座るスペースを確保すべく、掻き集めるようにしてチョコレートを袋の中に入れ始めた。
(女って・・・・女って・・・・みんなみんな、大馬鹿野郎だ・・・・!!)
どうしてろくに言葉も交わしたことがない相手に、こんな高そうな包みの菓子を買ってきたり、わざわざ時間をかけて手作りチョコを作ったり、懇切丁寧にカードを書いたりできるんだ・・・!?だいたい俺が甘いもの苦手だってこと、どれだけの人間が知ってるっていうんだ!許されるなら全校集会で校長のマイクをひったくって、あらん限りの声で叫びたい・・・・「チョコレートなんてもう沢山だ!」って・・・・それに来月!貰った人数に返す分だけのクッキーを焼かなきゃならないこっちの身にもなってみろ!さらに言ってみれば、チョコレートなんて動物の餌にもならないわけで・・・・
「士音君・・・?何だかお顔が怖くなってるよ・・・・?」
いつの間にか袋詰めを手伝ってくれていた麻弥の声に、士音はハッと我に還った。予鈴のチャイムが鳴る中、顔を上げると麻弥と目がかち合った。
「・・・そんなことねぇよ。俺は元々こんな顔だ。」
麻弥の気遣うような視線に、自分の心を見透かされたような感じがして、士音はわざとぶっきらぼうに答えながら席に着いた。
机の横には大きく膨らんだ袋がドンッと幅を利かせている。
それはホーム・ルームの為に入ってきた担任の先生の目にすぐ留まる位の大きさで・・・。
「・・・冬木君、チョコレートはお家に帰ってから開けてね・・・」
士音は、顔を引きつらせながらそう言った女性教師から目をそらした。そんなこたぁ、言われなくても分かっている。
(後で少し分けてくれよな・・・!)
孝太の呑気な声でさえ、頭痛の元になり始めてしまった。
![]()
帰りのホーム・ルームが終わると士音は誰よりも先に教室を出て、帰路についた。サンタクロースよろしく、大きな袋を肩に担いで。琴音が4階の教室から「ちょっと待ちなさいよ・・・!」と声をかけてきたが、「先に帰るぞ・・・!」と合図を送りながら士音は歩むのを止めない。今日は後からチョコを渡しにやってくる輩から逃れるために、士音は休み時間のたびに屋上へ逃げた。4組の男子は琴音がばら撒いている手作りの一口サイズのプチチョコを貰って歓喜の声を上げていた。あいつらも馬鹿だ。琴音の目的は来月のホワイトデーに決まってんだろ?1クラス最低でも15人にそのプチ義理チョコを渡したとして、琴音の場合何も言わなくても確実に15人分の倍返しをゲットする。バレンタインデーとホワイトデーって何かおかしくねぇか・・・?どうして大して苦労もしてない琴音が楽に良いものを手に入れて、重くて甘くてうざくて辛い思いをしている俺が苦労して大量のクッキー焼かなきゃなんねぇんだ?それより何より、もうチョコレートの香りで頭が変になりそうだ・・・。
士音が一人広い校庭を痛む頭を抱えながら闊歩していると、校門の方から士音の名前を呼ぶ高い声が・・・・。さらなる頭痛の種が駆けてくる、栗色の長い髪をなびかせて、両手を広げて・・・・後ろからは「姉さん!待ってよ・・・!」そんな遠慮がちな声が聴こえてきたり・・・。士音は袋を下ろして校庭の真ん中でへたりこんだ。
「士音〜〜!!会いたかったわ!!」
「テメーら!学校サボって来てんじゃねぇ!!」
楓と峻、薫流と劉邦の子等の家は新宿から片道五時間、この時間にここにいるってことは、確実にサボタージュだ。
「ご、ごめんね、士音・・・年に一度だけだからどうしてもって姉さんが・・・・」
一杯になった袋に身をもたせかけ、グッタリとしている士音の耳に、峻のオロオロとした声が虚しく響く。
「はい、士音・・・!今年はお手製のどんぐりチョコよ・・・!」
楓は士音の状況などおかまいなし、リボンを施した笹の包みを士音の胸元に押し付けた。
鼻を擽る甘過ぎるほど甘い匂いに、士音は内心舌打ちをしながらも、とりあえずその包みを受けとりながら立ち上がった。
すると、背後で「士音君〜!」と彼の名前を呼びながら、息せき切って走ってくる一人の少女が・・・・麻弥だ。
彼女の姿を先に目にした楓の雰囲気が変わった。
「・・・誰?」
「・・・クラスメイトだよ・・・」
後ろを振り向きつつ、どーでもいいだろ、そんなこと・・・と士音は一人言ちながら背伸びをした。
士音の隣まで駆けてきて、大きく息をついた麻弥の目にも、彼女を睨みつけている楓の姿が目に飛び込んできた。
「誰・・・?」
「!!〜〜私は士音の将来のおよめ・・・・ン〜〜!!」
楓の突然の衝撃発言は、峻と士音のとっさの口封じで最後まで音をなさなかった。
暴れる楓を、弟の峻が引きずるようにして校門付近まで引っ張っていく。
(〜〜!!ちょっと!何するのよ・・・・!)
(姉さん!また余計なことを言うと、士音に嫌われちゃうよ!?)
隅でコソコソと諌め合いをはじめた姉弟に呆れた溜息をつきつつ、
「従兄弟みたいなもんだよ・・・」
と士音は麻弥に答えてやった。
麻弥は少し安心したように小さく息を吐く。しかしその顔にはすぐに紅がさし・・・。
「そう、なの・・・。あの、ね、士音君・・・もう沢山持っているからいらないかもしれないけれど・・・チョコクッキー、作ってきたの・・・クッキーなら、士音君も少しは食べられるかなって・・・・。その、貰ってくれたら嬉しいな・・・」
麻弥は顔を真っ赤にして俯きながら、赤いリボンが掛けられた小さな丸い缶を差し出してきた。
「あ〜・・・・」
―もういらねぇよ・・・・―
勘弁してくれ――ホントはそう言いたかったけれど・・・・ふと脳裏を過ぎったのはいつか聞いた父親の言葉。
―女がくれるって言ったものは、毒や爆弾でもない限り、とりあえず貰っておけ・・・―
(・・・?どうして?)
―お前にも、そのうち分かる・・・―
今ならなんとなく、分かるような気がした。
ここで断ったら北嶋は確実に泣くだろう・・・・そんな気もした。
“女は泣かしちゃいけない”―これも父さんから学んだ鉄則だ。
(つまり、俺の選択肢は一つしかないわけで・・・)
「ありがと・・・」
士音は小さくそう言いながら、その丸缶を麻弥の手から受け取った。
瞬間、麻弥の顔がパッと明るくなり、満面の笑みがその貌を飾った。しかし・・・
士音が白い袋を開けて、楓からの笹の包みと、麻弥からのクッキー缶をその袋の中に入れようとしたとき、
「「あ」」
という声が二人の少女から上がった。
その声に弾かれるようにして顔を上げると、麻弥が今にも泣き出しそうな顔をしている。
後ろを向くと、楓も目を大きく開いて悲しそうな顔をしている。
そして二人の物言う視線が士音にグサリと突き刺さってきた―
―その袋の中に、いれちゃうの?―
その他大勢のチョコレートと、一緒にしちゃうの・・・?
(・・・どこら辺を・・・どう特別扱いしなきゃなんねぇんだ・・・?)
身を不自然に屈めたまま石化し、冷や汗を流す士音に助け舟を出したのは、校舎から駆けてきた琴音だ。
「はいはいはい、士音ちゃん〜!もう帰りましょ・・・!あら、あんたたち、来てたの?」
―じゃあ、手伝いなさいよ―
琴音は手際よく袋の口を閉めると、遠慮なく峻に袋を持つように促した。士音の手には二つのギフト。
峻は士音の方を気の毒そうにチラリと見ると、嫌な顔一つせず袋を担ぎ上げた。
「ほら、行くわよ・・・!」
琴音はグズグズしている三人を促し、士音の手を取って歩み始める。
「じゃあな・・・」
士音は麻弥に軽く手を降り、琴音に引っ張られて行く。
「士音君・・・!」
回り角に一行が消える前に、麻弥が声を上げた。
士音は歩みを止め、チラリとその視線を麻弥に向けた。
「わ、私・・・士音君だけだからね!そのチョコクッキーをあげるのは!」
顔を真っ赤にしながらそう叫んだ麻弥に、士音はもう一度麻弥から貰ったクッキー缶を小さく上げて振った。
そして琴音と楓に引っ張られながら、電柱の向こうに消えていった。
そんな彼の後姿を、麻弥はどこか晴れやかな気持ちで見送っていた。
![]()
「ラスト、87・・・五年三組の東雲・・・愛子さん・・・・誰よ、これ。『士音君、今度一緒にデェトしよv』って・・・するわけないじゃない・・・」
琴音は士音の部屋で本日87個目のチョコレートの欠片を齧りながら、バレンタイン・カードを読み上げた。
士音は読み上げられたクラスと名前をリストに記載していく。ホワイトデーのお返しの為だ。
「・・・・そんなマメなことしてるから、チョコの数が増える一方なんじゃない?」
楓もお裾分けのチョコを口に含みながら、呆れたようにリストを覗き込む。
「でも、貰いっぱなしはいけないって、父さんが・・・それより琴音、お前今年は学校でいくつばら撒いたんだ?」
士音のその言葉に、琴音よりも峻が大きく反応した。
「こ、琴音ちゃん・・・!もう誰かにチョコレートをあげたの!?」
小鹿のように大きな目を潤ませながら、突然声を上げた峻に、琴音はラッピング・ペーパーを畳みながらそ知らぬ顔をして答える。
「う〜んと・・・今年はクラスの男子と各クラスから欲しいってやってきた子にあげて・・・23個かな?」
その数を聞いた瞬間、うんざりしたような顔をした士音と楓をよそに、「あ、ついでだから峻にもあげるね!」と琴音は小ぶりのギフトボックスを机の上から取ってきた。「あ、プチチョコじゃねぇ・・・」そんな士音の声に、峻の顔が一気に喜色ばんだ。
「あ、ありがとう、琴音ちゃん・・・!」
「うん、手作りよ。義理だけど!」
あっけらかんとそんなことを言われ、峻の眉が今度は悲しそうに下がった。
「え・・・琴音ちゃん・・・本命、いるの・・・?」
「何言ってるのよ、本命はパパに決まってるじゃない・・・!で、準本命が、士音ちゃん!」
峻の表情が刹那、明るくなったが、次の瞬間には複雑なものに変わっていった。
(士度おじさんなら・・・なかなか超えられない壁としていいとして・・・でも士音よりも下って・・・)
「オメーのは義理のファーストクラスだよ・・・たぶん」
少し曇った表情でギフトボックスを見つめる峻に、士音が慰めるように声をかけると、峻の表情にまた光が射した。しかし、
「峻のチョコの隠し味は・・・キムチにしてみました!」
そんな琴音の言葉に、峻の顔色は見る見るうちに蒼くなる。
「・・・・多分、俺のたくあんよりもマシだよ・・・」
もう峻の気持ちは浮上して良いのかどうかすら分からなかった―アンタ、その百面相どうにかしなさいよ・・・―
姉の容赦ない言葉すら耳に入らないほど、峻はこれから食すこのギフトボックスの中身を想像することに必死だった。
「ねぇ、士音・・・こんなにたくさんのチョコレート、いったいどうするの?」
まさか全部食べるわけじゃあるまいし・・・袋の中を覗き込みながら、楓はその匂いに眉を顰めた。
「・・・種類わけして、全部溶かして・・・・メイドさんたちがチョコレート・ケーキとかチョコムースとか作ってくれるんだよ。そしてご近所にお裾分けしたり、一週間、デザートには必ずチョコなんとかがついてきたり・・・」
おかげでここ数年、この時期になると回ってくる「冬木さんちのチョコケーキ」はご近所ではちょっとした季節の名物だ。
デザートのことも、考えるだけでウンザリだ・・・そう言いながら舌を出す士音の首筋に、楓が突然しがみついてきた。
「私のも溶かしちゃうの・・・!?せっかく一生懸命作った本命チョコなのに・・・」
「・・・ドングリに直接チョコをコーディネートしたものなんて・・・溶かせないだろ!北嶋のチョコクッキーもだ!」
「――!!じゃあ、そのチョコクッキーはともかく、私のドングリチョコはみんな士音が食べてくれるのね・・・!」
目を輝かせながら士音を抱く腕に力を込めた楓を、士音は振り払えないまま脱力していた。
(言えねぇ・・・外側のチョコレートを削いで、中身は庭にいる連中にやろうとしてたなんて・・・・)
そんな士音の横では、峻が半分涙眼になりながら、赤い粒が入ったチョコレートを琴音に促されるままに齧っていた。
「お、美味しいよ・・・琴音ちゃん・・・」
引き攣った笑顔の中でも、精一杯の思いやりを口にのせながら。
峻にとって琴音の微笑みが一番の――胃薬だった。
![]()
学校をサボってきたおかげで、今回楓と峻は最終バスで帰路につくことになった。
家に帰ったら、黙って抜け出してきたことに父が烈火のごとく怒るだろうが、いざとなったら琴音のキムチチョコを食べさせればいい――楓は峻にのんびりとそんなことを言った。
「・・・っダメだよ!これは僕が全部食べるんだ。」
帰りのバスの中で、峻は大事そうにギフトボックスを抱え込んだ。
キムチ味だろうと、義理だろうとなんだろうと、琴音ちゃんが僕のことを思って作ってくれた世界でたった一つのチョコレートだ。
誰にも渡すわけにはいかない。
「アンタ、お腹壊すわよ?」
呆れたようにそう言ってくる姉に、
「慣れればこれも結構案外美味しいよ・・・!」
と峻はむきになって反論する。
―来年はどんなチョコを作ろうかな・・・・あ、その前に士音の誕生日が・・・―
楓は帰り際、ぶっきらぼうに一言、
「わざわざ遠いとこから来てくれて・・・とりあえず、ありがとな」
と言ってくれた士音の表情を思い出した。
それはきっと、来年の今日までの・・・いや、ずっとずっと大切な宝物。
楓はお土産に貰った「冬木邸メイドさんズお手製チョコレート」の包みを開け、一口食してみた・・・・確かに、美味しい。
(こんな美味しいチョコを作れるようになるのは、きっとまだまだ先だろうけれど・・・でもきっと・・・・私のチョコには愛情エッセンス満載だから・・・・)
―士音も美味しく食べてくれるよね・・・?―
バスの窓を通り過ぎていく夜景を見つめながら、琴音はもう一度、士音の顔を思い浮かべ、眼を細めた。
![]()
和室で一家団欒、お茶の時間――士音の目の前には、チョコクッキーとドングリチョコの山盛りが。
「・・・父さんも、食べてみる?」
そんな士音の問いに、マドカの膝枕の上でグッタリとしている士度は手を振ることで断った。
「パパ、今日はお仕事なかったはずなのに・・・・どうしてそんなに疲れているの?」
「日頃の疲れが出たのよねぇ・・・士度さん・・・?」
士度の硬い髪を戯れに弄りながら微笑むマドカの膝を、士度は子供たちに見えない角度でそっと撫でた。
抹茶チョコから始まって、チョコレートソースのデザートに、ブランデーチョコにチョコレート・ドリンク・・・
「年に一度ですし・・・!」
そう言いながら嬉々としてお手製チョコを振舞うマドカに付き合っていたら、この有様だ。
琴音のワサビチョコのパンチもかなり効いたが・・・・。
士音はそんな両親の姿に眼を細めながら、口の中で転がしていたドングリチョコを噛み砕いた。
チョコレートの甘さの後は、適度にふやけたドングリを飴玉みたいに転がせて、悪くない・・・・かも?
次いで、麻弥のチョコクッキーに手を伸ばす。先に食べた琴音がクスクスと笑っている。
「・・・・っ苦ッ・・・」
焦げているのか、ビターチョコの味なのか・・・もはやどっちなのか分からない絶妙かつ複雑な味だが・・・・。
「甘いチョコよりは・・・マシかも・・・な。」
緑茶片手に士音はチョコクッキーをサクサクと食し、二枚目に手を伸ばした。
足元で味見をしたがっているシベリウスに、
「やめておけ・・・」
と声をかけながら。
今年もやっと終わった2/14――それでも冬木邸からは暫くの間、チョコレートの香りが途絶えることはなかった。
Fin.
駆け足でしたが、七緒様・・・!大変お待たせ致しました!バレンタイン・リクエストでございます。
久し振りに峻と楓を書くことができて、非常に楽しゅうございました♪次回はもっと出番を増やして峻と楓を書いてやりたいと思います☆2/14は士音にとって永遠の厄日です・・・恐らく。そんな中でも楓と麻弥の存在はちょっとした清涼剤に・・・なるのでしょうか・・・;久し振りに書いた双子モノですので、突っ込みどころ満載ですが;少しでも楽しんでいただけたら幸いです。
素敵なリクエストをどうもありがとうございました、七緒様!
またのチャレンジをお待ちいたしております。