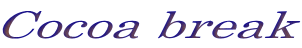
たまに此処を訪れるのは、此処のココアが美味しいからだとか、
此処が父さんと母さんの行きつけの喫茶店だからだとか、
映画に行った後は琴音が必ず「どこかでお茶していきたい!」というからだとか……。
とにかく、最近は一月に一度くらいは此処を訪れているような気がする……。
父さんと母さんについて来たりすると、二度とか三度とか。
カウンターからはときどきマスターの煙草の匂いがする――
これが父さんの天敵の蛇ヤロー“さん”の場合は煙草の“臭い”をいつも振りまいている。
(大人には“さん”付け――って教わったから仕方なく)
大体、珈琲片手に煙草を吸うなんて珈琲を味わうも何もないじゃないか…といつも思う。
(“珈琲は大人の飲み物”だから、その味の良さはイマイチまだ解らないけれど、
父さんが好きなんだからきっと自分もいつか好きになるんじゃないかな)
アルバイトのお姉さんが淹れてくれるココアも美味しいけれど、マスターが淹れてくれるともっと美味しい。
家でも執事さんやメイドさんが美味しいココアを淹れてくれるけれど、やっぱり此処のココアは“何か”が違う。
秘蔵のココアを使っているんだとマスターは言っていたけれど、本当のところはどうなんだろう?
――そういうわけで、今日もいつも通りココアを頼んだ。
夏だけど腹を冷やさないようにとりあえずホットで。
カウンターの隣に座っている琴音はヘヴンさんと今日観た映画の話をしている――
スーパーヒーローとスーパー“ヒロイン”が出てきたのがえらく気に入ったらしい。
――女の子はどちらかというと適度にお淑やかな方がいいと思うんだけど。
俺の逆隣に座っている卑弥呼さんはファッション雑誌を何となく捲っている――この人の隣は静かだからなんとなく好きだ。
その隣の席の銀次さんは美堂蛮と(“さん”付けはもう面倒くさい)仕事が多い少ないの話を相変わらずしている。
テーブル席に座っている笑師さんと亜紋さんは、こちらも相変わらずネタの打ち合わせ。
亜紋さんは魔里人なのに、なんで漫才師みたいなことをやっているんだろう?――
「そういえば士音君は初めて此処にきたときからココアだね…?」
鍋にたっぷり入れたミルクを火にかけていたマスターが小さく笑いながら不意に声を掛けてきた。
「え…?そうなんですか?」
俺の代わりに不思議そうに返事をしたのは琴音。卑弥呼さんが雑誌から顔を上げた――
アルバイトのお姉さん達も何故か満面の笑みを浮かべている。
「正確に言えば、“物心ついてから”初めて此処に来たときよね〜?赤ちゃんの頃もベビーカーに乗せられて一度来たことあるけれど、“子供には煙草の臭いがきつ過ぎる”って士度さんとマドカちゃん、直ぐに帰っちゃったものね?」
夏実さんの台詞に卑弥呼さんが「そういえば……」と懐かしそうに眼を細めた――そうだっけ?
「……此処に初めて……いつだったかな……」
赤ん坊の頃はともかく、物心ついてからって……――
「――!!確か小学校入学したての頃やったで!まだまだピカピカのランドセル背負っててな、確か……」
「参観日の帰りだったんだよね?士度が髪上げてスーツにコートとか、いつもと違う格好してたからよく覚えてるよ。あの頃はまだ二人とも“小っさい”ってイメージあったのになぁ……」
いつの間にやらこんなに大きくなってしまって……――それは言わん約束やで婆さんや……!――
……笑師さんと亜紋さんは何時の間にやら漫才モードに入っている――
父さんはこの二人の漫才に笑ったことがあるのだろうか?
「あぁ、そーだった、そーだった……士音なんてそこのカウンターの椅子、上がるのに精一杯だったじゃねぇか」
美堂蛮が面倒くさそうに煙草に火を点ける音がした――そうそう!で、琴音ちゃんがねッ……!!………!!
――上がるのに精一杯だった――カウンターのこの椅子。
あぁ、そうだ――あの頃の俺らの周りはまだ全てが巨大で―――隣に座る父さんも本当に大きく見えたんだっけ……――
二人が双子の息子と娘を連れてHONKY
TONKを訪れたのは、本当に久し振りのことだった。
冬の参観日に懇談会――長引いた慣れぬ催しに、父親の方が少し一服したくなったようだ。
丁度よく集まっていたこの店の常連客達は、小さなお人形のような子供達の訪問を手放しに喜んだ――
あっという間に大きなお姉さんと元気なお兄さん達に囲まれ、もみくちゃにされるようにランドセルとコートを剥ぎ取られ、
可愛い可愛いと撫で回され――「嫌ァ!!」――先に我慢できなくなったのは琴音の方だった――
ワインレッドに紺のリボンがついたワンピースを着た彼女は長く伸びてくる大人の手から逃れるように飛び出すと、
コート掛けにかかっていた父親のコートに顔を隠してしまった。
「…………父さん!」
士音は大人達の手を振り払いながら真っ直ぐに父親の足元に駆け寄った――
テーブル席が埋まっていることを確認した父親は、
母親をカウンター席に導いてやっているところだった。
「士音、一人で座れるか?」
子供には少し高すぎるカウンター・チェアを指差しながらの父の声に息子は黙って頷いて、
クライミングをするように器用に座席まで辿り着く――すると大きな掌が上から下りてきて――頭を撫でてくれたくれたことが妙に嬉しかったこと――それは今でもよく覚えている……――
「士度さ〜ん!琴音ちゃん、隠れちゃいましたぁ……」
レナの残念そうな声に、「そのうち出てくるさ」――と士度は微かに苦笑しただけだった――「士音、落ちないでね……?」
父の隣から心配そうに声を掛けてきた母親に、「大丈夫だよ」――
と小さな士音は返事をし、妹が隠れているコート掛けの方にチラリと視線を流した――コートの合わせから琴音もチラチラとこちらを覗いている――
「士音、メニューは一人で読めるかしら?」
「読めるよ、母さん」
いつも通りの自分達の注文をした両親から、「何を頼む?」と聞かれて士音は反射的にメニューを開いた――それでも、当時の士音は小学一年生。
カタカナ、平仮名は読めても――読めても、珈琲の種類とか(マンデリン・ブルーマウンテン・イタリアン・アメリカン・ブレンドetc.)、紅茶の種類とか(アールグレイ・ダージリン・ジャスミン・カモミールetc.)サンドイッチの種類とか(パストラミ・モッツァレラ・タルティーユetc.)――イマイチ違いと意味が解らなかった。ジュースは……冬の最中、やっぱりお腹が冷えそうだったし……。
けれど、「読めるよ」と言ってしまったからには、注文くらい一人でしなきゃ……――そんな妙な使命感に駆られながら、士音は急いでメニューの上の解る言葉を探した。
父さんは黒眼鏡のお店のおじさんと仕事の話を始めた――母さんは胸が大きなお姉さんとなんだろう、お化粧品の話?をしているのかな……――琴音はジッとこっちを見ている――椅子だって一人で登れたし、注文だって一人でできるって、たまにはお兄さんらしいところ見せなきゃ……――
すると士音の目に、メニューから三つのカタカナが不意に浮かび上がってきた――
これなら、分かる、知っている……!
「……“ココア”……を、くだ、さい……」
「「「「―――!!」」」」
「凄い凄い士音クン!ちゃんと一人で注文できるんだね〜!!」「メニューもちゃんと読めるんだぁ!」
「えぇ〜!!やっぱり子供って可愛いなぁ……!僕も欲しくなっちゃうよ……!!」「……まず相手をみつけなさい……」
アルバイトのお姉さん達の大仰な褒め言葉に士音と両親が目を白黒させているなか、
金髪のお兄さんからの吃驚発言に褐色のお姉さんが溜息半分に突っ込んでいた――と、そのとき……
「パパ……」
琴音がやっと士度のコートから出てきて、おずおずと父親を見上げてきた。
「〜〜可愛えなぁ!!ワイも“パパv”って呼ばれてみたいわ!!」
「笑師が言うとなんか違う“パパ”に聞こえるよ……」
笑師はさっきから琴音の仕草一つ一つに鼻の下を伸ばしっぱなし、亜紋はそんな相方の様子が楽しくて仕方がないらしい。
「琴音、ほら……」
娘を椅子に座らせようと立ち上がり片手を差し伸べた父親に、琴音はフルフルと頭を振った。
「こ、琴音も一人でできるもん……!」
あらあらv琴音ちゃんはちょっと勝気なのかしら?――ヘヴンは士度ともマドカともあまり似ていない幼子の側面に面白そうに目を丸くした――マドカも少し困ったように微笑んでいる。
「そうか、じゃあ頑張ってみろ……」
そう静かに言いながら士度は手を引っ込めると自分の席に戻り、マスターやマドカや仲介屋と何やら子供達には分からない会話をし始めた――
「…………」
琴音は刹那小さく眼を見開いたが、やがて黙って背の高い椅子に手を伸ばし、足をかけ……――しかし“高さ”に無意識の恐怖があるのか握力の違いか――何度やっても彼女は椅子の足の真ん中から上に上がることができない。隣の席からハラハラしながら見守っていた士音も手伝ってあげたかったが、椅子に座っている体制からはどうやっても琴音の体には手が届かないし……。
助け舟を出そうと立ち上がりかけた笑師を、亜紋が穏やかな表情で片手で制した――銀次も本当は手を伸ばして小さな女の子を助けてあげたかったのだが、蛮のサングラスの奥の眼差しは“余計なことをするな”と牽制している。
「……………」
椅子の座に手をかけながら、琴音はチラリと父親を見上げた――彼は母親に優しい眼差しを向けていて、母は彼の腕に手をあて幸せそうに微笑んでいる――なんだかとっても二人の世界。
「……………」
――琴音はもう一度力一杯ジャンプしてみたが――どうして?士音ちゃんはすぐに椅子に座ることができたのに……――椅子がどんどんどんどん高くなるような気がして、琴音の気持は焦るばかり。
「……………」
琴音はもう一度、チラリと父親を見上げた――こんどは胸が大きなお姉さんと話している……――次は心配そうな顔をしている金髪のお兄さん……そしてまたママと……こんどはお店のおじさんと……。
「………パパ………」
琴音は小さく掠れた声で呟いた――士音が気がついたように父親の方を振り向くと、彼は珈琲カップをソーサーの上に戻したところだった。
「………パパ…ァ……!!」
泣き出すのを懸命に我慢している細く精一杯の声がカウンター周辺に木霊し、琴音は何か恐いものから逃れるように父親の方へ駆けていくと、彼のジャケットに懸命に手を伸ばした――すると彼女の小さな体はフワリと宙に浮き――気がつけば、目の前にはミルクが入ったマグ・カップ。
琴音が顔を上げると、優しい顔をした父の姿がそこにはあった――「パパ……」彼女が確かめるように呟くと、母親が差し出したハンカチが、琴音の大きな瞳から零れかけていた涙を優しく拭ってくれた。
「“できない”ときは“できない”って、言っていいのよ、琴音……?」
母親の優しい声に、琴音は恥ずかしそうに俯き、小さく瞬きをする。
「そうすれば、父様も母様も、琴音のことを助けてあげられるわ……」
父親の大きな手を握りながら、琴音は深く頷いた――士音はいつの間にか目の前に出されていたココアに視線を落とした。
そうか……父さんはちゃんと……――
ちゃんと、琴音のことを、見てたんだ……――
広く、大きな背中で――琴音が頑張っているのを、あの時ずっと、見てたんだ……――
「……今はちゃんとこの椅子にだって一人で座れるもん!」
「図体がでかくなったお陰だろ?甘えっこの性格はまだ治ってねぇんだろーよ、あの後確かお前は……」
琴音と美堂蛮が騒々しく睨み合っている――「……士音君、ココアのお代わりいるかい?」
サービスだよ……――昔と同じように笑うマスターに、“お願いします……”と士音は空になったカップを差し出した。
「パパ……抱っこ!」
コートを着せてもらったあと、琴音は父親に向かって精一杯両手を伸ばし、抱っこをねだった――士度が眼を細めながら彼女を抱き上げると、琴音の愛らしい喜びの声が喫茶店を満たした。
士音は高く父親の胸元まで上がった妹を刹那、羨ましそうに見上げたが、コートを着ることに専念することで――何でもない振りをした。
だって、きっと二人を抱えることになったら――重いし、両手が塞がったら歩きにくいし……双子だけど、自分はお兄さんなんだし、男の子だから、我慢。
「士音、帰りましょ……?」
「うん……」
母が差し出してきた右手を、士音はそっと握り返した。
――それに……父さんがこの手を握ってあげられないときは――俺が母さんを守らなきゃ……。
父の仕事仲間である褐色の肌の女性が、自分のことをジッと見つめていることにその時士音は気がついた――“いい子ね……”
“お母さんのこと、守ってあげなさい……”――普段の少し鋭い視線とは違う、穏やかな眼差しに士音はほんの少し頬を染めた――
喫茶店の常連客に大仰に見送られながら、やがて親子はその店を後にした――途中、琴音は疲れて父の腕の中で眠ってしまったようだ――
士度とマドカが交わす優しい夕暮れのような会話に耳を傾けながら、士音は黙って盲導犬と母に歩調を合わせた。
屋敷につくと、琴音は真っ先に寝室に運ばれて――夕ご飯前の一寝入り。
「……士音」
「何、父さ―――!!?」
コートを脱ぎ終えたところで、不意にその身体を父親に高く高く持ち上げられた士音は、父によく似た細い眼を精一杯丸くした。
「――さて、どこへ行こうか?士音」
フワリと宙に浮く感触と、頼もしい声、温かい父親の匂いが士音を一杯に満たし――士音は父親の首に抱きつくと少し恥ずかしそうに囁いた。
「どこでもいいよ……」
いつもよりずっとずっと高い視点から見下ろす母の姿も、嬉しそうにゆらゆらと揺れている――士度が士音をあやすように背中を叩いているからだ。
「ちょっとね、こうして貰いたかっただけだから……」
秘密を打ち明けるように、士音は小声で父に囁いた――彼は優しく眼を細めながら頷くと、
「庭でも散歩するか……きっと夕陽のいい香りがする……」
そう呟き、妻とも笑顔を交わしながら庭へと足を向けた。
やっぱり、ちゃんと――
(自分のことも、見てくれてたんだ……――)
父の広い背中は、小さな腕では包みきれないほどで、とても暖かくて、それがとても嬉しくて――
眼を細めた息子の気配に、自然マドカも微笑みを湛えた。
そう、ちゃんと、“見ている”わ――父様も、母様も、あなたのことを……――
大きな腕に包まれながら、ゆらりゆらり太陽と緑の中を散歩しているうちに、士音もいつしか夢の中へ――
重たくなったな……――
息子を腕に抱きながら感慨深げに呟く士度に、
次は私の番かしら……?――
マドカは甘えるように囁いた――問いかけるように片眉を上げた彼の珍しくも愛嬌のある仕草に、マドカはクスクスと笑いながら、彼の腕にそっと寄り添い、士音の寝息に優しく耳を澄ませた――
「たぶん、暫く……ココアだと思います……」
「……どうして?」
GBと琴音のいたちごっこと、亜紋と笑師のネタ合わせと、喫茶店の従業員とへヴンのコントめいた会話の喧騒の中で、誰に言うでもなくポツリと呟いた士音に、卑弥呼が不思議そうに問いかけた。
「きっと………」
聞き慣れた足音が二つ、聴こえてきた――そうだ、“僕ら”はすっかり大きくなってしまったけれど……
そして、包まれている温もりも、想いの深さも、変わらずに、とても心地が良い――それでも……
「忘れたくない、味だから」
大きく、逞しい存在に抱きあげられ、足が地から離れ宙に浮く――あの瞬間を。
Fin.


![]()