



「…………………」
十月末日――夜の音羽邸が橙南瓜とその顔から灯されている蝋燭の燈で柔らかく幻想的な空間に変わるのは毎年の恒例で、その光景にようやく慣れてきた自分に士度は内心苦笑した。
いつもならこの日特別のカボチャ尽くしの夕食が始まる頃合に、士度は身体に多少の疲労感を抱えながらようやく音羽邸の門をくぐっていた――出掛けに、今日は仕事で少し遅くなる旨を伝えたとき、それでもマドカは笑顔で送り出してくれたのだが――その貌の裏にやはりどこか寂しそうな影が見えたような気がしたのは、きっと気のせいではなかっただろう。
たまには、こっちから今日のクッキーの出来栄えでも訊いてみるか……――
やはりこちらも毎年恒例になっている、食後に出されるカボチャ色の焼き菓子とマドカの笑顔を思い出していた士度が音羽邸の玄関に一歩足を踏み入れ、彼に気付いた執事が迎えの言葉を口にしようとしていたまさにそのとき――士度のジャケットの携帯が急を告げるように無音の着信を伝えたので、士度は嫌忌の感を隠さぬまま渋々と電話に出た――すると彼が何か言葉を発する前に、けたたましい女の声が士度の耳を劈いた。
「士度クン!?今マドカちゃんのおうちの玄関でしょ!?今すぐ回れ右をして急いでホンキートンクの裏口まで来てちょうだい!!緊急のお仕事なの!!早く!!」
「〜〜〜!!?急ってなん――」
「――時間がないから急いで!!あ、お庭からコウモリを二匹連れてきてちょうだいね!!理由はあとで話すからっっ!!」
まるで唾が飛んできそうな勢いで電話の向こうの女は捲し立てるだけ捲し立てると、士度に二の句を告げる間を与えないまま一方的に通話を切った。最初の一声で一瞬仲介屋かと思ったのだが、彼女より少し低いがよく通るその声の持ち主はあの蛇野郎の育ての親で師匠とやらのマリーアとかいう魔女だった。
今まで数度、共に仕事をしたことがある間柄の、いつもはどこか飄々とした風さえ漂わせている彼女からの突風のような電話に面喰いながらも、彼女にしては珍しい切羽詰まった声に士度は只ならぬものを感じ――携帯を懐にしまい舌打ち一つで意に沿わぬ回れ右をして、入ったばかりの玄関から飛び出した。執事が珍しく驚いた顔をしているのが一瞬士度の視界の端に入った――耳にキンキン響いたあの声は、きっと受話口の外にも漏れていたのだろう……。
多少のばつの悪さを感じながら、士度は門を出る直前に庭の前で短く、そして常人には聴こえないほど甲高い獣笛を吹いた――すると胴体は掌大の大きさで、ウサギのように長い耳が特徴的な二匹のコウモリが、ハロウィンの燈に照らされた夜闇パタパタと飛んできて――どこか嬉しそうにそれぞれ士度の肩に舞い降りてきた。
<ヨンダ?シド?>
<オサンポ?シド?>
「――仕事だ……お前らにも手伝って欲しいんだとよ。走るからしっかり掴まってろよ!」
両肩から覗き込んできた好奇心旺盛そうな円らな瞳にそう応えると、士度は人通りが少ない裏道を選びながら、灯色に輝く街を駆けた。帰りに通って来た表通りは、案の定菓子をねだる化けた子供で一杯だったから。それに裏通りなら――ときどきこうやって、塀を飛び越えて近道をするのも容易かったりする。
西洋祭の夜を走る士度の肩から降り落ちまいと、二匹のコウモリは彼のスピードに眼をギュッと瞑りながらも、小さくも鋭い鉤爪をしっかりとジャケットに引っかけている。その愛らしい仕草に士度が刹那眼を細めたそのとき、不意に嫌な予感が彼の脳裏を掠めた――電話をかけてきたマリーアは“魔女”だ。仕事にコウモリ?急いで?何のために…?まさか怪しい薬を作る為に、コイツらを煮立った鍋のなかに突っ込むつもりじゃ……。
「……………………」
<シド?>
<ドウシタノ?ツカレタノ?>
走りながらもその表情が急に固くなった士度を二匹のコウモリは心配そうに覗き込んでくる。
「……いや、なんでもねぇよ――大丈夫だ……」
言いながら士度は心内で今日何度目かの舌打ちをした――もしそうだとしたら、あの魔女……!!――とりあえず鍋やナイフの類が出てきたら、近くの窓を蹴破ってでもコイツらを空に逃がして……――
―――と、そんなことを考えながら新宿の裏道の灰色のまた一つ飛び越えると、目の前の角から件の魔女が飛び出してきた――ったく、こいつの眼は水晶ででもできているのか……――
「こっちよ、士度クン!!」「――ッ!!」
士度の腕を引いたマリーアの力は思いのほか強く――士度が速度を緩める前にその勢いのままどこぞの路地裏に引き込まれ、やはりそのままどこぞの家の扉の奥に放り込まれ――「はい、コレ!!着てっっ!!」「――!!?」「急いで!!」――
薄暗い部屋で有無を言わさず士度の手に押し付けられたのは、クリーニングされた燕尾服――さらには、
「〜〜〜士度君ごめん!!手伝うから早く!!」「〜〜〜〜!!?」
紙袋を片手にどこかから現れたのは、
「いったい何んなんだ――!?」「シャツ着た!?ちょっと頭下げて!!」「〜〜〜!!!!?」
士度が返事をする前に、波児は彼の髪に整髪料をたっぷりベッタリと注ぎ――絶句している彼の頭に急いで櫛を入れると、あっと云う間に凛々しいオールバックに仕上げてしまった。士度についてきた二匹のコウモリたちは、籐の対立ての上に避難しポカンとした口を開けながら、騒がしい人間たちの有様を目をまん丸くして見つめている。
「はい、髪は出来上がり!!ズボン履いたら仕上げにこのネクタイつけて出てきてくれ!!」
鏡はそこにあるから!!――そう言いながら波児は士度の手に赤い勲章を下げたネクタイを押しつけて、慌ただしく対立ての外へと出て行ってしまった。
「………………」
こちらもいつになく忙しい様子の喫茶店のマスターを、士度はズボンのベルトを締めながら唖然と見送ると、指に引っかけるようにして残された暗赤蝋色の勲章付き洋風タイを目の前にぶら下げ、鏡の前で一人怪訝そうな顔をした。
「………………」
それでもとりあえずタイを身につけ、ベストを着て靴を履き替え、燕の尾を持った漆黒のジャケットに渋々と袖を通しながら対立ての外へ出てみると、
「仕上げはこれよ!!」 「―――!?」
バサリと音を立てながら一瞬士度の眼の前で深紅の裏地が翻り――マリーアは凛とした声と共に手早く漆黒の襟立マントを彼に羽織らせた。
「あ、違ったわ――仕上げはこっち♪」 「………?」
首元に降りてきたマントの留め金を訳が分らぬまま留めていた士度の耳に続いて入ったのは、マリーアの一転して機嫌良さげな声と――目に飛び込んできたのは、彼女の掌に鎮座している……牙?
「………おい。」 「ここと、ここにね、はめるだけでいいのよ?」
マリーアはその着牙を士度に渡し微笑みながら、笑顔の下の自らの犬歯を人差し指で軽やかに指し示す。
「……………」 「は・や・く♪」
ここでようやく――彼女の企みの四分の三ほどに気がついた士度は本当に呆れた表情をみせたのだが、マリーアの半ば脅迫めいた無言の笑顔に溜息一つ―――演技をしてまで士度を引き入れようとしたなんらかの計画に、仕方なくだが黙として手を貸してやることにする。
「さすが士度クン!!話が早いわぁ♪どこぞの馬鹿弟子とは大違いね…!!」
あ、コウモリちゃん達は、そんなところに張り付いていないで、ちゃんと士度クンの周りを飛びなさい…!!――そんな台詞と共に士度が着たマントにぶら下がったばかりの二匹のコウモリを引っぺがし空に放ったマリーアの背後の扉からは、「仕度できたかい?コッチコッチ!!」――ごめんよ、後で説明するからさ……――そんなことを言いながら再び波児が顔を出し、士度の手をとった。二匹のコウモリを引き連れた士度は、急かされるままにやはり薄暗い廊下を僅かに歩いた――そういえば黒眼鏡の彼も、今日は見慣れない派手な洋風の茶会服を着てる……――
やがてマスターは向こう側に喧噪が聞こえる扉を開きながらお客向けの声を出した――
「お待たせ致しました〜〜ドラキュラ伯爵です!!」

「マスター、ブレンド……」
しかしいつもの喫茶店の空間を彩るハロウィンの派手な飾りと、いつにない子供たちの賑やかな声の中で間髪いれずにカウンターにスッ……と出てきたのは、磨きあげられたワイングラスに入った真っ赤なトマトジュース。
「……………」 「ゴメン、まずはコッチでサービスしてやってよ……」
ね?――そう申し訳なさそうに言いながら、マスターがクイッと軽く顎で指した方には、オレンジカボチャや犬やら猫やら小人やらに仮装した幼稚園から小学生低学年くらいの数人の子供たちが集団になって、士度のことを遠巻きだがジッと見つめている――
「………………」
連れてきた二匹のコウモリがパタパタと士度の周りで空中浮遊を続ける中、士度は子供たちをチラリと視界に納めると――吐息が漏れる前に目の前のトマトジュースを飲みほした。子供たちは一斉に息を呑み――「……!!血を飲んだ…!!」「ホンモノだよ〜ママ!!」「私たちも食べられちゃうよぉ……!!」――そんな恐怖の声を上げて騒ぎながら、親たちの元へと駆けて行った――士度の隣のスツールでは真っ赤な頭巾を被ったマドカがクスクスと笑っている――赤い頭巾とスカートの丈が短い南欧の民族衣装にハイソックス――森少女風の衣装を身につけた彼女は、なんでも狼喰われる少女(最後には助かるらしいが)の仮装だそうだ。彼女の天敵である狼の格好をして愉しんでいるのは、士度と同じく元四天王の柾なのだが――
「今宵は七匹分の愛が詰まっている
――ときたもんだ。マスター曰く、町内会の担当を引き当ててしまった結果、町内会のハロウィンパーティーをこの喫茶店で行うことになり――子供たちリクエストのモンスターズを用意するのを嬉々として手伝ったのがマリーアというわけだ。
柾とヘヴンは面白半分で『狼と七匹の子ヤギ』役を引き受けた――『赤頭巾』を選ばなかったは、単に毛皮ビキニ風の子ヤギコスチュームの方が赤頭巾のよりもセクシーだったという、いかにもな理由からだった。
ドラキュラ伯爵にショックを受けた子供たちを笑顔であやしている銀次は、紫と灰色の縞模様の、デップリとした猫の着ぐるみを着ている――そんな銀次にブツクサと文句を言っている蛮は小洒落た燕尾服に大きな懐中時計を下げ――頭にはそのしかめっ面には似つかわしくない白い兎の耳をつけているのがなんとも間が抜けている。楽しそうに談笑する町内の親子に笑顔でケーキや珈琲を配っている夏実は白いエプロンに水色の少女服、彼女を手伝うレナはハートの模様が数多についた派手な貴族的なローブと衣装、平謝りをしながら士度にやっとブレンド珈琲を提供したマスターの傍らには通常の二倍ほどの大きさのシルクハット――彼の役はお茶会主催する帽子屋で、ここらの仮装はアリスとかいうひとつの物語から引っ張ってきたそうだ。「容姿と笑わないところがピッタリ♪」と士度を見事にこの茶会に巻き込んだマリーアは――黒いとんがり帽子に黒マントに、片手には木の杖――そのまんまじゃねぇかと彼は心の中で呟いた。
「凄く好評ですね、士度さんのドラキュラ伯爵……!!」
牙まで生えているんですって?――そういいながらマドカは無邪気にも士度の口元に手をあててくる――今宵は常連客ばかりではないというのに。
「……手ぇ切るといけねぇから、よせよ……」
ほんの少しの気恥ずかしさも手伝って、士度はそう言いながら彼の口元に触れているマドカの手をそっと掴むと、彼女が下げていた籐の籠を話を逸らすようにトントン……と叩いた。
「……あ、コウモリさんにですね?確かドライフルーツが……」
自分の耳元で何かをねだるようにホバリングをし始めたコウモリの様子からも彼の意図を察したマドカは籠を探り、林檎のドライフルーツを取り出すとティ―ソーサの上にのせてコウモリたちに勧めてやった――彼らもパタパタとカウンターに降りてきて、ようやく一休み。
すると先程まで銀次達とジャレていた5〜6歳位の子供たちがマドカのところへおそるおそる駆けてきて……
「……赤頭巾ちゃん、一緒にいたら食べられちゃうよ?」「血、吸われちゃうよ?」「ドラキュラだよ!!恐いんだよ!!」
そう言いながらマドカの頭巾やスカートを引っ張った。何を言っているんだと自分の格好の意味に疎い士度が子供たちに視線を向けると、彼らはビクリと顔を引き攣らせながらマドカの方へと回り込み、士度から距離を置く――士度は仕方なくその視線をカウンターの上で寛いでいるコウモリたちの方へと移した――どうやら赤頭巾は人気者で、自分が化けているナントカ伯爵とやらは悪役らしい。
「このドラキュラさんはいいドラキュラさんだから、大丈夫よ?」
そう言いながらマドカは籐の籠からお菓子の包みを出すと、子供たち一人一人に手渡した。
「でも……ドラキュラは可愛い女の子を食べちゃうからあの赤頭巾ちゃんも危ないわってママが言ってたよ?」
どこの馬鹿親だ……――と士度は思ったが、マドカはニコニコ笑顔を絶やさない。
「私、このドラキュラさんになら食べられても……」 「〜〜!!?馬ッ鹿!!お前……!!」
大意を含まずに漏れたマドカからの危うい台詞に、士度がバサリとマントを翻し彼女の口元を覆うと、自然赤頭巾はドラキュラのマントにスッポリと覆われてしまった。赤頭巾はドラキュラの腕の中でキョトンとしている。
「〜〜〜!!赤頭巾ちゃんが……!!」「ママ〜〜!!食べられちゃったよぉ!!赤頭巾ちゃんがぁ!!」「ドラキュラが食べちゃったぁ!!」
子供たちは伯爵の突然のリアクションに吃驚して喫茶店の中を右往左往、そんな子供たちの様子を保護者達は微笑ましく見つめ、狼と時計兎は口元をニヤニヤさせながらこちらを見ている。
「はい、ドラキュラ伯爵〜〜」 「赤頭巾ちゃんお持ち帰り〜〜♪」
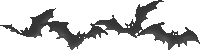
あの後士度にちょっかいをかけてきた蛮と柾にコウモリが噛みついて――飛び上がる兎と狼に場が盛り上がるなか、ドラキュラと赤頭巾はパーティーを抜け出してきた。衣装そのままで出てきても、日が日だけに新宿の街の中はそんな輩ばかり、ドラキュラも赤頭巾も大して目立たなかったはずだ――マドカのスカートが短すぎるのか、すれ違った男たちが時々こっちを振り向いていたが、番犬付きでは何もできまい。
音羽邸に戻ると出迎えた執事が二人の姿を見て一瞬驚いた顔をした――
「……余興だ。」
そう呟いた士度に返ってきたのは「よくお似合いでございます」――というどこか誇らしげなニュアンスが籠った褒め言葉――自分はこの伯爵に似ていて、マリーアの選択は間違っていなかったのかと士度は今更ながらにぼんやりと思った。
着替えてくる――二階に上がるなりそう言った士度に、マドカは部屋までついてきた。
そして部屋の扉を閉めた彼の前で、彼女はフードの頭巾を被ると一度クルリとターンしてみせた――あぁ、そういえば……――
「あぁ、良く似合っている……が……」
月灯りだけの部屋の中でドラキュラの言葉に嬉しそうに顔を輝かせた赤頭巾を、彼はフワリと持ち上げ姫抱えにすると――その反動で頭巾が脱げた彼女の漆黒の髪に貌を埋めながら、そのスカートをからかうように引っ張った。
「――コレが短すぎるな……」
誰かに喰われちまうぞ……?――ドラキュラからのそんな低い声に魅かれるように、赤頭巾は微笑みながら彼に唇を近づける。
「このドラキュラさんになら―――」 「――だからその台詞は危ねぇって……」
彼女の唇の柔らかな感触を感じながら、早く牙を外しちまわないと――とドラキュラは思った。
赤頭巾は甘えるように彼の逞しい首筋に両腕を絡め貌を寄せた。
彼が顔を傾けたせいか、彼の足元で長いマントの端がユラリと翻る――
窓から見える裏庭には、例年と変わらず橙色の南瓜と淡い灯が幻想的に並んでいたが、
今年の二人は暗がりの一室で密やかに――異国と異形の衣装に身を包み、
菓子要らずの甘い夜に酔いしれた。
〜Fin〜
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆*:..HAPPY HALLOWEEN NIGHT☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆*:..
★ブラウザを閉じて御戻りください★