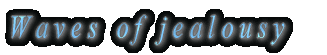
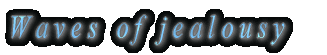
出掛けるまで、ほんの少し・・・時間があったから。
彼もがまだ・・・降りてきていなかったから。
これからきっと交流も多くなるだろうから、今のうちから少しずつ・・・そんな風に思って。
マドカが音楽院の仕事に出掛ける矢先、士度を会合に迎える為、魔里人の女性幹部が音羽邸を訪れた。
当の本人は二階で仲介屋・ヘヴンと電話で打ち合わせの真っ最中。
律儀にも玄関で立ったまま主を待とうとする客人を、マドカはティー・ルームに招きいれ・・・束の間の茶話がどこかぎこちなく、静かに始まった――
互いの年齢の話は、当たり前のようにすぐに訪れ――その魔里人の女性は、士度よりも一つ、歳若いという――しかし、彼女はマドカの年齢を聞くと、少し驚いた素振りを見せた。そんな彼女の反応に、マドカも眼を瞬かせると――女性幹部は少しばつが悪そうな顔をしながらも、正直な気持ちをマドカに伝えた――
「いえ・・・士度様が4つも歳のお若い方とお付き合いするのは・・・何だか意外な気がして・・・・」
――同い年位か、年上か・・・・その辺りがお好みかと存じ上げておりましたので・・・・
今度はマドカが眼を瞠る番だった――しかし、マドカが肝心な問い掛けを客人に投げかける前に士度が階下へ降りてきたので、その女性幹部は席を辞す旨をマドカに丁寧に述べると穏やかな華の香を薄らと残してティー・ルームから消えていった。
後に一人取り残されたマドカは――膝の上にティー・カップを載せたまま、暫く呆然とその見えない瞳を虚空に彷徨わせていた。
![]()
あれは彼女なりの牽制だったのだろうか――いや、どこまでも“彼”に従順な人達のこと、自分と彼との間にわざと波風を立てようなどと画策するはずは――おそらく、ない・・・・。仮にそうだとしても・・・・彼女のあの口振りからすると・・・きっと・・・・
(士度さんには・・・・やっぱり昔・・・・お付き合いしていた
仕事の帰り――同僚の車の後部座席で、マドカは昼間のやり取りを思い出しながら、泣き出したい気持ちを懸命に堪えていた。
音楽院での授業は滞りなくこなしたが、やはり今日の自分はどこかしら・・・心の不安が表にも出てしまっていたらしい。
友人たちからは元気がないと心配され、気分転換にと誘ってくれた夕食の席でも、何だか心ここにあらずといった雰囲気で。
そんな彼女の様子に、モーツァルトも心配そうに鼻を鳴らす――「もうすぐ、着くからね・・・」――そんな同僚の声と共に、車がゆっくりとスピードを落とす気配がし、マドカは俯きがちだった頤をゆっくりと上げた。
「道が狭いから・・・まずはワンちゃんを先に降ろしたほうがいいよ?」
夕食会に出た女性メンバーを自宅まで送り届けるのは、男性陣の役目――そんなことが当たり前になっている音楽院の仲間内で今夜マドカを送ってくれたのは、よく競演するオーケストラの首席バイオリニスト――彼は合計4名の女性陣を順番に、実に紳士的に自宅まで運んだ――しかし、自宅が一番近かったのは本当はマドカだったのだが、入る道を一本間違えたとかで結局は彼女が一番最後になるはめに。
「・・・ありがとうございます――?」
カチャリと開いた後部ドアはしかし、モーツァルトが降りるや否や再び静かに閉ざされた――そして代わりに運転手役だった同僚がマドカの隣に腰を降ろす。キャン・・・!――車の外でモーツァルトが少し慌てた風にマドカを呼んだ――同僚の不可解な行動に、マドカは僅かに眉を寄せた。
「あの・・・・」
「音羽さん・・・君、今日は何だかずっと・・・・哀しげな表情をしているよ?何か困ったことでもあるの?僕でよければ相談に・・・・」
そう言いながら唐突にマドカの手を握ってきた彼に対して、彼女の心は大きく警笛を鳴らした――「あ、あの・・・大丈夫ですから・・・!!」――マドカは少し性急に同僚の手を振り解くと、懸命に後ずさりをしながら、逆サイドのドアの取っ手に手を伸ばした――しかしロックが掛かっているのか、マドカの手の動きに合わせてカチャカチャと空しい音が響くばかり。
――あぁ、そっちは車道に近いから・・・ね、危ないんだよ。
男はその白い貌に柔和な微笑を称えながら軽やかにそう言うと、マドカの肩に両手を置き、自分の方へ引き寄せる――マドカの心は反射的に竦み上がり、その細い両腕を突っぱねて懸命に同乗者との距離を保とうとするが、そんな彼女の行動を嘲笑うかのように彼の指はマドカのブラウスのリボンへと掛かった。
「――!?ヤッ・・・・ッ!!」
スルリとリボンが解かれるのと同時に、凍るような恐怖がマドカを襲う―― しかし、そんなマドカの様子を気に留める風もなく、男はマドカの襟元を寛げながらマイペースにお喋りを続けた。
「ねぇ・・・知ってる・・・?女性の悩み事を解消する音楽は何もモーツァルトだけじゃなく・・・・たとえばバッハのアリアを反芻しながら気持ちの良いことをすると・・・・――!?」
男の唇が震えるマドカの首筋を捕らえようとしたその刹那――ガッ・・・!と派手な音を立てながら後部ドアが開いたかと思うと、男は襟首を掴まれそのまま外へ放り出された――アスファルトにどこか打ち付けたのか、不様な悲鳴が男から上がった――そして眼に一杯の涙を溜めながら震えていたマドカも、状況を把握できぬまま突如として現れた第三者に躰ごと掬い上げられ―― 一瞬、抵抗を試みたマドカであったが、小さく呼ばれた名前に、その声に・・・・そして広がる、彼の人の匂いに――彼女の瞳は今度は安堵の涙を誘われ、マドカは形振り構わず彼の首筋にしがみついた。
![]()
「・・・・ッたく、同僚だからってよく知りもしねぇ男の車に乗るなんて・・・・」
――ガキじゃあるめぇし、何考えてんだ?お前は・・・・
珍しく諌めるような口調の士度の言葉に、マドカはひたすら小さくなるしかなかった――彼の言うことはもっともだ――急な夕食会だったので、運転手をはじめ、使用人たちには先に仕事を切り上げてもいいと、帰りはタクシーを使うからと電話をした結果がこれだ・・・・同じく仕事の帰りが遅くなった士度がたまたま通り掛からなければ、どうなっていたことか。
――・・・途中まで、お友達も一緒に乗っていたから・・・・
そんなマドカの小さな言い訳も、士度の飽きれたような溜息に掻き消され、マドカは再び泣き出したくなるような気持ちに駆られた。
「・・・世の中の連中が皆、良い奴らってわけじゃねぇんだ・・・お前、ときどき無防備過ぎるんだよ・・・・」
今日は疲れていて機嫌が悪いのだろうか――屋敷に着いてマドカを腕から降ろして以降、士度は彼女に触れてこようとはせず、ただ・・・言葉を並べるだけ――いつものようにその大きな手で頬を撫でてくれたり、広い胸の内に守るように抱きしめてくれたら、この気持ちはどんなにも楽だろう・・・・――萎れるばかりのマドカの心を、士度の次なる言葉がさらなる傷を作った――
「お前も、もうそろそろ・・・どんな
「・・・見えないもの・・・・」
マドカの抵抗するような暗い声に、士度は一瞬戸惑うような顔をしたが、彼女の言葉を幼げな反抗ととったのか、すぐに気をとりなおしたようだ。
「・・・・そう言う意味で言ったんじゃねぇんだ。揚げ足をとるなよ・・・・けど、もし、お前の気に障ったんなら謝――マドカ・・・?」
しかし、マドカは士度の言葉を遮るように首を打ち振ると、想いの丈を吐き出すかのように、突然、声を高めた。
「私・・・見えないし・・・!それに・・・“士度さんと違って”、他の人とお付き合いなんてしたことないから・・・分からないもの!」
――どんな男の人が何を考えているかなんて・・・分からないもの・・・・!
叫び声に近い声がマドカの口から漏れたかと思うと、彼女はクルリと身を翻し、士度の部屋から出て行こうとドアノブに手を伸ばした――しかし、その細い腕は士度の逞しい手によって遮られ、マドカはあっという間に壁際に追い詰められてしまう。
「・・・ッ!!は、離してください・・・・!!」
逃れようと抵抗するマドカの両手を、士度は片手で難なく拘束することでその動きを封じた――そして彼女の心を見透かすような眼差しでマドカを見下ろしてくる――そんな彼からの視線から、マドカは恥らうように顔を背けた。
「・・・そこで、どうして・・・“俺の”話が出てくるんだ?」
――今は関係ねぇだろ?そんな話…
しかし士度の口から出た、突き放すような言葉に――マドカは驚いたように顔を上げると――まるで心の澱を一気に吐き出すかのように声を上げる。
「関係ないって……た、確かにそうかもしれませんけれど…!でもやっぱり…私は…その…士度さんと比べると経験がほとんど無いから…!」
――男の人が考えていることなんて…分からないことだらけで……
士度はマドカの唐突な言葉に、再び片眉を上げた――
そんな士度に拘束されたまま、マドカは薄い唇を噛んだ――違う…誰が何を考えているかなんて、関係ない…今、自分の心の中で吹き荒れるのは、途方も無い嫉妬心だ――しかも相手は彼の過去――
そして今日ほど――いつも心の片隅で燻っていた疑問と不安がはっきりと形を成してマドカに襲い掛かってきたことはなかった――
彼は…――自分以外の女性を知っている――
そう思う度に心は千々に乱れ、悲しみの檻の中を彷徨うというのに――彼の温もりは今は自分のものだと…確かめたいのに…今、自分に与えられているのは、冷たい視線と言葉――そして士度は厭きれたような声を出す。
「――“俺と違って”だの、“俺と比べて”だの…さっきからお前…何言ってんだよ?どこからそんな話になるんだ…?」
士度の問いかけにマドカは頭を振りながらも、震える声でさらに言葉を吐き出した――
「だって…だって…!!わ、私は…士度さんが今まで
小さな舌打ちが聞こえたかと思うと――マドカの声を遮るように押さえつけられていた手が唐突に解放され、代わりに体位を入れ替えられ――士度はマドカを壁際に立たせたまま、背後から覆いかぶさるようにして彼女の耳元で囁いてきた――
「どこの誰から何を聞いたか知らねぇがな…確かに俺は…お前以外の女を何人か…
――里のしきたりもあったし、何より
「――!!」
悪びれもせず、さも当たり前のように紡がれた士度の冷えた言葉に――マドカの双眸は大きく見開かれ、その痩躯は悲しいまでに硬直してしまった――そして士度の次なる言葉と行動が――マドカを絶望の淵へと追いやっていく。
――マドカ…確かにお前は何も分かっちゃいねぇよ……
士度の手がゆっくりと彼女の腰を撫で上げる――薄いスカートの上から伝わってくるのは、いつもとは違う――優しさから懸け離れた感触。
「い…嫌……」
彼女の本能は――士度が次に何を言うのか全て理解していて――マドカはそんな士度の元から離れようとその細い身体を精一杯動かしたが、士度にとってそのか弱い抵抗は無いに等しく、彼はまるで彼女に更なる怖懼を与えるかのように戒めの手に力を篭めた。
「…男って生き物はな…マドカ……」
自分の下で怯え、その大きな瞳に涙を一杯にため――懇願するように首を打ち振る彼女を、士度はどこか暝い表情で見下ろしながら非情にも言葉を続ける――
「……
「……!!――……ッ!」
漆黒の瞳から流れ落ちた一筋の涙が、彼女の白い貌を犯した――そして悲痛な悲鳴が、仄暗い部屋に小さく木霊した。
「……悪かった」
背後から聞こえて来た士度の静かな――しかし気恥ずかしげな声に、マドカは顔を上げた。
頬の横で感じるのは、彼女の首筋に顔を埋めたままの彼の沈んだ気配。
「・・・・・・どうしちゃったんですか・・・今日は・・・?」
――確かに私も…・・もっと気をつけなきゃって思いましたけれど…
――でもちょっと……痛かったです。
わざと拗ねるような声を出しながら、マドカは士度の腕に頬を預けた。
――すまなかった・・・
マドカの頭を優しく撫でながら、士度はもう一度謝罪の言葉を述べた――しかしマドカはポンッ・・・・と彼の腕を軽く叩きながら、自分の問い掛けへの返答を促す。
刹那、士度は困惑の気配を漂わせたが――やがて観念したかのような溜息を吐くと、心底極まりが悪そうにポツリ・・・と呟いた。
「俺…お前が初めてだからさ・・・・」
マドカは驚きを隠さず眼を瞬かせ、「でも・・・士度さん、さっき・・・・」――と疑問符を顔に張り付かせる。
「嫌、そういう意味じゃなくてだな――その・・・・」
士度は忸怩たる思いを押し込めながら――マドカの耳元に口を寄せて囁く――
――どーしようもねぇくらいに自分から・・・・
思いもよらなかった彼からの突然の告白に眼を白黒させるマドカを他所に、士度は僅かに顔を紅潮させながら言葉を続けた。
「だから・・・さ、お前のことになると、いつもみっともねぇくらいに余裕無くして……考えていることだだ漏れになっちまって・・・・」
――今日だって・・・他の男とあんなに近くにいるお前の姿見て、頭に血ィ上っちまって・・・・それに、今までの他の女とお前は違うってこと・・・マドカは全然分かってねぇって思うと腹が立ってつい・・・
「・・・・つい?」
士度の言葉尻を捕らえて小さく睨みつけてきたマドカに、士度は弱りきったように――悪かった・・・――と、もう一度目を伏せた。
そんな彼の胸に、マドカはそっと頬を寄せる――
「士度・・・さん・・・それって・・・・もしかして・・・“嫉妬した”って、ことですか・・・・?」
めったに聞かない言葉に士度は一瞬硬直したが――間が悪そうに小さく頷いた。
士度の胸元でマドカの唇が安堵の微笑を作った――
「でも、愛がなくても女を抱けるって・・・・・・」
彼女からの意地悪な問いに、士度は不面目な自分を恥じたが――今日の彼女に対して無言は許されない――観念したかのように頭を垂れた。
「・・・・言ったろ、お前は“違う”って」
喜びを押し隠すかのように、マドカは士度のシャツを握り締める。
「違う・・・んですか?」
――どう違うんですか・・・?
おずおずと、しかし懸ける想いをその美しい貌に乗せたまま、マドカは士度の顔を覗きこんできた。
士度は――まだ言うか――と困却の表情をマドカに向けたが・・・・彼女はうっとりと彼の言葉を待っている。
士度はマドカを抱き寄せ――その首筋に唇をあて、音を出さずに呟いた。
「― ― ― ― ―」
満ち足りた幸福感がマドカの心を駆け――麗らかな微笑が士度の心を奪った。
マドカは彼に
「汗・・・かいちゃいましたから・・・」
キスの合間に、マドカは気恥ずかしげに自分のブラウスを引っ張った。
今度は士度のほうから――わざと問いかけるような眼差しが降りてくる。
「・・・・だから今度は・・・ちゃんと・・・触れて、欲しいです・・・・」
頬を真っ赤に染めながら、胸元で愛らしく囁く恋人を、士度は優しく抱き上げた。
そしてもう一度キスを――
その夜、溢れる愛を止められぬまま、二人は互いのぬくもりを分かち合っていた――
互いの心の中で荒れていた大きな波は、いつしか静かな凪となって、二人を穏やかな夜の闇へと誘っていった。
Fin.
難産でしたが・・・ダークサイドの士度さんを久々に書いてみました。
それでも士度さんはマドカ嬢愛・・・ということで☆
三万hit御礼企画第二段、いかがでしたでしょうか?
裏の“妬波-ツナミ-”と合わせてお楽しみいただければ幸いです。