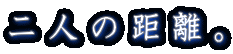暑い……熱い…熱い……………――
ここに入ってからまだ一時間も経っていないのに、何度頭の中で無意味に繰り返しただろう――
咽返るような暑さの中で、卑弥呼は既に立っているのが精一杯だった。
目の前にいるビーストマスターは
「……悪い、脱ぐぞ」
――律儀にもそう断りを入れてから、着ていた皮のベストと黒シャツをこの狭い空間の中で
器用に脱ぎ、それを置く場所すらないのでしかたなく、自分の頭のすぐ上で揺れる段ボール箱と天井の間の、狭い隙間にその衣服を滑り込ませた。
「………………」
鍛え抜かれた彼の素肌が、卑弥呼の目の前に露になる――あぁ男って、こんな時はすぐ裸になれていいわね……――流れ落ちる汗で肌に張りつく通気性が決して良いとは言えないチャイナ服の下の自分の躰を恨めしく思いながら、真っ先に脳裏を過ったのがこれである。そして……
「――――ッ!!」
――ハタと目にした彼の鋼のような肉体に――卑弥呼の身体の熱は自然沸点に達する勢いで上昇した。
なにも彼の素肌を目にするのは初めてではない――何だかんだで怪我や戦闘が多い裏稼業()
、途中手当をしたり、ボロボロになった服を着替えたり――どちらかというとパワーファイト専門の彼が何らかの折にその素肌を晒す度、同じ男でも蛮とは筋肉の付き方が違うものだと感心したりしていたのだが、
如何せん今回は――目の当たりにしている距離が違う。
今、自分と目の前のビーストマスターとの距離は――15センチと、離れていない。
加えて言うと、自分たちは一メートル四方もない、とてつもなく狭い空間の中に向い合せに立っていて、三方は丁度ビーストマスターがスッポリと隠れる高さの、中身がギッシリ詰まって積まれた段ボール箱に囲まれ、卑弥呼の左手、士度の右手側は鉄の壁――
(〜〜〜〜〜どーしてこうなっちゃったのよ……!!)
顔を真っ赤にしながら俯き、心の中であらん限りの声で叫んだ卑弥呼と――相変わらず蒸す暑さに思わず溜息を吐いた士度は――
夏の夜の高速道路をひた走る、大型トラックのコンテナの一番奥に、揺られながら突っ立っていた。
こんなはずでは、全くなかったのだ――少なくとも、60分程前までは。
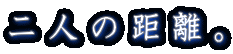
報酬のわりに、その経緯はともかく、あまり難しくはない仕事のはずだった。
複雑且つしち面倒な旧家同士が絡む嫁入り問題の際に、渦中宅の蔵からその家に古く伝わる嫁入り道具が消えた――
それは花嫁の家と代々の交流がある婚約者の家を繋ぐためには必須とされている国宝級の漆塗りの櫛が盗まれたのだった。
花嫁とその婚約者の家々の者が総出でその行方を捜したところ――その素行故、家を継ぐことを許されなかった花嫁の分家筋の伯父にあたる人物が、金欲しさに闇ルートに流してしまったらしい。
その行く先は裏の世界で幅を効かせているとある収集家のところで、物が物だけにそして出所が出所だけに――最新の注意を払ってカモフラージュされながら輸送されるというところまでは、その被害者側が既に突き止めていた。
そして婚礼日が間近に迫った昨夜、仲介屋と共に士度と卑弥呼はその旧家に呼ばれ――亡き母も愛でていた櫛と共に嫁ぎたいとさめざめと泣く花嫁と、彼女の願いをなんとしても叶えてやりたいと頭を下げる婚約者に請われるまま、色恋沙汰話に最近滅法弱い仲介屋に強く押されて二人は仕事を引き受ける破目に。
櫛は今宵運ばれる――しかも大型トラックに数多に乗せられる段ボールの中に紛れて。
その中から櫛の行方を捜す方法は、その櫛と対になっている簪()
を借りた士度が犬に擬態して同じ漆の匂いを追うという、いたってシンプルな方法。
行き先の情報も仲介屋が手に入れた――出発地点から一時間弱のところだ。しかし敵も本家からの追跡を警戒している為今回は馬車()
の足は使えないこともあり、士度と卑弥呼が隙を見てトラックに潜り込み、出発してからコンテナの中でターゲットを確保。トラックの到着と共に出される荷物に便乗しながら、外にいる連中を催眠香で眠らせ脱出――
手際の良い二人にとっては、この段階まではいつも通り黙々と作業をこなせば夕食の頃合には帰ることのできる仕事だったはずなのだが……。
卑弥呼がトラックの運転席に盗聴器を仕掛けた後、トラックの大型コンテナの奥の方に荷物が積み込まれた時を狙って二人で潜入するところまでは上手くいった――
しかし荷物の陰に身を潜める二人に続くように運び込まれてきた段ボールの数は、彼らの予想を遙かに超え、荷物を順に奥へ押し込め整えていく運搬人達に怪しまれないことを士度が考慮しながら手足を踏ん張った結果、なんとか二人はその段ボールの山に潰されずに済んだのだが――
結果一メートル四方もない空間に二人で閉じ込められる羽目に。
櫛の場所は意外と早く確認できた。カモフラージュに埋もれさせるとはいえ、大事なものは奥に、奥にが人の性。
士度の頭上の段ボールから香る漆の匂いを、閉じ込められながらも犬に擬態した士度の鼻はすぐに捉え――手でボール箱を破ることによって、ターゲットはスンナリ確保できた。
「囲まれちゃったけど、後一時間経ったら出れるしチョロイものね……」
そう言いながら卑弥呼は手渡された櫛を機嫌よく振ると、それを和布で丁寧に包んで腰につけているポーチにそっと仕舞った。
そして今度はイヤホンと小さな機械を取り出すと周波数を合わせ、走り出したトラックの運転席の会話に耳を澄ませる――イヤホンの片方をビーストマスターの方に差出し、一緒に聞くかと瞳にで問えば、“必要ない”と手で軽く制され、彼はその細い目をそっと瞑ると何かに意識を集中し始めたようだ。
(あ……なるほど、これがあのドリフ男が言っていた所謂“兎聴擬()
”……)
便利なものね……――卑弥呼はそう素直に感心しながら、盗聴器のイヤホンに耳を澄ませた――運転席と助手席に座っている若い運搬人達の呑気な会話がエンジン音に交じって聴こえてきた。
<あ〜、たかだかちっせぇ段ボール一つ運ぶのに十トンのバンボディ使うって頭おかしいんじゃねぇの?しかも何入ってるかしらねぇ段ボールまで積めるだけ積みやがって……>
<そのちっせぇ段ボールの中身も俺らは知らないけどねぇ……ま、おっかないから知らない方がいいけどさ……>
<………なぁ、ホントにコレ、S山のホテルの駐車場で荷物降ろすだけでいいのか?>
「「―――!!?」」
運転手の声に卑弥呼が目を見開き、士度も眼を瞑ったままではあったがその肩をピクリと動かした――仲介屋が手に入れた情報では、これらの引き渡しはC港だった――流された情報が違う?
S山といったらここから車で約2時間の――
<S山でいいんだよ。最初C港って言ってたけど、段ボールが潮風に吹かれたり水で濡れたりするとヤバいんだってさ……しかも加えて3時間もノンストップで回り道しろって……――どうなってんの?>
「「―――〜〜〜!!!?」」
卑弥呼は思わず顔を上げビーストマスターの方を注視した――相変わらず眼を瞑ったままであったが、思わぬ事態に彼の眉間にも皺が寄っている――卑弥呼は急展開となった仕事内容の新情報を聞き洩らさぬよう、しかし隠しきれない焦燥感を抱えながらもう一度イヤホンの奥から聞こえる声に集中した。
<――ったくよ、尾行されるかもしんねぇから異端ルートで迂回し尽くしてから山道に入れとさ!なんだよ尾行って!!どんなお宝積んでんだかなぁ…俺達は!>
<……ま、口止め料込みで報酬も正規より10倍ってことだし、ホント、俺らは何も知らない方が身の為だよ……。チャッチャッとドライブ済ませて荷物置いて帰ればいいのさ――>
<〜〜!!十トン転がして野郎と二人っきりの夜間ドライブなんて色気が無さすぎだろ!!しかも五時間寄り道もできないって軽く拷問だろ!?……まぁ、これでバイクのローンがチャラになると思えば………>
「「……………………」」
その後延々と続き始めた愚痴話と世間話に卑弥呼はイヤホンを外し、士度は呆れた顔をしながらようやく眼を開けた。
「こんなところに、五時間ですって………!?」
苛立ちを隠さずに呟いた卑弥呼の台詞とシンクロするように、士度は「一寝入りしてればつくさ……」と諦め半分の顔で背後の段ボールに背をつけて腕を組み軽く頭を垂れ再び眼を閉じた――早速長時間待機の姿勢だ。
ここで卑弥呼は初めて自分たちが突っ立っている空間の危うさを意識する――お互いピッタリと背後の段ボールに背をつけてもその距離は30センチも無い距離だ。
高速を抜けた後のトラックが万が一悪路を通り激しく揺れた場合、二人の衝突はきっと避けられない――
(………とは言っても、ビーストマスターだし。)
はたと気づいたように卑弥呼は眼を瞬かせた。思い出すまでもなく、目の前の男は卑弥呼に対してまったく前科のない男だった。
くわえて彼女持ちで実直な彼のこと、異性の相棒に思わず触れる事態に陥っても、赤くなるか青くなるかは知らないが――どこかの誰かさんとは違い下心を持ったりセクハラ紛いのことをしたりすることは、まず、ありえない。
ようするに、安全な男なのだ――女にとって、彼は。
(S山だと……今回は“足”がないし、着く頃には最寄りの終電時間も過ぎる頃だから……その“ホテル”とやらに泊まりになりそうね……)
とりあえず仲介屋に予定変更の連絡を入れておかないと――このトラックの大きさ、この装甲――運転席にまでコンテナにいる自分たちの声はよっぽどの大声でない限り漏れることは無いと卑弥呼は判断し、ウェストポーチから携帯を取り出すと仲介屋のナンバーを探した。
電波はすぐに繋がった――卑弥呼が仲介屋に苦言交じりに今回のミッションの変更と今夜の宿泊先の確保の指示を伝えていると、士度が何かに気がついたようにジーンズのポケットから携帯を取り出し、何やら操作をし始めた――どこかぎこちない、動作で。
(メール……?)
卑弥呼が今後の段取りを仲介屋に改めて確認している数分の間に、ビーストマスターの手の中で携帯が小さく揺れて着信を伝えた――携帯を再び開き、画面に視線を落としたビーストマスターの目が刹那、優しく眇められたような気がした。
そして彼は再び短く操作をし、ほんの少し間を置いたのは送信画面を見つめていたせいだろうか――やがて彼は携帯をポケットにしまうと眼を瞑り、先と同じ体勢で待機の姿勢をとった。
「……………」
通話を終え、パチン……と自分の携帯を閉じた卑弥呼は向かい側にいるビーストマスターと同じようにその背を背後の段ボールに預けると、彼の方をちらりと視線を向けた――寝ているのか、瞑想をしているのか、眼を相変わらず閉じたまま、彼はとても静かな表情をしている。
メールとか、使うんだ……――
機械は苦手だ、嫌いだ、解らない――出自故、それは不思議ではないと思っていたこの今回の相棒も、彼女の為なら俗世のことを覚える努力を多少はしているようだ。
普段決して口数が多くない彼が打つメールの内容はどんなものだろう……――
興味本位にそんなことを思いながら、卑弥呼も生あくびを噛み殺し眼を閉じた――こうやって厚い紙の壁に寄りかかってうたた寝をしていれば、五時間なんてきっとすぐ……――そんなことをこのときはまだ暢気に思っていたのだが……。
「「………………」」
トラックが走りだして40分程経った頃だろうか――二人が立っている空間に徐々に熱が籠りはじめた。
恐らく運転席で使っている空調の余熱と回り続けるトラックのエンジンの熱だろうが――その熱気が肌や衣服に纏わりつき、身体を伝い始めた汗が煩わしくなってきた。
背を預けていた段ボールでさえもやがて熱を身体に直接伝えてくるように感じられ、卑弥呼は茹だる熱に浮かされながらその背を離した――ビーストマスターもこの暑さに嫌気がさしてきたのだろう、彼は卑弥呼に短く断りを入れると、15センチと離れていない彼女の目の前で上半身の衣服を脱いだ。
今までにないほど間近で異性の肌を目の当たりにし、多少涼しくなったと思った背中がまた熱くなるのを卑弥呼は感じた――(〜〜〜〜〜どーしてこうなっちゃったのよ……!!)
叫び出したい思いを封じ込めれば込めるほど、身体の熱は上がり、汗は止まることなく流れ、衣服に張りつき――呼吸するたびに熱波に肺を侵されるような気がするので自然息苦しくなり――目の前にいるはずのビーストマスターも、どこか遠くにいるように感じられ……。
「――……ィズン――レディ・ポイズン!!」
運転席に声が漏れるのを配慮してか、卑弥呼は士度に両の二の腕を掴まれ、耳元でピシャリとその名を呼ばれてようやく我に返った。
「な…な、に……?」
まだどこか朦朧とした表情で卑弥呼は苦しい息の中、ビーストマスターにやっとのことで返事をする。彼の少し困ったような顔が、すぐ目の前にあった――
「――呼吸が乱れているぞ、アンタ。そんなに暑いならまずはこの上着を脱いだ方がいい。」
「〜〜〜!!?な、なんですって〜〜!!?」
掴んでいた卑弥呼の二の腕をポンッ…と軽く叩きながらの士度の台詞に卑弥呼は擦れた声で悲鳴を上げたが、シッ…!!と士度に諭されることで、慌てて次の声を飲み込んだ。お陰様で意識は覚醒すれど、頭に血は昇るは動悸は激しくなるわで彼女はパニック寸前だった。
「ソイツの通気性は良いとは言えないだろ?まずは少しでも身体を熱から解放して、アンタも落ち着け。――安心しろ、何もしやしねぇよ……」
「―――ッ!!………そ、そうね……」
自分とは裏腹に冷静な口調で、最後は苦笑交じりに言われてしまうと――この場合、もう同意するしかない……。
それに目の前にいるのは、ビーストマスター。いつもの彼なら、きっと………。
卑弥呼は赤面しつつも気を取り直した風を取り繕いながらチャイナ服に両手をかけて脱ごうとしたが、しかし既に汗でびしょ濡れになってしまった細身の仕事着は彼女の身体に纏わりつき簡単には離れてくれなかった。
「―――!!」
すると士度が子供の着替えを手伝うように彼女の上着を引っ張り上げ、スルリとそのチャイナ服を脱がしてしまった――突然上半身が黒い下着()
一枚になってしまった卑弥呼は慌てて胸元を隠したが、士度は彼女の上着を自分の衣服と同じところに片付けると、今までとまるで変わらない視線を向けてくる。
「………………」
卑弥呼はとっさに異性の視線を意識した自分が気恥ずかしくなり、胸元に置いた手を下ろし、手持無沙汰に前で組んだ――気付けば、先程まで身体を苛んでいた熱が少し和らいだような気がする。
ホッ……と一息吐けば、「少し楽になったみたいだな……」――微笑んではいないものの、士度はどこか労うような表情で卑弥呼を見下ろしていた。
「えぇ……―――ッ!!!?」
落ち着きはじめた自身の身体に卑弥呼も安堵の表情を浮かべたその瞬間――ガタンッ!!とトラックが派手な音を立てながら大きく揺れ、卑弥呼はその反動でバランスを崩しながら士度の胸元に飛び込む形で飛ばされてしまった。
――しかし体当たりされた当の本人は叩きつかれらるようにして倒れこんできた卑弥呼を受け止めてもビクともしない。
士度の腕の中で体勢を整えるべく身体を起こそうとした卑弥呼だったが、山道を登っているのか蛇行し続けるトラックの中で彼女の足元は覚束ないまま。
そんな危うい状況を見かねた獣王にやがて卑弥呼は片腕で肩を抱かれる形で支えられ、この狭い空間の中互いに半裸の身、自然ビーストマスターと素肌が密着する――
(―――!!)
彼の、少し汗ばんだ固い体躯の熱に直に触れ、卑弥呼の心臓が再び鼓動を速めた――そして肌を伝うその力強さとこの揺れの中微動だにしない彼の態は――卑弥呼に男と女の差を意識させるのに十分だった。
そして次の瞬間、
(〜〜〜〜!!!)
山道の急カーブをトラックが乱暴に曲がると同時に卑弥呼は下着越しとはいえ位置エネルギーと運動エネルギーに翻弄されるがまま、士度の胸元に自らの胸を押しつけてしまった――それはもう、“ムギュ”という擬音が聞こえるくらいの勢いで。
もしこれが蛮相手だったら赤面した卑弥呼を見た次の瞬間、奴はセクハラ紛いの言葉を吐きながらすかさず胸を揉んできたことだろう――そして自分はそんな蛮を張り倒し、ミッション中にも関わらず大ゲンカをして……。しかし――
「――大丈夫か?」
「え、えぇ………」
いつも通りの口調で聞いてきたビーストマスターがその後運転席の方を見ながら短く舌打ちをしたのは、その乱暴な運転に対してだろう――
(馬っ鹿だな、卑弥呼()!!閉ざされた空間で男と女が肌重ね合わせりゃ、次にヤることったぁ、どー考えてもひとつだろ!?)
――いつか口にした蛮の言葉が卑弥呼の脳裏を過った。
台風の夜に庇を借りに訪ねてきた蛮と天野銀次とその夜ピザとポテトを貪りながら惰性と戯れに見た映画――気が置けない友人同士だった男と女が、夜のアパートで戯れあっているうちにどちらともなく互いを求めあうという――そんなありきたりの展開に、卑弥呼が「どーしてこの手の映画って、毎度こうも安直な演出なのかしら!!」と顔を赤くしながら苛立ちを口にしたとき、蛮がポテトを口に放り込みながら言った台詞だ。
そのとき蛮は――視線をテレビ画面に固定をしたままだったが、その顔はその口調とは裏腹に、何故か笑ってはいなかった。
お前も、気ぃつけろよ――
独り言のようにそう言われ、そのときは“誰にどう気をつけるのよ……”と呟きながら別に欲しくもないドリンクを取りに台所まで行き、彼の言葉を適当に聞き流した振りをした――天野銀次はそんな二人の遣り取りよりも、テレビの中で絡み合う男女に、顔を真っ赤にしながらも釘付けだった。
「………………」
そして今自分は――日常生活ではあり得ないほど狭く閉ざされた逃げ場の無い場所で、男と女、二人っきりで、不可抗力ながらも汗だくになりながら肌を寄せ合い密着している――
ビーストマスターに支えられているとはいえ、トラックが揺れるたびに彼女の上半身だけではなく細身のパンツも、彼のジーンズに擦れる有様。
しかしそれでも、ドキドキしているのは何故か自分一人で………。
この状況で、たとえ彼女持ちとはいえ異性であるビーストマスターにこうまで反応されないと、女としての自分の魅力が皆無なのかと卑弥呼は一瞬自信を失いかけたが、しかしそう言えばビーストマスターは……――
あの半ば露出狂染みたの仲介屋の毎度の服装にも(大抵の男どもはそのギリギリのスリットやホルスタインのような胸元に釘付けになるのだが)顔色ひとつ変えない男だ――若い女性の依頼人に惚れられたなんだのときも当の本人は涼しい顔をしていたとも聞く。
彼にとってはマドカ嬢()
以外の女の存在なんて、きっと……
(――みんな、そこら辺を歩いている猫()
程度の感覚なんだわ……)
段ボールの奥にある通風口から入ってくる夕焼けの色が徐々に弱まるのを感じながら、卑弥呼は士度を見上げた――彼は光が揺れる方向に気をつけながら、揺れるトラックの中でバランスをとっているようだった。
肩を掴んでいる彼の手は男独特の厚みをもち、大きく――そしていつもは拳を振るう少し擦れた肌を持つ彼のその手の指が意外にも長いことに、卑弥呼は気づいた。
――そういえば今まで蛮以外の男の手を意識したことなんて、なかった……。
そして彼女の脳裏を不意に過ったのは、音羽嬢の穏やかな微笑み――
冬木士度()
この手が、彼女の頬に触れ、そして彼の手の甲にそのたおやかな白磁の手を重ね――花が綻ぶように柔らかく微笑む彼女。
卑弥呼()
が目にしたことのないそんな光景は、しかし現実だろうと卑弥呼は肌に伝わる士度の手のぬくもりとその力強さを感じながら眼を伏せた。
例えば音羽嬢()
が――似たような状況()
で、同じような格好をしていたら、ビーストマスター()
の顔は少しは朱色になるのだろうか――
峠を越えたのか、再び高速にのったのか――ややしてトラックはその激しい動きを止め、また規則正しいスピードで走りはじめる。
するとビーストマスターは卑弥呼を支えていた手の力を緩めると、その背を再び段ボールの壁に預け、その長い左脚を徐に対面の段ボールの壁まで蹴りつけるようにして伸ばした。
それでも彼の脚が緩く“くの字”に曲がるほどのスペースしかないこの場所、これでは自分の立つ場所がなくなると卑弥呼は彼の胸元で苦情を口にしかけたが、
(――――!!?)
不意に彼女の細い体はフワリと持ち上げられ、対壁まで伸ばされた彼の左脚の大腿にチョコンと座らされてしまった。
「〜〜〜!!?ちょっ!!アンタなにやって……!!?」
「この熱、下からきてるらしい――」
――足つけたまんまだと、アンタの体力じゃもたないぜ?
「――!?あ………」
両腕を腰のあたりでゆるく組むことで彼女を支える士度の言葉に、卑弥呼は何かに気がついたようにその眼を大きく開けた――足が宙に浮いたことにより、彼女の身体を取り巻いていた熱が足元から離れていくように身が少し軽くなった。
コンテナの中を唯一照らしていた夕焼けの光が、暮れる直前の最後の輝きを二人に注いだ――士度は決して安定しているとはいえない場所に座る卑弥呼がずり落ちてしまわないように、大腿の上の彼女の腰に両手を緩く回すと、その先で手を組むことで姿勢を整えた。
「……ありがたいけど、こんな姿勢であと四時間って………」
「――体力だけは、あるつもりだ」
アンタが大変じゃない――続いたであろうそんな卑弥呼の台詞をわざと遮るように、今回の相棒は緩く苦笑してみせる。
「……そう………」
最早何があっても今更だし、ビーストマスターもやっぱりいつもの彼だ。
卑弥呼は彼の上で漸く肩の力を抜いた。彼女が腰をかけてもビクともしない彼の大腿は、まるで丸太の椅子に座っているようだった。
「………………」
しかし、やっと気持ち的にもリラックスできる状況とはいえ、やはり口数が多い方ではない二人――仕事を共にこなした回数も数あれど、こういう場合()
は如何せん会話が続かない。
拠りどころなく卑弥呼が段ボールだらけの閉鎖空間に視線を流し、走るトラックの中を揺れ動く鮮やかなオレンジ色が視線の中を徐々に薄くなっていく――そんなコントラスト以外は大した発見もなくその視界を一周させてもとに戻そうとした刹那、彼女の眼を掠めたのは、鋼のように鍛え上げられた相棒の体躯。
夜色に近づく夕焼けの橙の中に薄らと浮かび上がったのは、その逞しい肉体の上を処々にはしる瘢痕の数々――
「………………」
過去に深く抉られたであろう他より顕著な脇腹の疵痕も、今では鍛錬された筋膂によって目立たなくなってはいるが――彼の胸元を薄くとも長く酷に奔る刀傷、二の腕に鋭く引き攣るように残る矢傷の創、崩れる星の様な痕を遺す槍手、白く、処によっては濃く変色した治癒の名残――それらは激しく冥い戦の痕跡、彼の体躯に酷虐に刻まれた、忘れえぬ血刃の記憶。
「――珍しいか?」
「………痛そうね。」
卑弥呼のそんな視線の方がむしろ珍しいとでも言うような士度の声に、卑弥呼は思ったままを伝えると、その一番大きな古傷にそっと手を伸ばした――憐みでも慰めでもなく、今、こうしないことこそが彼の過去に対する非礼なのではと、半ば無意識にとった行動だった。
士度もそれを嫌がる素振りを見せなかった――卑弥呼の手は彼の過去の痛みを語るような雄々しく奔る傷痕を労わるように刹那辿り、そしてそっと離れた。
「……見える疵はまだいい――痛みが去れば、痕が残るだけだ」
男にとっちゃ、大した事じゃねぇよ――
どこか自嘲気味に呟く士度の言葉を、卑弥呼は彼の向こう傷を目で辿りながら聴いていた。彼はときどき――周りの人々がもどかしく思うほどに、自己を顧みなくなる。
愛する人を守る為ならば、傷つくことに恐れを知らず、命すらその為の武器にする……。
「見えない傷の方が、恐い?」
「――そうだな。傷つけたくねぇって、思うんだが……」
彼はそこで言葉を切った――蟲達に攫われ、その身を器に堕とされ蹂躙された彼の想い人――それは士度()
にとって明らかなトラウマであり、身に巣食う何よりも大きな内なる創()
。
(傷つけたくない()
、か………)
彼の脳裏を過った狂おしいまでの想いを察しながら、卑弥呼もまた言葉を噤んだ。
彼といい蛮といい天野銀次といい、あの風鳥院家の跡取りといい……そして死んだ邪馬人()
といい――それぞれ性格とその表現方法は全く違えど、卑弥呼()
の周りには他人のことを気にかけない男どもが多すぎる。
――もっとちゃんと、自分のことを考えなさいよ!――彼らの胸倉を掴みながらそう叫んでやりたくなる衝動に駆られるのも、嘘ではない。
自分が流す紅い血よりも、隣の誰かが可視不可視の傷を負うことを怖れ、憂う彼ら――
馬鹿ね……―ほんとうに、馬鹿なんだから――
守ってやらなきゃ……って思うじゃない……――
そうやって自分が微力ながらにも蛮に想うのと同じように、音羽嬢()
もきっとそう思っている。
ときに非情となり、そしてその強さと力を驕らず自負しながらも――いつかは枷となるかもしれない、そんな優しさ故の“怖れ”を捨てきれない彼ら。
そして冬木士度()
も――その刻みつけられた傷の数だけ、見えない疵を心に負わされただろうに――彼はそれに目を瞑っている。
血を伴う痛みに耐え――たとえそれが癒され痕になっても、まるでそれが罪といわんばかりに、その奥にある創痛は紅い涙を滾々と流し続けている。
(この疵の向こう側で、アンタは誰を失くしたの……?)
訊きたい言葉を、卑弥呼は士度の膝の上で飲み込んだ。魔里人と鬼里人の憎しみの連鎖とその凄烈な様は、その血で血を洗う最後の局面を目の当たりにした自分も嫌というほど思い知らされた。
あの憎悪の渦中に幼少の頃から身を浸し、今もその源を胸に宿しながら生きる運命を担っている彼()
が失ったものは、ただ末路の一端に参戦したにすぎない自分たちには計り知れないものだろう――
冬木士度()
の仕事に対する姿勢や、極稀ではあるが不意に垣間見せるあの凍りつくような冷眼が赤屍()
に似ているのは――血戦を潜り抜けその慟哭を知る者達だからだろうと、卑弥呼は思う。
現に赤屍()
は――方や尽きぬ敵対心をもって、方や戦々恐々と涙目で――自分の姿を見るたびにそんな反応をしてくるGBとはまた違う視点で、冬木士度()
を観察しているようだ。
獣王に秘められた魔の力が――いつ禍々しくその嘴()
を開け、そして彼自身の本性と共に業火のように燃え上がるのか――それを待つ喜びを、あの運び屋
()
はまるで楽しんでいるような貌で彼を観ている。
(――普段はこんなにも、静かな奴なのに……)
するとどこか悲しげに俯く卑弥呼の頭上から不意に――慣れた声がおりてきた。
「――じきに日が落ちてこの中も暗くなる。一眠りでもして身体、休めておけ……」
「うん……」
みると士度も少し無理な体勢にも関わらず、先程と同じように眼を瞑り軽く俯くことでそのまま残りの時間を過ごすつもりのようだ。
卑弥呼も彼に習うように眼を閉じた――不慣れで不安定な場所なはずなのに、彼の膝の上が妙に心地よく感じたのはきっと――あぁきっと……邪馬人()
にどこか似ているからだ……――
あれだけ煩わしかったトラックの揺れも、もう気にならない――彼の腕に背や腰があたっても、それも今ではむしろ安心だ。
コンテナに籠る熱に散々煽られたせいだろうか、卑弥呼は疲労を訴える身体に促されるように強い睡魔にその身を引かれた。
――彼の腕や脚から伝わる体温が、子守唄の代わりに卑弥呼の心を安堵させる。
ごめんね、少し借りるわ……――
卑弥呼は心の中で小さく、相棒()
の想い人に謝罪した。
「……………」
身体に傷がつくのは構わなかった――むしろ戦場では、己の血が肌から吹き出し、その後刹那遅れてやってくる痛みと血の臭いこそが、炎と火薬と死と憎悪と悲鳴の血煙に慣れて曇っていく視界と思考からの覚醒を酣戦の中で促し、再び生へと駆り立ててくれる。
今、自分の躯に奔る疵は――云わば己を生かしたのだ。
そして一族の怨悪を返す刃と拳に託して放った――敵の肉が裂ける感触、骨が断たれ砕ける音、目の前に迸る禍々しくも鮮やかな紅、命を散らす間際の呪いの声――それらは戦塵の中での道標だった――死戦のなかで、己が修羅になるが為の。
“生き残る”“生き延びる”――そんなことは重要ではなかった。それは彼にとって戦の合間の虚空を刹那見上げるときについてきた、謂わば結果論に過ぎなかった。
長の子として――戦士として――そして己の意思で――
守りたいものが、そこには確かにあった――しかしそのなかに、士度は己の幸福を望むことも、祈ることもしなかった。
それは里の者たちが、動物達()
がそして彼の父である長が、彼に望んでいた守るべきものだったのだが――当時の彼はそれを想像だにできず、故に己の中の揺ぎ無き思いを糧に血に塗れることも、そして自らを囮に里から離れることも厭わなかった。
そして――無限城を出た後に唐突に降ってきた幸せに――士度は初めて心から恐怖した。
それは、彼が守り方を知らない――幸福()
だった。
まっしろな雪の上にキラキラと輝きながら降り積もる新雪のように、己の心に穏やかに優しく、しかし確かに満ちていくソレを――士度はどう扱えば、そしてどんな反応をすればよいのか、まるで分らなかった。
今考えてみると、当時の自分はマドカの前では本当に憶病で――過去の守りきれなった記憶が業火のように己の中を渦巻いたのもそのときだ。
そしてこれらの“傷”の痕を初めて意識したのも、彼女とひとつ屋根の下で暮らすようになってからだった。
温室育ちのお嬢さんが見たって、決して気持の良いものではない――むしろ己の粗野と残酷さを見せつけるような戦の痕――士度は彼女()の眼が見えないことに、初めて感謝したものだ。
しかし褥を共にするようになって、彼の安念は脆くも崩れ去る。目が見えない分、人一倍敏感な彼女の指先は――やがて彼の躯中の疵の場所を、一つ残らず覚えてしまった。
そして事も無げに云うのだ――
この傷ごと、士度さん()
のことが好きです――
大好きです……。
そう、この醜い疵痕に指先を這わせた彼女()
もそのときやはり――今日の工藤卑弥呼()
のような儚く悲しげな表情をした。
――痛そうですね……――
古傷でもう痛みはないのだと伝えれば、そうではないとマドカは悲しそうに頭を振った――
この傷の奥の、士度さん()
の心が………――
「………………………」
外の陽は疾うに暮れ、僅かに揺れながら路を行くトラックの中は既に闇に包まれていた。止まる気配は一向にない――道程はまだ大分あるようだ。
レディ・ポイズンは眠っている――確か歳はマドカとそんなに変わらなかったと思う――信用してくれているのか、普段はキリリとしている彼女からはあまり想像のつかない、どこかあどけない寝顔で身を任せてくれている。
身長はマドカより少し低いくらいで――それで同じ女でも、身体つきはだいぶ違うように感じる――不思議なもんだ。
「…………………」
士度は卑弥呼の寝顔に小さく苦笑すると、やはり躯を微動だにさせないまま、もう一度微睡の中に身を委ねた――
「………………!!」
ふと眼を覚ますと――コンテナの中は真っ暗闇で、ただ俯いていただけだったはずの頭は硬い枕の上にあった――どうも知らず知らずのうちに、ビーストマスターの胸筋を枕にしてしまっていたらしい。
熟睡もいいところだ。
「〜〜〜!!………………」
卑弥呼は僅かに赤面しながらも、士度の胸元からソッと頭を離して様子を窺った――反応無し――そして空気が揺れている気配も無い。
「………………」
いつのまにか陽が落ちてしまい闇に包まれたコンテナの中で、卑弥呼は眼を慣らそうとビーストマスターの顔があるであろうあたりにじっと視線を固定した。
トラックのタイヤの低い音に加えて、時折水溜りを撥ねる音と長く水を切る音が足元から――そしてバラバラとコンテナを打つ雨の音が上から聞こえてくる。
ビーストマスターは動かない――やがて慣れてきた卑弥呼の眼は、閉じられた士度の瞼と、少し薄い唇を捉えた。
「………………」
ごく自然に閉じられている唇は、ひどく無防備に卑弥呼の眼に映った。
少し背を伸ばせば卑弥呼の唇も届く距離に彼の顔もある――不意に、小さな好奇心が卑弥呼を襲った。
こんな密着閉鎖空間で半裸の若い女を目の前に(いくら仕事上の付き合いとはいえ)何のリアクションも見せなかったビーストマスター……。
それがもし、逆の立場で――つまりほんの刹那であれ手を出されたら()
いったいどんな反応を見せるだろう?
驚きのあまりその細い眼をめいっぱい丸くする?呆れて声も出せない?蔑んだ視線で私を射抜く?真っ赤になって声が上擦る?それとも――珍しく大声で罵倒する……?――
「………………」
恋でも愛でもなく――ただの戯れの為だけにこんなことを思いつく自分に卑弥呼は心底呆れてはいたが、ようするにこんな状況()
に置かれても何の反応もされなかった()
ことを自分は何だかんだで気に病んでいるらしい。
それに今日この空間ではあまり表情を変えていない彼の空気に、ほんの少し変化を求めたかったのも確かだ。
「………………」
座らせてもらっている彼の大腿に両手をつき、卑弥呼は眼を開けたまま僅かばかり背伸びをした。そしてその顔をゆっくりと士度の顔に近づけていった――
闇と濃灰の間の世界で静かに目を瞑るビーストマスターの顔をこんなに間近に繁々と見るのは初めてだった。暑ければ取ればいいのに、不可思議な紋様が施されたバンダナもいつも通り額を飾っている。
山育ちでどちらかというとパワーファイター的な部類に入るであろうビーストマスターだが、こう間近で改めて見ると、案外整った顔をしているもんだ、と卑弥呼は思った。
ただ――開いた眼の細さと鋭さとこの鍛え上げられた長身の体格が、この端正な顔立ちに野性味を加えているのだろう――
「………………」
あとほんの少し……その身を伸ばせば、卑弥呼の唇は容易に士度()
のそれに届く―― 一瞬、彼女の脳裏に皮肉な笑みを口元に湛えた蛮の姿がよぎったが、卑弥呼はそれを振り切るように眼を瞑り――暗闇の中でそのしなやかな背を伸ばした。
そして、微動だにしない彼の唇に、彼女の柔らかな唇が触れようとした、まさにその瞬間……――
「〜〜〜〜ッ!!!!?」
「――――ッ……着いたみたいだな……」
緩やかながら、ガクンッ――と停車したトラックにつられ卑弥呼は士度の上でバランスを崩し、彼の喉元に頭突きをしてしまう始末。
そんな卑弥呼を反射的に支えながら彼女の上から発せられたビーストマスターの声がとても寝起きのソレに聞こえなかったことに、卑弥呼は貌は驚き半分悔しさ半分の朱に染まった――
「〜〜〜っ!!!アンタいつから起きて……!!?」
「―――アンタの出番だぞ……」
ビーストマスターのそんな台詞に、急に伸びてきた彼の大きな掌の下で卑弥呼は思わず唇を引き締めた――そしてガチャガチャとコンテナの扉が鳴り始めるなか、彼女は腰のベルトに並んでいる小瓶を指で辿り、目的の一つを慣れた手つきで取り出す。
外からは相変わらず雨音が聴こえる――香りの流れが湿気に捕らわれないよう、重く、長く、香りを流す必要がある……。
「……………」
卑弥呼の合図に士度は彼女を自分から下ろすと、コンテナの鉄の壁に背をつけることで卑弥呼から精一杯離れた。ここで彼女が流す香りを吸ってしまっては元も子もない。
チャンスは一度きり――目の前の段ボールが動いたその刹那……――
「――止まないわね。」
「止まねぇな……」
数十分後――士度と卑弥呼はトラックの目的地であったS山のホテルの一室のベッドに並んで腰を掛け、窓の外を飽くことなく流れる雨脚を、ただ何となく眺めていた。
ややして士度が徐に立ち上がり、先程卑弥呼が使ったばかりのシャワールームへと無言のまま消えていった―― 一方ホテル備付の浴衣に身を包んだ卑弥呼は、疲労感を隠さぬまま腰掛けていたダブルベッドにその背を預けた。
実際、自分とビーストマスターは良い仕事仲間だと思う――ついさっきだって、上手い具合にコンテナを抜け出せた――難しい状況の中においても卆なく毒香()
を操れたのは、異常な閉鎖空間の中での五時間を比較的まともに過ごせたからだ。
コンテナの中で催眠香の睡魔に昏倒した二人の若者をビーストマスターが迅速に人目につかぬよう運転席と助手席に運び――
そして二人で手分けしてコンテナ内の積み荷を適当に運び出しておき……
(そうすれば二人の若人が目覚めたとき、自分たちは作業の後、疲れて果てて眠ってしまったんだと思うだろう)
奪還屋運び屋の二人は再び身につけた汗と雨に濡れた上着に不快感を感じながらも、深夜で雨でやはり今宵は帰宅どころか下山も無理な状態なので、予定通り仲介屋が予約を入れてくれた目の前のホテルにチェックインをした――
二人が同室予約になっていたので(後で仲介屋を締め上げてやろうと卑弥呼は思った)、何かの手違いだと卑弥呼が部屋の追加を求めても、この雨故に峠越えのツーリング客で既に満室状態だと受付係に頭を下げられた。ロビーのソファに座って待っていたビーストマスターに視線を移せば、「庇があればどうでもいい」――心底そんな顔をしていた。
「………………」
ダブルベッドとは案外狭いものだ――山越え用の素泊まりホテルせいか、清潔感はあるものの極々簡潔な造りのカップル用の部屋を見渡し、卑弥呼は小さく溜息を吐く。
着いた時間も時間だっただけに、娯楽の無いこのホテル、他の客たちはとうに自室へと引っ込み、ホテルの食堂も閉店済、自分たちが手に入れた夕食といえば、自販機で買ったビールと水と酒のつまみとポッキーくらいだ。
「………………」
気怠い疲れにうんざりしながらも、さてこの狭いベッドを今夜二人でどう分けようかと卑弥呼が考えあぐねていると、ベッドのサイドチェストの上に放り出してあったポーチから、今回のターゲットが顔を覗かせていた。
卑弥呼は誘われるようにそれを手に取り、包んである和布を開いてみると――出てきたのは月の下を秋草に駆る兎の金蒔絵を鮮やかに施した深い朱塗りの櫛。今回の依頼人達の、愛の証。
「奇麗なもんだな――」
不意に上から響いてきた静かな声に、卑弥呼は櫛から視線を外さぬまま「そうね……」と呟いた。
きっとマドカにもよく似合う――彼の言外にそんなことを想像しながら、卑弥呼は口元で小さく笑みを作った。
そう遠くはない未来に純白のドレスに身を包むであろう彼の想い人の至幸は、きっとこの櫛の輝きも霞むほど。
卑弥呼がチラリと彼の方へ視線を流すと、彼は頭を拭いたであろうタオルを首にかけたまま、僅かに着崩した浴衣姿で冷蔵庫から冷えたビールを取り出し、片手で器用にプルタブを開けていた。
そしてドカリと卑弥呼の反対側に再び腰を下ろすと、一気に喉を潤したようだった――彼の躯から微かに香る石鹸とツンとしたアルコールの匂いが、卑弥呼の瞼を重くした。
彼女はその櫛を再び和布に包むと元の場所に仕舞い、ビーストマスターの方を振り返った――彼は既に身体を横にし手枕をし目を瞑り――相変わらず寝に入るのが早い。
「……あんだけ寝たのに、また寝るの?」
「この雨んなか、他に何すんだよ……」
反対側を向いているビーストマスターから、どこか眠たそうな声が返ってきた――それもそうだと卑弥呼も思ったが、今日は何かと近い二人、しかも最近組むことが多い割には仕事ばかりで……――
「話でも……しない?」
そんな卑弥呼の言葉に姿勢を変えず、ただ首だけめぐらせてきたビーストマスターの表情は、少し目を丸くすることで“意外”という言葉を無言に語っていた。
「………ほ、ほら、最近結構一緒の仕事が多いけど、こうやって落ち着く時間なんてほとんどないし、アンタとは知り合って長いような短いような………」
「――話、か………」
少し言葉が走る卑弥呼とは裏腹に士度は器用に身体の向きを卑弥呼の方へと変えると、どこか考え込むように呟いた。
何の――? 例えばそう訊かれたどう答えようか――卑弥呼がそう冷や汗交じりに彼の言葉の先を待っていると……
「例えば……さっきアンタがトラックの中で意外にも気持ち良さそうに爆睡してたこととか、か……?」
「〜〜〜〜!!!ちょっと!!アンタも寝てたんじゃないの!!?」
ホントどっから見てたのよッ!!?――卑弥呼が反射的に放り投げた枕はビーストマスターの広い掌に阻まれ――そのまま彼の枕になってしまった。
「それとも……さっき俺に悪戯しようとした事……」「〜〜〜〜〜!!!?ア、アンタどこまで……ッ!!!」
士度の台詞は途中で遮られ、彼の顔面に二つ目の枕が飛んできた――どこか可笑しそうにそれを避けるビーストマスターの貌は、確かに卑弥呼が初めて見るモノ。
「……男の膝の上でああも無防備になるたぁ、案外アンタも余裕なんだな……」
「〜〜ッ!!そ、それは!!昔邪馬人()
がよくああやって……ッてそれよりアンタだってあれだけアタシと密着しといて――!!」
―――漫才紛いのそんな会話は二人の想像よりも遥かに続いた。
やがてそれは雨音に惹かれるようにポツリポツリと互いの独り言のような人事のような昔語に変わり、丑三つ頃に卑弥呼の声音に小さな欠伸が交るまで穏やかに続いた。
「………………」
緩やかな眠りに落ちた卑弥呼に士度が掛布を掛けてやったときには、合間買い足した酒やつまみやジュースの類は結構な量になっていた――
「――でね、ホントよく寝るのよ、ビーストマスター()
は……。帰りの電車の中でも、駅弁食べ終わったらいつの間にやら目ぇ瞑っちゃってるんだから!」
それでもコンテナの中といい、電車の中といい、ちゃんと時間になると目を覚ますのが不思議なところなのよね……――
いつもよりどこか饒舌な卑弥呼に波児は愉快そうに相槌を打ち、「アンタらは普段から時計に頼り過ぎてんだよ……」――そんなことを言いつつも、卑弥呼の隣に座っていた士度は喫茶店の壁掛け時計に視線を流した。
「おや、もうそろそろかい?」
珈琲を飲みほす士度のそんな様子に波児が訊くと、「あぁ……」と短い返事が返ってきた。
音羽嬢とは昼過ぎに新宿の外れの、静かなオープンカフェで待ち合わせ。連絡をとったとはいえ、結果夕食をすっぽかしてしまったお詫びに今日は昼食の後、買い物に付き合うことになったとビーストマスターは言っていた。
背後で来客を告げる扉のベルが鳴ったが、いつもの如く戯れあいながら飛びこんできた二重奏を、誰も気にとめはしなかった。
「仲介屋に宜しく言っておいてくれ――」
「文句は言わせないわよ……」
どこか挑戦的に片眉を上げた卑弥呼に士度は「頼む」と苦笑交じりに礼を言うと、マスターに小銭を渡しながら席を立った。
「まいどあり♪」空になった珈琲カップを下げるマスターの機嫌の良い声音と、卑弥呼と交わした二言三言に送られながら出口へ向かうと、そこには丁度入ってきたばかりらしい二人の奪還屋の立ち尽くす姿が。
「え……士度?」 「――?よう銀次、またな。」
どこか冷や汗交じりにパクパクと口を開けている銀次の様子に士度は疑問符を浮かべながらもすれ違いざまに声を掛けた――すると次の瞬間、反対側から士度の腕を尋常ではない力で掴んできたのは、美堂蛮の右手――
「――てめぇ、どーゆーつもりだ!?」
カウンターにいる波児と卑弥呼にとりあえず配慮してか声は低く抑えてはいるものの、サングラスの奥の胡乱げな眼差しと、カウンターと自分達を忙しなく往復している銀次の視線に、士度は美堂蛮が思うところを察し――
「――阿呆。」「〜〜〜!!?なっ……!!!」
冷やかな視線と共にそう言い放つと、絶句する美堂蛮の右手を自分の腕を握っているソレと比べてやはり遜色ない力で振り払うと、重くはない足取りで、居心地の良い喫茶店を後にした。
「……アンタはなんでそうやっていつも、ビーストマスターに喧嘩売るのよ?」
「……そんなことより、卑弥呼。その椅子、近すぎやしねぇか?」
「――?そうかしら?」
呆れを隠さない卑弥呼の台詞を、蛮は再び疑問符で返した――そしてつい先ほどまで士度が座っていたカウンター席を、左足で行儀悪く小突いた。
一方卑弥呼は蛮の言動を少し不思議そうに見つめただけで、彼の真意を読み取れていないようだ。
「あ、あれ…?夏実ちゃんとレナちゃんは…?」 「あぁ、二人は今お使いに行ってもらっているから……」
きっともーすぐ戻るよ――波児の言葉に銀次は少し肩を落とした。だってさっきHONKY TONK()
に入ってくるなり目の当たりにした卑弥呼ちゃんと士度の距離――いつもより“近い”って思ってしまった。
それになんだか二人の話す雰囲気が――いつもと少し……なんだろう……少し羨ましい感じで……――
二人がどんな会話をしていたかなんて、マスターはベラベラと喋る感じじゃないし……卑弥呼ちゃんだって……。
看板娘たちとのお喋りついでにあわよくば――の画策も脆くも崩れてしまったのだが、“士度ばっかり何故もてる!?”の疑問に取りつかれてしまった銀次は、いつまでもソワソワと落ち着きがない。
「……お前、猿回しと随分と仲良し小好しな雰囲気だったな?」
「そーかしら?」
卑弥呼は出てきたケーキにフォークをつけながら、蛮の台詞など意に介する様子もない。波児だけが蛮の額にくっきりと浮かんだ青筋に苦笑している。
「ほ、ほら……士度ってあんま、喋る方じゃないのにさ!さっき卑弥呼ちゃん、なんだか楽しそうにお喋りしてたから……」
「………そう?」
銀次の言葉に卑弥呼はやっぱり不思議そうな顔をしたが――フォークの下のケーキを切りながら、どこか懐かしそうに呟いた。
「……色々と上手いのよね、ビーストマスター……」
「〜〜〜〜!!!?」「ブッッ!!!え、えぇぇぇっぇっぇぇぇっぇ!!!!?」
煙草を取り落としたり珈琲を拭いたりのGBに構わず、波児は落ち着いた様子で卑弥呼に同調する。
「本人も言っているように、不器用な面もあるんだけどね。黙っていてもよく気がついてるし、士度君はいつも自然体だから……不思議と、ね……」
「ホント、マドカさんが羨ましいわ……」
目玉が飛び出さんばかりに目を丸くし二の句が継げない蛮と銀次をよそに、波児と卑弥呼はどこか仄々と件の人の噂話をしている。
そこへナイスバディとバストを揺らしながら入ってきた常連客の仲介屋は開口一番――
「はぁい、卑弥呼ちゃん♪昨夜はアレが精一杯だったのよ、ゴメンね!でも士度クンだから一晩くらい同じ部屋だって……あら、蛮。顎が抜けそうよ?――ちょっっ!!!?銀ちゃん!?チョコレートでも食べ過ぎたの!?マスターおしぼりおしぼり!!」
カウンターに撃沈した蛮と妄想が暴走して鼻血塗れになった銀次の心意を読めぬまま、卑弥呼は「相変わらず騒がしい連中ね……」と溜息を吐いた。
そして――時には仕事の相棒として、時には―茶飲み友達だったり、邪馬人()
を思い出させたり――そんなビーストマスターのとの距離が、頼もしくも心地よいものに変化したことを――誰にともなく、心密かに感謝した。
ヘックシッ……――
「――?お風邪ですか?士度さん……」
「……いや、ここの空調がちょいと効きすぎてるのかもな……」
高級スーパーの鮮魚売り場で噂話に擽られた鼻の頭を、士度は人差し指で軽く掻いた。
「あら大変!それでは早くお魚を買って出ましょうね?今日は士度さんが好きな秋刀魚を……どのお魚が美味しそうですか?」
軽く身を屈めたマドカと同じように士度も彼女に合わせ、夕食の食材を選ぶ彼女を手伝った。
今夜は彼女が夕飯を作ると言ってはいたが、魚を焼くときにバイオリンを奏でるその細い手を火傷したりしないようにこっちが注意しとかねぇと……――
士度が選び、魚屋に袋にいれもらったお目当ての物をマドカに持たせてやると、今夜の調理が楽しみだと、彼女は眼をキラキラさせながら喜んだ。
そんな彼女の笑顔に何度でも絆されてしまう自分に苦笑しながらも、士度は彼女にだけ向けれられる――とても穏やかな表情でその想い人を見つめた。
その視線に気づいたのか、不意にマドカの頬が朱に染まる。そして手にしていた袋をカートに入れると、いきましょう?とどこか恥ずかしげに愛らしく士度を促した。
「そうだな……」
士度もカートの押し手に手をかけた――彼女の手が添えてある、すぐ隣に。
「………………」
マドカが僅かに手を滑らせると、彼女の小指が彼の小指にコツンとあたった――彼の優しい視線が、降りてきた。
そしてその視線は穏やかに語る――「わかっている」と。
レジまでカートを押す間、互いのいちばん小さな指先から感じる煖かさがマドカの心を欣幸に染めた――
それでも――きっと今日はもっと――彼のことが愛しくなる――
「ほ、他に何か――食べたいものはないですか?」
きっと真っ赤になっているであろう自分の顔色を誤魔化すようにマドカが士度を見上げれば、
「そうだなぁ……」
――と、歩を進めながらも思案の声が聞こえ、やがて彼の歩みがピタリと止まった。
<― ― ―>
そして彼女の耳元で囁かれた一言に、マドカの鼓動が跳ね上がる――
「〜〜ッ!!も、もう……!!ふざけないでください……!」
ポカリ、と彼の腕を叩きながらマドカが小声で抗議をすると、「そりゃ残念だな……」――返ってきたのは彼の苦笑。
「……………ッ」
マドカは眩暈がしそうなくらいに奔る鼓動の中で、彼の素直な返事に身を焦がす――話すのは不得手な方だ――そう言いながらも、ときどきこんなにも――心を揺さぶることを言ってくる、困った人。
「――そ、それは……。一番最後のデザートです……!」
マドカがやっとのことで呟くと、彼の周りの空気がまた少し明るくなったように感じた――「じゃあ、早く帰って飯にしようぜ……」
カートの上の彼の小指が、トントン……と軽やかに押し手を叩いた。
お会計を済ませたら――この荷物、士度さんは片手で持てるかしら……?
彼にお見通しは百も承知、それでも少し怒った振りをしながら、マドカはそんなことを考えていた。
もし、彼の片手が空くのなら、今度は小指の先だけではなくちゃんと――彼と手を繋げるから。
彼の心が伝わってくるそんな煖かさと幸福()
に――夜の帳が下りるまでにゆっくりと、この身を溶かしていきたいから。
彼女()が求める距離を士度は知っていた。自分が求めるそれはきっと彼女のよりも、もっと貪欲な距離かもしれないことも自覚していた。
そして工藤卑弥呼()が求める、どこか懐かしい距離も――過去の束の間の平和を思い出させてくれる、互いの望郷を映し出す距離であることを知っていた。
去り際の相棒の笑顔を思い出しながら、士度は詰めた袋を片手で持ち上げると、空いた手を――
迷いなく彼女()へ差しだし、その太陽のような笑顔に思わず貌を綻ばせた。
Fin.
最近管理人的流行の士度&卑弥呼+本流士マドなお話でしたv男女の距離も色々…思うところも色々。