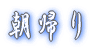
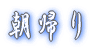
その野良猫は、気まぐれにやってきた。
来たいときに来て、お勝手口でニャア、と鳴いてミルクをねだった。
大きなオス猫だったと思う。
コックさんは、立派な縞模様のトラ猫ですよ、と言っていた。
彼が食事をしているときに私が悪戯に触っても、爪を立てたりしなかった。
彼の少し埃っぽい毛皮は、それでもフワフワしていて気持ちが良かった。
けれど、抱っこをしようとすると怒られた。
フゥ!と威嚇して毛を逆立てた。
私が一歩下がって、しゃがんでまた彼の様子を窺うと、
その野良猫は何事も無かったかのように食事に戻る。
そしてお腹一杯になると何処かへ帰って行った。
毎日来るかと思えば、ニ・三日の間を置いたり、時には一週間も二週間も来なかったり。
いつしか、うちのお庭でまどろんで行くようになり、
やがて、庭の物置を住処にするようになった。
そしてフラリと何処かへ行って、いつもフラリと帰ってきた。
私には自分の方からは決して寄ってこなかったけれど、私を拒絶するようなことはしなかった。
ただ、抱っこだけはさせてくれなかったけれど。
喉を掻いてあげたり、耳の後ろをくすぐってあげたり、一緒に日向ぼっこをしたり・・・・
彼がミルクを舐める音、尻尾をパタパタさせる音、音も立てずに歩く気配、
喉をゴロゴロ鳴らしたり、ザラリとした舌で毛づくろいをする様子―― 。
沢山の愛らしい音と穏やかな時間を、彼は私に与えてくれた。
それでも彼は相変わらず野良だったけれど。
彼は私の友達だった。
傍に居てくれたら、嬉しい存在。
けれどある日を境に―― 彼はフッといなくなってしまった。
いつものように帰ってくると思っていた・・・彼は時々長い散歩に出るから。
オス猫ってそういうものですよ―― 誰かが言っていたし。
毎日毎日、お勝手口やお庭の気配を私は気にした。
それでもあの大きな存在を欠片も感じることが出来なかった。
一月経っても二月経っても・・・彼は戻ってこなかった。
私は一人で日向ぼっこをした。
そしてある日、知ったのだ。
彼はもう二度と戻っては来ないと―― それは予感ではなく、確信だった。
何かが、私にそれを伝えた。
私は泣いた。一人で。私の隣にいた彼の為に。
―― 俺は野良猫みてぇなもんだからな ――
少し自嘲気味に彼は言った。
―― まぁ、次の居場所が決まるまで、お世話になるぜ ――
私はすぐに、彼の気配が好きになった。
彼から私の方へ寄ってくることはないけれど、私を拒絶するようなこともしない。
他愛のないお喋りをしたり、お庭で一緒にお弁当を食べたり、日向ぼっこをしたり・・・
彼はこのお庭が気に入ったと言ってくれた。
私のバイオリンの音色も心地良いと言ってくれた。
彼が隣にいる時間が好き。
彼と一緒に居れば居るだけ、私は彼のことをもっともっと知りたくなる。
彼が歩く音、彼の癖のある咳払い、彼の・・・私の耳には優しい声。
彼からもたらされる音に、私はいつもドキドキさせられっぱなし。
動物と一緒にいるときの彼の穏やかな気配、一人でいるときの静かな様子、
そして時折感じる、照れているような、困ったような表情。
彼の違った“顔”を、もっと知りたくなる。彼の“音”をもっと感じたくなる・・・。
彼が同じ屋根の下に住むようになってから、私の世界は徐々に変わっていった。
その変化が、私には新鮮で楽しかった。
そしてある夜―― 不意に庭がざわめいた感じがして、私の眠りを妨げた。
けれど、それは私が完全に覚醒する前に治まって、すぐにいつもの静かな夜が戻ってきた。
それでも、私が気がついた気配・・・彼はどうしているだろう?
そんな風に思って、私は彼の部屋に行ってみた。
ノックをしてみても、返事は無い。
ドアノブに触れると、鍵は掛かっていなかった。
―失礼します・・・― そう言いながら私はドアを開けた。
夜風が私の髪を遊んだ。
カーテンがはためく音がした。
彼の気配を―― 感じなかった。
私は彼が使っているベッドへ腰掛けた。
ベッドメイクされたままで、ただ枕だけから彼の匂いが微かにした。
何故だか―ここで待っていたら彼が帰ってくるような気がした。
自分が使っている部屋に勝手に入り込まれて、勝手にベッドを使われたら彼だっていい気はしないだろう。
でも・・・私はその枕を抱いて、ベッドへ身を横たえた。
夜が明ける前に、彼が開いた窓からフラリと帰ってきてくれることを願いながら。
夜明けの烏の声がした。
私はベッドに一人きりだった。
不意に、あの野良猫のことが頭を過ぎった。
何も言わずに消えてしまった、隣にいた彼。
私は部屋を飛び出すと、急いで着替えを済ませて、
熟睡していたモーツァルトにごめんね、と謝りながらも起きてもらった。
そしてそっとエントランスを抜けて、外へ出る。
朝靄が頬を掠めた。一日の始まりの空気が肺を潤した。
新聞配達のバイクの音が聞こえる。
牛乳屋さんの自転車も走っている。
私は・・・何をしているのだろう?
そんなことを思いながらも、私は彼の気配を探した。
彼、は自由だ。
何処で何をしようと、これから何処へ行こうと、他人なんかきっと関係ない。
彼はあの野良猫のように気ままに行動するのが性に合うのだろう。
私にも彼を束縛する権利なんて無い。
でも・・・私はこうして懸命に彼の存在を追っている。
彼がいなくなる――
たったそれだけのフレーズが、私の心を掻き乱す。
出会ってから、たったの一ヶ月なのに。
あの野良猫がいなくなったときにだって、こんな不安は感じなかったのに。
大丈夫、帰ってくる――どうしてそんな風に思えないのだろう?
彼が夜、黙ってスルリとこの家から抜け出るようにして消えてしまったから?
もしかしたら、そんなことは彼にとっては至極普通の事なのかもしれない。
長い散歩に出たのかもしれない・・・。
そう考えたら、別の寂しさが私の心を過ぎった。
次の居場所が決まったのかもしれない・・・。
悲しみが心の底から首を擡げてきた。
私は探す―― 一ヶ月の間で身に染み込ませた、彼の気配を、その存在を。
耳を澄まして、音を集めて・・・・。
遠くで、探していた声が、聞こえた。
覚えのある鈴の音も、聞こえた。
待ち侘びた足音がこちらへ近づいてきた。
私は彼の名を呼んだ。
思ったよりも大きな声が出て、自分でも吃驚した。
そしてモーツァルトと共に駆け出した。
朝風にのって、彼の香りが私の鼻腔をくすぐった。
途中から彼もその歩を早めた。
彼との距離が近くなる。
彼の額に巻いたバンダナが風にはためく音がした。
彼は、戻ってきた。
心を渦巻いていた心配と不安が、安堵と喜びに瞬時にして変わった。
朝焼けの匂いがまだ漂う中に、彼の存在が広がった。
そして、私が伸ばした手が、彼の手に触れた。
こんな風に彼の手をとったのは、始めてかもしれない。
彼の少し吃驚したような、困惑したような気配がそこから伝わってきた。
そんな彼の表情も、少し熱く感じた彼の手の感触も、ずっと覚えていようと私は思った。
そして私の口からついで出た言葉。
―― おかえりなさい ――
彼は目を瞬かせた。
そして彼のますます困った気配が伝わってきた。
あぁ、ここが彼の居場所になればいいと思う。
彼が帰ってくる処に。
彼が私に、何の躊躇いもなく
―― ただいま ――
そう、言えるような場所になればいい。
そして、その言葉を聞ける存在に、私はなりたい・・・。
朝食の後、アルコールに浸された身体を休めるため、士度はベッドに身を投げた。
そして枕を引き寄せたそのとき、微かに香った彼の女(ひと)の匂い。
その口元が僅かに綻んだことを、
彼の手に触れたその指を機嫌よく弦に走らせている乙女は、知る由もなかった。
Fin.
MISSA様から頂いた“a nexus to you”の素敵挿絵![]() に触発されて突発的に書いてしまいました、
に触発されて突発的に書いてしまいました、
マドカ視点のサイド・petit・ストーリーでした。あの絵の表情の奥にある二人の心を書いてみたいような気が凄くして・・・。
単品でもいけるとは思いますが、nexus〜を読まれてからの方が分かりやすいと思います。
野良猫と士度の違うところは、どこでしょう?
◆ブラウザを閉じてお戻り下さい◆