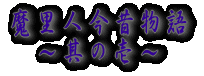
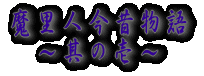
女が目覚めると、
青年―そう呼ばれる歳になったばかりの彼は、暗がりの中、隙間風に微かに揺れる蝋燭の炎を見つめていた。
彼女から少し離れたところで、胡坐をかいて、静かに。
女は――
一族の巫女だった。
神に仕えて神楽や祈祷を行い、僅かながらだが未来を視ることができた。
男は――
長の息子で、若輩ながら里一の戦士だった。
一族伝来の技を今よりもさらに歳若いときに殆ど習得し、動物と自然に誰よりも愛されている者だった。
女は微かに軋む身体を起こし、立ち上がろうとした。そしてその時になって初めて、自分の身体に外套が掛けられているのに気がついた。
予想し得なかった、目の前にいる者からの小さな心遣いにその艶めいた口元が僅かに綻んだ。
その外套を肩にかけ、女はゆっくりと立ち上がり、数歩離れた男に近づく。
彼は――微動だにせず、橙色の灯りから目を離す素振りすら見せなかった。
外から静かに進入してくる冷たい空気が互いの熱を喰らい尽くそうとしている最中、最初に口を開いたのは女の方だった。
「・・・・・初めての女が、自分よりも七つも年上だと、やっぱり興醒めですか?」
――士度様・・・・・
彼の人の名を呼んだ女の声にも、男は黙ったままだった。
静寂がただ、その場を支配する――女の唇から溜息が吐き出されようとした瞬間、男がやっと言の葉を紡いだ。
「・・・・お前だって、二十歳を幾つも過ぎてねぇだろ。」
間が悪い彼なりの不器用な言葉に、何故だか女は心を揺さぶられた。
「そうですけどね・・・」
その歳に似合わず妙に落ち着いた雰囲気を漂わす彼女が揺れる心を抱えながらもう一歩、彼に近づくと、男から再び言葉が漏れた。
「・・・・悪かったな。儀式とはいえ、酷いことをした・・・・。」
――
お前、痛そうだったし・・・もっと慣れてるかと思ってた・・・・。
その言葉に、女の眼は見開かれ、そして再び唇が弧を描く。あぁ、彼は――屈強の戦士でありながら、こうやって、どこまでも・・・・。
女は冷たい木の床に両膝をつき、大人のそれではあるが、どこかまだ少し幼さを孕んでいるその広い背中に頬を寄せた。
彼女の唐突な動作に、男は少し驚いたようだったが、拒絶はしなかった。
「いいえ・・・あなたは・・・」
――優しかった。
唇がその逞しい躯に、言葉を伝えた。
「それに、痛いのはあたりまえです・・・私だって、初めてでしたもの。」
「――!?」
男は急に弾かれたように顔を上げて振り向き、思わず女の顔を見つめた。
彼女は穏やかに微笑んでいた。
「なのに・・・・儀式だからって、巫女だからって・・・よく知らねぇ男と褥を共にしたのか、お前は!?」
――長がそうしろって、命令したのかよ!
彼にしては珍しく、声を荒げ怒気を含んだ口調だった。
女はもう一度ゆったりと微笑する。
「御命令もありましたけれど・・・・私自身が、選んだことなのです。私の、望みでもありました・・・・お許しください・・・・・」
――
それに私は、あなたが思っている以上に、あなたのことを存じ上げておりますよ・・・・士度様。
そう、巫女である自分よりも遥かに、自然とそれを司る神々から寵愛を受けている彼がとても羨ましく、そして光り輝いて見えていた。
気がつけばいつも自分の眼は、彼の人を追っていた。その視線が返されることがないということも、自分が一番よく理解していた。
「・・・・何よりも素晴らしい、冥土の土産になりましたわ。」
彼女の言葉に男は眉を寄せた。
「・・・・何言ってんだ、テメェは。」
「未来が、“視える”のですよ・・・・士度様。」
近い、未来が。
血溜まりの中、最初で最後の男の腕に抱かれながら事切れる自分の姿が――
女はその事を男に言わなかった。
その未来が変わってしまうことが何よりも恐ろしかった。
「・・・・お前、死ぬのか?」
男は再び女に背を向けた。
「はい、きっと、近い将来・・・。」
当たり前のように、女は答える。それが、私の運命。
「・・・こんなご時世だ。俺もきっと、長くはない。」
自嘲を含んだその声に呼応するかのように、彼女は細い腕を彼の躯に回した。
「あなたは――
一族の誰よりも辛く、重く、苦しい運命を背負うこととなるでしょう・・・・」
憂いを含んだ声だった。男の片側の口角が皮肉気に上がった。
「上等だ・・・」
「――けれど・・・・その先に、“光”と“闇”が視えます。どちらも、きっと、とても穏やかで優しい・・・・それ以上は視えないのです。
あなたの未来は、強大過ぎて。」
「・・・・呑まれて、消えるのかもしれねぇな。その“光”と“闇”の中に。」
「“光”はきっと・・・あなた自身ですよ。」
女は後ろから男を抱きしめるように、その腕に力を籠めた。
「・・・・錯覚だ。」
巫女の言葉をいともたやすく否定する男に、彼女は苦笑する。
「私は、その“闇”が羨ましい・・・」
再び沈黙の帳が降りた。
やがて男は背中に、熱い雫を感じた。
彼は躊躇いながらも、彼女の手をソッと握ってやった。
――生きて・・・・。
女の掠れた声がした。
――
どんなに過酷な刻が貴方を苛んでも・・・お願い、生きて・・・・。
そしたらいつか必ずあなたは“永遠”を手に入れるはずだから・・・そしてどうか、幸せになってください・・・・。
それが私の残された、唯一の願い。
男の戸惑いが繋いだ手から感じられた。
「・・・・もっとマシな願いは他にねぇのかよ。」
――どうせ願うなら、自分の為に願えよ・・・。
彼の半ば呆れたような、憂いを含んだような声に、彼女の涙は流れることを止めた。
彼が紡ぐ言の葉は、女にとって一言一句神聖なものであった。
彼の言葉に従うように、彼女はゆっくりと願いを口にした。
「・・・できるならもう一度、口づけを。そして、あなたの遠くに、少しでもいいから私を、刻み付けておいて・・・・」
そして細い吐息に灯りが揺れる。
その灯りも、再び動き始めた空気にやがて掻き消された。
血に塗れることが当たり前の日常で、戦士と巫女が過ごした最初で最後の夜は、紅い月が闇を照らしていた。
Fin.
士度の初めては何となくマドカではない気がしたのです・・・。