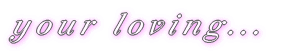
ただ一度だけ
もう二度とはない
でもそれは
誰よりも
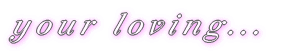
メイドAは父親の十三回忌の法要に出たかった。
メイドBは懸賞で当たった温泉旅行に思いを馳せていた。
メイドCはメイドBの温泉旅行にどうしても便乗したかった。
メイドDは死に物狂いで手に入れたロック・バンドのチケットを無駄にしたくなかった。
執事は学生時代の登山部のOB会に出席したかった。
――こんな風に、申請した休暇届の日付が重なることは珍しくない。
そして、いつもは誰か(大抵は執事とメイドAになるのだが)が気を利かせたり、我慢をしたりして、最低2人は通常業務をこなすことになるのだが――
メイドAは最近病気がちの母のことも心配だった――兄や弟、妹達も皆、集まると言う。
メイドBは今まで温泉旅行なんかしたことがなかった――いつか露天風呂に入って夜空を見上げるのが、小さい頃からの夢だった。
メイドCもしかり―― 一生に一度でいいから高級旅館に泊まってみたかった。
メイドDが目指すコンサート会場は遠く北海道――しかし数年に一度しか来日しない大物バンド。遠かろうが寒かろうが駆けつけるだけの情熱が、彼女にはあった。
執事は――そう、彼はいつもなら、年長者であり、このお屋敷の生活と秩序を守る一番の責任者であるその地位に相応しく――部下達を快く送り出してあげるのだが、今回の登山は当時彼に山と自然とは何たるかを教えてくれた恩師の引退登山――何としてでも参加して、頂上で眺めるご来光に師の今後の幸せを祈りたかった。
コックはその日、料理のコンテストがあるとかで早々に休みを申請している――自分たちが全員休むとなると、食事を作る人もいなくなる。
運転手は孫の運動会があると――よほど楽しみにしているのか、春先からシフトのカレンダーに休みを書き込んでいた。
普通のお屋敷なら、一日や二日、使用人が全員消えたってなんとかなるものだ――しかし自分たちのご主人は盲目のバイオリニスト、音羽マドカ嬢その人。
もしものことがあって屋敷の中や外で事故にあったり、世界から惜しみない賞賛を集める音色を奏でるその指に傷でも負わせることになったら――考えるだけでも恐ろしい。
「・・・・その日、モーツァルトは朝から大学病院で年に一度の検査入院になっています・・・・」
この屋敷での業務の全てが記録されている分厚い手帳を捲りながら、珍しく沈んだ声で執事が呟き、その場にいる乙女たちは大きな溜息と共に一斉に項垂れる。
外は快晴、洗濯日和の良い天気なのに、厨房脇の食堂の中だけドンヨリと曇り空だ。
その時―― 一人の青年が肩に黒猫を引っ掛けたまま、中庭から厨房へと入ってきた。勝手口からはミルクをねだる猫達の甘えるような声がハーモニーを奏でている。
「分かったから、ちょっと待ってろ・・・」
青年は冷蔵庫からミルクを取り出し、慣れた手付きで皿に注ぎ、水で少し薄め――そして、喉を鳴らしながら彼の手元を覗き込んでいる黒猫を肩に乗せたまま、ミルク皿を両手に顔を上げると――
メイドAは申し訳なさそうにこちらを見ていた―メイドBは縋るような視線を青年に送った―メイドCは心底安堵した表情で、メイドDは目を輝かせながら満面の笑みを彼に向けていた――普段は何処までも礼儀正しい使用人たちの、感情露なそんな視線を向けられ――青年はいつに無くギクリと固まる。
そして、眉間に皺を寄せていた執事が意を決したように立ち上がり――
「「「「「士度様・・・・!」」」」」
その声に、肩の上の黒猫は目を丸くしながら毛を逆立てる――使用人達から救いを求めるかの如く名を呼ばれ、青年は状況を把握できないまま冷や汗混じりに立ち尽くしていた――
外ではミルク待ちの猫達が、相変わらずニャアニャアと甘えた声を連呼していた。
![]()
「御朝食のいつものメニューのメモ書きは厨房の冷蔵庫に貼ってあります・・・・最近のお嬢様は苺ジャムがお好きで・・・・」
「お嬢様のお着替えも鏡台横のスツールの上に揃えておきました。あ、お洗濯物はいつも通りにランドリーボックスに放り込んでおいてくださいませ…!」
「お風呂に使用する薔薇のエッセンスは質を保つため浴室の戸棚の下から三番目の引き出しの中に入れておきました。御昼食と御夕食は申し訳ありませんが、外食という形になって・・・・」
「・・・・・・・・たった一日のことだ、そんなに心配しなくてもなんとかなるさ・・・・」
数日後、音羽邸玄関前――
いつもとは装いが違うメイドや執事から矢継ぎ早に出てくる言葉の数々に、士度は適当に頷きながら欠伸を噛み殺した。
エントランスの時計の針は、ようやく五時に差し掛かったばかりだ――早朝の。
コンサートとその打ち上げで昨夜遅くに帰宅した姫君は、もちろんまだ夢の中。
「お土産、買ってきますね!」 「お二人もどうか良い休日を・・・!」 「明日、帰りにモーツァルトも病院から拾って帰りますので・・・」 「朝早くから本当に申し訳ございません・・・」 「シド・・・・!タスケテヨ!!」
最後に叫んだのは執事に散歩綱を持たれていてる、病院嫌いのモーツァルトだ。朝から大学病院に置き去りにされてしまうらしい。
「・・・・楽しんで来い」
しかし、朝の気だるさに邪魔をされている士度は(昨日は彼の帰宅も仕事で深夜だった)、モーツァルトへの返答も、執事やメイドの言葉への返答とひっくるめて答えてしまった。「シド〜〜〜!!」――暴れるモーツァルトを引き摺りつつ、途中何度もお辞儀を繰り返しながら、執事とメイド達は音羽邸を後にする。
士度は彼らを見送った後――ガシガシと頭を掻きながら、先ほど執事から受け取った新聞を片手に、とりあえず厨房へと向かった。
『朝の紅茶はべノアのセイロン・ディンブラ、朝食に添える牛乳はバスチャライズド・フレッシュミルク、卵料理はスクランブル・エッグ(硬くなり過ぎないようにお願いします)、ベーコンを焼く際はピュアオリーブオイルで(焼き上げたらキッチンペーパーで余計なオイルは除いてください)、サラダの野菜はレタス以外はスライサーで細切りに、パンはバゲットかライ・ブレッド、ブラウン・ブレッド、およびローフ・ブレッド(*食パンのことです)のどれかをお好みで召し上がります(量は多くても一枚と半分程)。最近のお嬢様はストロベリージャムをエシレバターと一緒にパンにのせて召し上がるのがお好きです。ジュースはブラッディオレンジをジューサーにかけた100%のものが冷蔵庫に入れてあるので、お嬢様がご入用のときに。スープは春キャベツとパプリカのグーラッシュを今朝方作っておきましたので、暖めてお召し上がりください』
「・・・・・・・」
――とりあえず、食パンと・・・作り置きがある何とかスープだけはマドカに出せそうだ・・・・・
あと、ジャムは・・・・苺ジャムのことだよな――士度はメイドが残していった朝食用のメモ書きに頭痛を覚え、眉を顰めた――メモを握り潰してしまわないだけ、いいほうだ。彼にとって理解不能のカタカナ用語に註がついているのは不思議なことに“食パン”の件だけ。上品な奴らが使う特殊な言い回し故か、それとも自分がよっぽどの無知なのか――朝の空気が冷たい厨房で、士度は白い溜息を吐きながら、とりあえず苺ジャムを探すことにした。
――やがてジャム置き場の棚はすぐに見つかったが・・・・
beyberry、bilberry、 blackberry、 raspberry、 blueberry、 brambleberry、 buffaloberry,、checkerberry、
cloudberry、 dewberry.............................
「・・・・・・・・」
“苺=strawberry”――このくらいの方程式は士度にも理解できたが、目の前に並んでいる瓶のラベルには、所謂“似た文字”が並ぶだけ。物によっては“苺に似た”果物の写真や絵が、鮮やかにそのラベルを飾ってはいるのだが・・・・苺ではない・・・・多分。
彼は無言のまま、棚の扉を静かに閉めた――アルファベットに痛んだ目を煩わしそうに瞬かせながら。
そしてシンク下の収納を探り、小さな鍋と
「ん・・・・・・」
大分深く・・・・長く、眠っていたような気がする――コロン・・・と寝返りを打ちながら、マドカは寝起きでまだ重い身体を精一杯伸ばしてサイドテーブルに置いてある時計のボタンを押した。
<ゴゼン シチジ ヨンジュウ ゴ フン デス>
「七時・・・四十・・・五分・・・・・・・――えっ・・・・!?」
彼女は機械音が告げた音を反芻したとたん、弾かれたように飛び起きた――だって、今日は初めて――士度さんとこのお屋敷で、文字通り“二人きり”で過ごす大切な日なのに――朝寝坊という愚かな行為で貴重な時間を無駄にしてしまうなんて・・・・
「モーツァルト・・・!――ア・・・・・」
マドカは半分涙声になりながら愛犬の名前を呼んだが、しかしすぐに彼の定期健診の予定を思い出し、途方に暮れた顔をしながら手探りで慎重にベッドを降りた。
――士度さんはきっともう起きて・・・・朝ごはん、もう食べちゃったかな・・・・とにかく、早く着替えて
着替えがいつもの場所に置いてあることを確認したマドカは、急いでネグリジェを脱いでベッドへ放ると、まずはペチコートを履いてロングスカートを身に着けた――そして上の下着を手にとる・・・・今日はフロント・ホックのブラだけど――実はフロントにしろバックにしろ、マドカはこの“ホック”というものがあまり得意ではない――目が見えないとはいえ、大抵のことは一人でできるけど・・・下着のホックに関してはいつも一度は掛け違いをして、やり直す羽目になってしまうのだ。いつもはメイドさんが手早くキチンとつけてくれる下着だが、今日は時間が掛かりそうだ――マドカが手探りでホックと格闘しているとき、コンコン・・・・というノックと共に、「マドカ、起きたか?入るぞ?」――彼の声が、彼女の心を一層慌てさせた。
「あ・・・ちょ、ちょっと待ってください・・・!まだ着替えが・・・・」
そうか、悪りぃ・・・――短い謝罪の言葉と共に、少し開けられた扉は再びパタン・・・と閉じられた――そんな彼の反応にマドカは罪悪感を感じながらも、意識を再度ホックへと集中させる――しかし、慌てれば慌てるほど、小さな金具同士は全く噛み合ってくれない。
――五分後・・・・扉の外にも漏れるようなマドカの焦燥感を気の毒に思った士度は、もう一度彼女の部屋の扉をノックしながら、返事を待たずに中に入った――半分涙眼になった彼女が、恥ずかしそうに俯きながら彼に背を向けている。状況を瞬時に察した士度は、彼女の後ろから手を回して、フロント・ホックを留めてやった――そして、「次は・・・・これを着るのか?」――そう言いながらスツールに畳んで置いてあったスリップを手に取ると、遠慮がちに頷くマドカの手をとりながら、当たり前のように着替えを手伝い始めた。
――彼の少し武骨な指が器用に丁寧に、マドカのブラウスの小さなボタンを留めていく。マドカは士度の指先の動きを意識で辿りながら、一人頬を染めていた。前のボタンを留め終わると、次は袖のボタン――すでに一糸纏わぬ姿だって、見られているのに――“着替え”を手伝ってもらうことは、また別の恥ずかしさと高揚感をマドカに与えていた。肌と洋服の間を滑る彼の手――ブラウスを着せてもらうとき、髪を持ち上げるように言われその通りにしたとき刹那、彼の指が
(朝から・・・はしたないのかな・・・私・・・・)
「・・・・よし、次は・・・髪だな?」
士度はそんなマドカの内心を知ってか知らずか、彼女の少し癖のついた前髪を指先で跳ね上げる――マドカはそんな彼の声に我に還ると、震える声を無理矢理音にした。
「士度、さん・・・ごめんなさい・・・・・
――すると彼は――士度は、彼女の言葉を聞くなり目を丸くした。そして一瞬呆れたように彼女を見つめたが――やがて彼の口元は小さな微笑をつくり、その手は彼女の背を押して、鏡台の前の椅子へと導いた。
マドカは躊躇いがちに彼の様子を気にしながらも、されるがままにそっと椅子に腰掛ける。
彼は彼女の緑の黒髪に少し武骨な指を遊ばせ、黒絹の滑らかさを確かめるように戯れに、二度三度――その長い指を闇色の流れにのせた。
いつにない彼の動作を気にしながら――髪から伝わる彼の動きに翻弄されながら、マドカは士度の心内が推し量れぬまま、不安そうに瞬きをしている。
「お前なぁ・・・・」
士度は鏡台に並べてあるブラシから適当に一つ取りながら、苦笑混じりの声を出す。
「
見た目よりも柔らかな彼女の髪にブラシはゆっくりと滑る――そんな彼の言葉にマドカはピクリと肩を揺らすと、哀しそうに眉を寄せた。
「・・・・それはちょっと・・・・寂しいです・・・・」
――いえ、かなり・・・・・
――だろ・・・?
そう言いながら士度は鏡台の上にざっと目を走らせると、『寝ぐせ直し』の文字が派手に躍る霧吹きらしきモノを手に取り、彼女の髪を湿らせた。
次の言葉を求めるように、彼女は首を少し傾けながら背後を気にする素振りをみせた――彼女の髪を部分部分持ち上げながら、士度は丁寧にブラッシングを続けている。――使用人も、モーツァルトもいない一日――大好きな彼と二人きりで過ごせると単純に喜んでいたけれど、それはつまり・・・普段、メイドや執事やモーツァルトに手伝ってもらっていることを全部、全て、彼にしてもらうということ・・・・それはきっと、彼の負担になること――だから、自然に口をついて出てくる謝罪の言葉―― 一日を覆いそうな寂しさの予感に、マドカの睫に影を差す。
「・・・だからさ、お前は今日一日、何でも我侭聞いてもらえるつもりでいろよ。」
「え・・・・?」
彼の言葉に引かれるようにフワリと振り向いたマドカの前髪にも、優しくブラシはあてられる。
大きな彼が普段使わないであろう女性用のブラシを器用に扱う様は、少し意外な気持ちをマドカにもたらした。
「どうせ“遠慮すんな”って言っても・・・どうしたってお前は中に溜めちまうことがあるからな・・・・」
――“我侭” なら気持ち、楽だろう?
その言葉に、彼女は瞠目し――やがて心にゆっくりと浸透してくる喜びに頬を桃色に染めた――彼は・・・自分でも知らない私も見ていてくれている・・・?
士度はマドカの自分に対する優しさや思いやりが――時々彼女の言葉を内に押し込めているのを知っていた。
おそらくは、彼女の無意識の中で・・・“理解”という形で。
普段は、口数が少ない士度を導くかの如く明るく真っ直ぐに話す彼女だが、時折――そう、例えば仕事で長く留守をするとき――「いってらっしゃい」と柔らかに言う彼女の穏やかな瞳が、彼の気配を追うようにそのまま無言で語りかけてくる――どうか、無事に帰ってきて――早く、戻ってきてくださいね・・・――・・・・行かないで――
自分はいつも――彼女の音を成す言の葉に甘えているのだということを、士度は自覚していた。
そしていつも・・・繋いだ手を離す瞬間に心の中で深く誓う――大丈夫だ・・・この温もりを知る限り、自分はココに・・・
――そんな風に優しく、心を強く持つことを厭わない彼女に普段の自分は・・・・いったい何をしてあげているのだろう?
「我侭、ですか・・・・」
マドカが隠そうとする心の高揚はしかし、跳ねた語尾がその明るさを朝の光の煌きの中に放ち、士度は密かに目を細めた。
「それは、お願いを・・・・聞いてもらえるということですよね?」
それは彼女らしい言葉の置き換え――父親と使用人と、幼い頃からの音楽の英才教育を受け持った先生達、年上のライバル達、音楽関係者――まだ二十歳にも満たない彼女は、世間一般の同世代の女子達よりもずっと早い歳から大人社会の中で生きてきた。目が見えない分、人の心に敏感な彼女の今までの人生の中で、“我侭”という概念が発動された回数は数えるほどしかなかっただろう――そんな風に思っていた士度の予想通りの、彼女の反応。
おずおずと確認するように、しかし大きな期待を含んだマドカの言葉に、
「そうだな・・・・試しに何でも言ってみろよ?」
――俺にできる範囲のことなら今日は何でも・・・・叶えてやるぜ?
マドカの桜色の唇から思わず漏れたのは、愛らしい喜びの声。
何でも叶えてやる・・・・お前が望むことならば――本当はそんなこと、彼女の笑顔を見る度に心が無意識に運んでくる想いだけど。
それを自分が言葉にする間がないくらい、普段の彼女は満ち足りた微笑を湛え、彼女の周りには彼女を支える人達が数多にいるのだ。
――俺は
誰よりも自分に安らぎをもたらしてくれる彼女に、自分は何ができるのだろう・・・・――それが分からぬまま、せめて今日は日常生活の中で彼女に不自由がないように努めようと士度は思った。そうすることによってもしかしたら――自分が彼女にしてやれること、彼女が自分に望むことが見えてくるのではないかと思って。
「よし・・・こんなものか・・・・」
士度は彼女の髪の表面を確かめるように撫でながら、カタン・・・とブラシを鏡台の上に置いた。
彼の指先が髪から離れていく名残惜しさが、マドカの心を撫であげる――人の体温は髪をも伝い肌に伝えるものだと、マドカはその時初めて知った。
そう、彼に髪を触れられるのは、とても心地よい――まるで優しい歌を聴くように。
彼女は左手で、一度確かめるように自分の髪に触れた後、士度の手のぬくもりがまだ残るブラシを手に取った。
「マドカ・・・・?」
仕上がりが気に入らなかったのだろうか・・・――そんな憂慮を、名を呼ぶ声に滲ます士度の気持ちに気づかぬまま、マドカは少し恥ずかしそうにブラシを彼に差し出した。
「最初のお願い・・・・・いいですか・・・?」
頬を染め、僅かに俯きながら小さく尋ねてきた彼女の手からブラシを受け取りながら、士度はその“お願い”の内容を聞く前に反射的に頷いていた――
「これは・・・ナイフとフォークで食べるんですか?それともお箸で・・・」
「・・・・そのまま持ち上げ齧り付くんだよ。でも嫌なら匙でもなんでも出す・・・・」
「いえ!士度さんが仰った通りに食べてみます・・・!」
コンロの前で鍋をかき回す士度の言葉を半ば遮りながら、マドカは目玉焼きがのったトーストを慎重に持ち上げると、小さな口を精一杯開けながら、ハムッ・・・と(彼女にしては)勢い良く噛み付いた。そして口にあったのか、彼女は目を細めながらトーストを賞味している――途中、「あ、ベーコンもついているんですね・・・!」―と声を弾ませたりしながら。
弾む彼女の心とともに、背中に下ろしてある綺麗に編まれた三つ編みも揺れる――マドカの最初の“お願い”は、士度に髪を編んでもらうことだった。
草鞋や竹細工なら編んだことあるが、女の髪なんか編んだことねぇよ・・・――そう言いながらブラシ片手に途方に暮れる士度の返事に、マドカは密かに安堵した。意外にもブラシを慣れた風に扱う士度の様子に、もしや・・・・といらぬ不安が心を掠めていたからだ。
「草鞋を編む感覚でいいですから・・・お願いできますか・・・?」
そうして士度は困った顔をしながらも、再びブラシをマドカの髪に当てながら髪を編み始めた――士度さんは・・・ブラシを使うのがとても上手ですね?――マドカは小さな嫉妬心を表に出さぬよう、何でもないように士度に訊いてみた。探るようで恥ずかしいけれど、小さなことでも気になってしまうのがまだ初々しい乙女心。
最初は少し戸惑いがちに動く彼の指からはしかし、動揺は感じられなかった――・・・あ?あぁ・・・ガキの頃、薫流のさ・・・――士度は半ばまで編んだ髪を一度解いて、もう一度確かめるようにしながら編みなおしていく。
――ほら、祭りや寄り合いで四木族の長らが集まったとき、アイツの面倒を見るのはいつも俺や亜紋や劉邦でよ・・・。薫流の髪を梳くのは俺の役目だったんだ・・・亜紋は必要以上に女子供には近づかねぇし、劉邦が梳くとどうしても乱暴になるって言ってさ・・・・
昔の話になると時折、ほんの少し饒舌になる彼がいる――いつもより静かな屋敷の中で朝日と同じ暖かさのその声を独り占めにしているような気がして、マドカは小さく微笑した。
「だから俺が・・・・でもよ、薫流のヤツ、ガキのくせして “早く梳くと髪が痛む ” だの “もっと深く櫛をあてろ” だの “痛い、ヘタクソ” だの色々五月蝿くてよ・・・それにアイツの髪は長くて量が多いだろ?何回かやってれば嫌でもいらねーコツを覚えるさ・・・・」
――でも今日・・・役に立ったみてぇだから、良かったのかもな?
最後に、鏡台の上で目に付いたウサギのファーがついたゴムで彼女の髪を結び、士度が鏡を見ると――編まれたばかりの三つ編みにそっと触れながら幸せそうに微笑む彼女が、そこにいた。
「ジャムって・・・・ようは果実を煮たヤツだよな?・・・・これでいいのか?」
マドカがベーコンエッグトーストを美味しく食べ終え、サラダを突付いていた頃、皿に新たに滑り込んできた半切のトーストから香る甘酸っぱい匂いが厨房脇の食堂を満たした。
「あ・・・ジャムが・・・温かい・・・・」
トーストに口をつけたマドカは思わず目を丸くした。苺本来の控えめな甘みと仄かなレモンの香りがまだ残る熱の中で踊っている――マドカが不思議そうに士度の方に意識を向けると、彼は彼女に背を向ながらティーポットにお湯を注いでいるようだった。
「誰かが置いていったメモにお前が苺のジャムが好きとかなんとか書いてあったんだが・・・・見当たらなくってよ。だから裏庭に植えおいた苺を適当に摘んで・・・・」
「作って・・・くれたんですか?ジャム・・・・」 ――私の為に・・・・?
――ありがとう、ございます・・・・
マドカの心を彩るのは、見えないジャムの色と同じくらい鮮やかな喜びの色。
「昔、里の女達が似たようなのを作っていたの思い出してよ、
パクリ――士度がポットを片手に首だけを彼女の方へ向けたときには、マドカは既に最後の一口に齧りついているところだった。
そして上目遣いに恥ずかしそうに訊いてくる。
「あの、おかわり・・・いいですか?」
「あ、あぁ・・・待ってろ、今、鍋から出して・・・」
まだ熱いポットを片手に持ちながら、士度は手元にあったシュガーポットも手にとった。すると、その影から出てきたのは――探していた、苺ジャムの瓶。
「・・・・・・・」
士度は危うくシュガーポットを取り落とすところだった――
「士度さんが作ってくれた朝ご飯・・・どれもとっても美味しいです!」
――でも、男の人がお料理上手だと、ちょっと妬けちゃうかな・・・?
両手が塞がっていることと、彼女の無邪気な声を言い訳にして、士度はそのジャムの瓶を見なかったことにした。
マドカを起こしに行くまで三時間近く――ジャムの下ごしらえをしたり、厨房にある数多の食器やオイルの中からどれを使えばいいのか悩んだり、棚の一角を占める多すぎる紅茶缶の中から目的のものを探し出しだすのに苦労したり・・・・・ああ、結局バターはどれがどれだか分からなかったっけ――慣れない作業に振り回された心労が、眼下で輝いて見えるジャムの瓶のせいで一気に押し寄せてきた気がしたが――士度はそれすらも無理矢理気づかない振りをした。
――ジャム、今度は一緒に作りましょうね?
先程彼女が鏡台の前で見せた不安げな表情は今は欠片も見えない――「そう、だな・・・・」
淹れ慣れない紅茶を満たしたティーカップを手に持たせてやると、マドカはそれも美味しいと言ってゆっくりと味わう――その姿に士度が安堵の眼差しを向けると、朝の心地よい風が勝手口を通って二人の髪を揺らした。
小さな鍋の中をジャムを半切トーストの上に乗せ、士度は漸くマドカの隣に座った――今日は何をしましょうか・・・?――三つ編みを揺らしながら小首を傾げてくるマドカに相槌を打ちながら、士度はやっと朝の一口を食することを許された。
二人だけの食堂を、朝の光はそのささやかな幸せを包むかのように穏やかに照らし出し、士度を悩ませたメモを風に乗せて何処かへ攫っていった――
![]()
「とても良い香りがします・・・これは?」
「カルディ・・ナル・・・ドゥ・・リシュ・・・リュー?深い紫色だな・・・最古の紫薔薇って書いてあるぞ。」
「へぇ・・・・あら、こっちはとても濃くて・・・甘い匂いが・・・」
「バリエ・・・ガータ・・・ディポ・・・ローニア・・・?白と、深い紅の縞模様だ・・・・なんか舌噛みそうな名前ばかりだな、薔薇って植物はよ・・・」
――あら、でも香りを一番楽しめる植物だと私は思うわ?
マドカはそう言いながら目を細めると、満足そうに薔薇の香りを吸い込んだ。士度はそんな彼女の言葉に苦笑しながら、小さな溜息混じりに自分には場違いであろうその場所をもう一度ぐるりと見渡してみる――この世にある色の全てを鮮やかに敷き詰めたかのような花の絨毯の中に、自分たちは立っている。
しかし次の囲いに目を落とすと――宴、織部、神楽、銀世界、楽園、胡蝶、琴音、式部、緋扇、・・・・――薔薇の前の札には見慣れた漢字が並んでおり、士度は密かに安堵した。そして何気なく目に付いたのは――大輪の花々の中でひっそりと、小さく――しかし愛らしい白と薄桃色の花弁を薔薇にしては珍しく空に向けて広げている優しげで――どこか力強さを醸し出している、見慣れぬ花。そのプレートには美しく 「―姫―」の字が舞っている。
「・・・・・・・」
彼の視線は自然とマドカの方へと流れていった。
今日はモーツァルトがいないのでマドカは久し振りに白い杖を手にした。
彼が隣にいるのに甘えていつもより少しヒールの高い靴を履いてみた。
今日は移動の間はずっと・・・左手を彼の右腕に添えていられるので――タクシーではなく、電車で目的地まで行ってみたいとねだってみた。
お昼時、遅い朝食をたっぷり食べたのであまりお腹が空いていないと言ったら、士度は果物屋で林檎を一つ買って・・・素手で綺麗に二つに割ると、半分をマドカに渡し、二人は通り掛かりの公園のベンチに腰掛け、それを食べた。
(あの林檎も・・・・蜜が沢山入っていて、美味しかったわ・・・)
それに、皮付きの林檎をそのまま、しかも公園のベンチで食べるなんて初めての経験だったので少しドキドキしたけれど・・・
(でも士度さんは、普通だって言っていたし・・・・)
太陽の下で、赤い果実にシャクリと歯を立てるのは、案外気持ちよかったりしたのだ。
そして二人は坂道を少し登って――マドカが以前から行きたがっていたバラ園へとやって来て今に至り、もう既にかれこれ二時間近く、薔薇巡りをしている。
(またああやって・・・士度さん、林檎を分けてくれるかしら・・・?)
不意に昼間のことを思い出し、マドカは薔薇に顔を寄せながら麗らかに目を細めた。
「マドカは本当に薔薇が・・・・好きなんだな。」
――俺は
そう言いながら士度はマドカの頭をクシャリと撫でると、――次は日本の薔薇だってよ、舌、噛まずに済みそうだ――そう苦笑しながら彼女の手を引いて先へと促した――マドカの頬が咲き誇る花々と同じ色になったことに、彼は気づかなかった。
「えぇ・・・好きです、とても・・・・」
――好きなんです・・・・
マドカは彼の右手をそっと握り返した。
――夕霧、だってよ、ほら・・・
そのまま士度に導かれたマドカの手は、豊かな香りで挨拶をする薔薇の花弁に触れる――色は・・・白と薄桃だな・・・外側の花弁の端だけ・・・濃い紅が・・・・
時折、迷うように言葉を選ぶ士度の声が心地よかった。
髪や指に触れる彼の大きな手の温もりに心が高揚した。
嫌な素振りを微塵も見せず、慣れない花の姿を自分に伝えてくれる優しさに胸が焦がれた。
――そして彼が傍にいる――その事実と存在が、どうしようもなく愛しくて――
薔薇の芳しい香りに包まれながら、マドカは幸せそうに口元を綻ばせる。
そんな彼女の姿に自然、士度の気持ちも和いでゆく――今、彼女の心の瞳を彩り、笑顔を与えているこの美しい薔薇苑に、心密かに感謝をしたりしながら。
彼女の愛のベクトルが向く方向を、士度は身を囲む薔薇の香りに惑わされたかのように、最後まで的を外したままだった――
(あの子・・・長い黒髪の子。どこかで見たことあるなぁ・・・・盲目の・・・誰だっけ?)
(一緒に座っている人、ちょっと・・・カッコイイよね?彼氏かな?)
(そう?歳、少し離れてるみたいだし・・・・雰囲気もなんとなく、保護者じゃない?
「―――!!」
マドカはもう少しで紅茶のカップを取り落とすところだった―― 一方士度は、テーブルの上から懸命に話しかけてくるスズメに気をとられ、そんなマドカの様子に気づかない。
――薔薇を心行くまで堪能し、マドカの足も少し疲れて来た頃に入った小洒落たオープン・カフェで、世界に名立たる神の耳に飛び込んできたこんなヒソヒソ話。
いつもよりも彼の近くを歩いて、電車にも乗って、少し長めのお散歩をして・・・・マドカにとっては素敵なデートのつもりで士度と一緒に楽しんでいた矢先に、外の人からのこんな台詞。
――保護者・・・?この杖があるからかしら・・・・
マドカは目が見えない自分を久し振りに、少し寂しく思った。
並んで歩く自分達は・・・恋人同士のはずなのに。
道行く人達から見れば・・・私の隣にいる彼は、“好きだから傍にいる”のではなくて“心配だから傍にいる”――そんな風に見えてしまうのだろうか?
「紅茶のシフォンケーキでございます」
ウェイターの声に、マドカは気も漫ろに小さく頷く。
――歳が離れているから・・・?四つの年の差ってそんなに大きいのかしら?それとも私が幼く見えるのかな・・・士度さんが大人びているのかな・・・
今まであまり気にしなかった彼との歳の違いが、急にマドカに重く圧し掛かってきた。
――それに・・・・
何より、大好きな彼と恋人同士ではないと思われていることがマドカにとって大きなショックであった。たとえそれがほんの一部の人の見解に過ぎないことだとしても――薔薇の香りと同じくらい鮮やかな恋心を満喫していた彼女にとっては大問題。
――でも・・・手を繋いだり、一緒にお茶をするだけでは、恋人同士に見えないなんて・・・どうすれば・・・・
――試しに何でも言ってみろよ――
彼女の脳裏に不意に響いたのは、今朝方の彼の声。
(そうだわ・・・今日は士度さん、お願い事聞いてくれるって・・・)
ふとマドカの脳裏に浮かんだのは、恋人達のワン・シーン。
彼とお庭やお部屋で交わす――優しいキス。
(でも・・・・)
外の――しかも人気があるところで、普段の彼はそんなことをしないし、マドカも今までねだったことがない。しかしながら、女友達からときどき聞く恋愛話では――公園で、デート・スポットで、そして映画のシーンの中でも…外で
シフォンケーキを口に運びながら、マドカはチラリと士度の様子を伺った。
「?」
どうした?――士度からのそんな視線に、マドカは恥ずかしそうに俯き、ケーキを咀嚼する。
(だって私達だって、彼氏彼女だもの…)
それは他人様からのほんの些細な噂話だったのだが、大好きな彼との二人きりの一日を楽しんでいたマドカの乙女心に大きな亀裂を走らせたのは確かなこと。
――それに士度さん、今日は我侭聞いてくれるって言ってたし…
マドカはもう一度、士度の様子を伺った。
――穏やかな視線が彼女を包む。
「…どうした、少し疲れたのか?」
そして彼女を思いやる、憂慮の声。
――その音色に彼女の欲求は高まり…
「いえ・・・あの・・・士度さん、お願い、しても・・・いいですか?」
きっとこれはささやかな我侭だ。
普段の彼なら恐らく、きっと、自発的にはしてくれないから。
少しだけ、ほんの一瞬だけ、自分達の絆の優越感に浸ってみたい――愛されているのだという幸せを誰かに伝えたい――あの、刹那の触れ合いで。
「・・・!あ、あぁ・・・言ってみろよ。」
士度は一瞬、僅かに身構えながらも返事をする。
マドカは俯き、真っ赤になりながらも、懸命に声を絞り出した――
「あの・・・・一瞬でいいですから・・・・キ・・・・」
「っと・・・マドカ――」
――ついてるぞ?
口元に――そう言うと、士度は徐に腰を少しだけ上げ、彼女の口の端に飾りのようについていた白いクリームを自分の右手の人差し指で拭いとり――そして指についたそのクリームを、何の躊躇いも無くペロリと舐めあげた。
「・・・・これ、少し甘過ぎやしねぇか?」
「・・・・・・」
――前言撤回、やっぱり彼氏だわ――
・・・・そんな羨ましそうな声が遠くから、現か幻か、マドカの耳に木霊した。
そしてマドカの心の中で渦巻いていた靄が、嘘のように晴れていく――
――相変わらずこーゆーのが好きだよなぁ・・・お前は。
「・・・・丁度いいんです。」
士度の少し呆れたような声に重ねるようにして、マドカはポツリと呟いた。
「このくらい、甘い方が丁度いいんです・・・・」
士度が慣れぬ甘さに僅かに顔を顰めながら彼女の方を見やると――
先程まで顔を朱に染めていた彼女が、今は穏やかな木漏れ日のような笑顔でそこにいた。
「・・・・そう・・・なのか・・・・」
やっぱり、女って分からねぇ・・・――沈んだり、浮上したり、急に難しい顔をしたり、微笑んだり・・・
女にはきっと、男には計り知れない複雑怪奇な心の空模様があるのだろう――
いつもは少し大人びている彼女の、なんとなく歳相応な表情の変化を好ましく思いながら、士度は珈琲に口をつけた。
「・・・・で、姫さんのお望みは?」
「あ・・・・」
望んでいた、少し見栄っ張りのキスよりも甘い喜びを貰ったばかりのマドカは、見えない瞳を白黒させた。
「・・・・?」
それから暫く、彼女は次の我侭を考え出すのに大層苦労した。
士度は珈琲がすっかり冷めてしまうまで、彼女の揺蕩う姿を飽く事無く見つめていた。