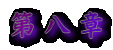
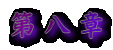
![]()
![]()
「………………」 一人少女がその細く白い裸体を惜しげもなく晒し、ベッドの中央にペタリと座り込んだまま無表情に天を仰いでいた。 よく磨かれている天窓から見えるのは、雲ひとつ無い夜空に浮かび皓皓と輝く 「………………」 まっすぐに長い亜麻色の髪の少女が常日頃被っている兎帽とお気に入りの丈の長いケープ型のマントは、豪奢ではないが洗練された調度品が置かれているローレライ号の客室のソファの上に、無造作に投げ置かれている。 夜空に何を思うのか、ただ見上げているだけの彼女がその姿勢のまま数度瞬きをしたそのとき、客室の扉が静かに開いた。 「………何か服を着ろ、薫流。」 重そうな陶器の水差しをもった劉邦は部屋に入るなり飛び込んできた幼馴染の肢体に思わず眉を顰め彼女のマントを投げかけたが、飛んできたマントを薫流はそんな彼の心情など頓着せずに無造作に形だけ羽織り、涼しげな視線を褐色の肌の男に送った。 「湯を貰ってきたのか。お前にしては気がきくな。」 「………具合はどうだ。」 湯の入った水差しをサイドチェストに置きながら訊いてきた劉邦の言葉に、薫流の艶めいた唇が小さく笑う。 「お前の方こそ、どんな具合だったのだ?」 初めて抱いた、私の感触は……―― 「…………………」 両手をベッドの上につき猫のようにしなやかな姿勢をとりながら紡がれた薫流の蟲惑的なが声が劉邦の耳を犯した。 彼は薄灰色の目で無表情に彼女を見つめた――大きな瞳が問いかけるように見つけてくる――華奢な躰にところどころ紅く咲いている情事の痕が羽織っている外衣の隙間からチラリチラリと覗き、劉邦の眼にそれはやけに扇情的に映った。 そう、初めて抱いた――士度が拾ってきた 「薫流………」 厭じゃなかったのか……?――視線を戻し盥にお湯を注ぎながら低く呟いた劉邦に、薫流は少し不思議そうな顔を返した。 「―――?別に……。昨今お前は、私の“婚約者”になったではないか……」 そんな我らが身体を重ねることに、何の不思議があるのだ……?―― 「………………」 いっそ無邪気なまでな薫流の言葉に、劉邦は手にしていた手拭を絞るまでもなく盥の中に置き去りにした――そして目を瞬かせる薫流の小さな顔にその厳つい手をそっと寄せる。 「――劉邦?」 「士度が……心配していたぞ……」 幼馴染のその言葉に、薫流がもう一度瞬きをした―― 「やはり、な……私が“力”を使えば毎度のことなのに、 仕方のない奴だな―― 「………………」 薫流の柔らかな唇が苦笑するように弧を描いた―― その音色に、嫉妬や未練の旋律が含まれていなかったことに、劉邦は人知れず安堵した――彼女をトーンフェーダー嬢から引き離したとき、薫流視線は刹那、トーンフェーダー嬢の様子を心配していた士度の方へと向けられた。そうしてからようやく、劉邦の腕のなかで身体の力を抜いた――それが安意故か諦念故かはその時の劉邦には測り得なかった。 もしかすると薫流はまだ――士度に対して思慕以上の念を持っているのではないか――そんな焦燥感が今まで劉邦のまわりを渦巻いていたのも偽れない事実だった。 士度は幼馴染で、自分が心を許せる数少ない親友だ――こう面と向かって言うと“らしくない”と苦笑されるだろうが、 「薫流……」 「――?どうした?」 自分がこうしてようやく想い人の手を掴むことができた今も、 ――士度はそれを……手繰り寄せられないままでいる。誰よりも勇敢な男が、今自分が最も欲しているモノを手に入れることに罪と戸惑いを感じている――劉邦にはそれがもどかしくもあったが、自分たちが士度に対して今できることと言ったら、“見守る”ことだけだということも、劉邦は頭の奥で理解していた。 「劉邦――?」 「……………」 婚約者に手を取られた薫流はそのまま再びベッドへと沈められた――鞣革のベストを素肌に羽織っただけの褐色の逞しい上半身が、薫流の細い躰に少し性急に圧し掛かってきた。 首筋に彼の厚い舌を感じながら、薫流は無表情にその瞳を瞬かせた。 「湯が、冷める――」 「また取りにいくさ………」 「―――ァ………ッ」 「薫流………」 劉邦は既に快楽を知っている彼女の円やかな乳房をその硬い指先で愛撫しながら幼馴染の唇を唐突に奪うことで、彼女の苦笑交じりの声を聞き流した――劉邦には士度と同様に、薫流の奔放な言動やその真っ直ぐな視線に平素から甘い面があり、同じ幼馴染の彼女には士度以上に尻に敷かれている自覚もあったが――やはり褥の中だけは、その主導権を譲れない――ふと目を開けてみると、いつもは高潔さすら感じるその小顔が、今は口腔をまさぐられる度に、胸の上で指が這う度に――仄かに桃色に染まり、彼女の頭上で押さえつけてある左手も彼女の細い躰とともに、劉邦の舌と指先に翻弄されながら戦慄くようにピクリピクリと震えていた。 あぁ、この 「――!?劉邦ッ……ま、だ……ア!!」 お前の狭い花奥に入るときの、この声も―― 「アッ……!!い……ァ……!!りゅう……ほ……激し……ッ!!」 「薫流……ッ…」 ゼンブ、オレノモノダ―― 己の存在を知らしめるかのように、劉邦は薫流のまだ幼さが残る躰に自らを激しく叩きつけた――先に放った己の残滓が彼女の最奥から掻き出され、白く卑猥な泡と音で、二人の視覚と聴覚を犯す――劉邦は薫流が泣き言に近い喘ぎ声を洩らすのも構わず、その白い痩躯に赤い花を噛みつくように咲かせ、熱く火照った彼女の耳を舌で嬲りながらその耳元で低く呟いた―― 「薫流……好きだぜ……」 「……………」 言葉は返ってこなかったが――その愛撫に震えながら、薫流の口角が緩く儚げに上がったような気がした。 劉邦には、今はそれだけで十分だった――彼女のその微笑みとよく似たものを口元に湛えながら、彼は自身を許婚の躰により深く沈めた。 ――そうして上がる愛らしい悲鳴も、悦楽に歪む貌も、濡れそぼる四肢も、淫らに揺れる躰も――全てを食らいつくすかのように、劉邦は薫流に溺れた。ようやく手に入れた、誇り高き想い人に。 「………………」 身体を揺さぶられながらふと見上げた天窓越しに見える月は、今は曇って見えている――身の内はこんなにも熱いのに、今自分を征服している褐色の躯は直に熱を伝えてくるのに―― どうしてだろう――今宵、 冷たく映る……―― 「………………」 内側とはいえ海風の影響かやはり少し色が濃くなってしまった木製の扉のすぐ上に、斜め構えられた天窓がある。澄んだ夜空と半月が奇麗に映るのも、ローレライ号の掃除当番が真面目に任をこなしている証拠だ。そしてなにより―― 鉄柵が、この空にはない。 月は無機質な縞模様に捕らわれず、天に自由な光を放っている―― 「…………………」 同じベッドが二台並べられた、広くもなく狭くもない二人部屋の片隅から、サファイアのように深く碧い眼が涼しげに輝く月を見つめていた―― 彼は椅子に座るでもなく、薄い毛布を肩に掛け、ブーツを脱ぎ棄て素足のまま直接床に腰を下ろしていた――日に焼けることを知らぬが如くの白い肌の上に流れる、その白に限りなく近い銀色の長く伸ばされた髪が、時折月灯りを反射して煌いていた。 ただ、その銀髪の奥にある碧眼は月に視線を固定しながらも、その蒼に映る夜の闇と月の白の挟間にある――どこか遠くに憂える思考の手を伸ばしているかのようだった。 「少し落ち着いたか?」 「――あぁ……。すまない……」 声がした方へ顔を上げると、その瞳の色以外は自分と寸部も変わらぬ姿をした双子の弟が薬湯香る琺瑯の そんな兄の様子を見て、ロートのルビーのように凛々しく澄んだ紅い瞳が刹那優しく瞬いた――その常人とはかけ離れた燃えるような瞳の色が髪と肌の色と相まって、そして常日頃あまり微笑まぬ性格も伴い――ロートはシリウスのメンバーの中でも断トツに冷淡な部類に入るといつか言ったのは笑師だっただろうか。 しかし近しい者から見ればロートの表情や思考の機微は、希薄ながらもとても素直でわかりやすいものだとブラウは思っているのだが――その微妙な変化を理解できるものは、シリウスの中でもごくわずかな者たちだけだった。 ロートは先程まで兄の視線が向いていた方へ眼を移した――海の青でも水の青でもない色が光の白に混ざった、黄金色の輝きを射した半月が、広い夜空に君臨していた。 「月を……あぁ、ここには……」 遮るものが、ないな……―― ――外見はその碧と紅の眼以外は変わるところがまるで無いのに、お前たちの性格はまったく違うのだな―― これも昔から――そして物心ついてからは他人から富みによく言われる台詞。 しかし自分たちはこうやって――つまりのところ、表現方法は違えど、その想いの行きつく先は同じなのだ。 そして自分は――そんな 「そうなんだ……この位置から見る月は―― そうか―― ブラウの言葉にそう短く相槌をうったあと、ロートも彼の隣に腰を下ろし天窓を見上げた。いつになく明るい月夜が二人の視線を出迎えた。 「……………」 「昔は毎晩――こうやって並んで、一緒に夜空を見上げていたな……」 「――木の床じゃなく、石の床だった。柵が邪魔してたから――こんなに奇麗には見えなかった……」 それに、毎晩じゃなかった……―― 「そうだな……帰れない夜や、お前が帰ってこない夜は……不安でしかたがなかったよ……」 「……………」 両手で持った杯に視線を落としながらのブラウの言葉に、ロートの沈黙が同じ想いを伝えてきた。 チラリと弟の方へ視線を流すと、彼はまだ月を見ていた――月灯のなか燈された生まれたての炎のような紅眼――彼の逞しい肩をサラリと流れる自分と同じ銀髪や、闇に映える白い肌も――自分よりもずっと確かに美しく、この世に存在しているかのように思われた。 幼い頃、互いの首元にあった痣は――今は眼を凝らさねば分らぬほどになっていた。 「…………………」 帰れない夜、帰ってこない夜―― 隣に片割れがいない、朝まで不安で眠れなかった夜。 それはもう二度と再び訪れることはないが、決して消えることもない――十数年前の、呪われた夜の記憶………。 二人は物心ついたときから、すでに檻の中にいた。お前たちが赤ん坊の頃に大陸の北の方で手に入れた――そう見世物小屋の親方は言っていた。 両親の顔も、生まれた村の名も知らなかった――母親は頭から爪先まで白く、眼ばかりが強く輝きを放つ生まれたての双子を見て発狂したという―― 彼女にとって、その双生児は白き天使ではなく、悪魔から与えられた悪戯だった――父親は子殺しなどできず、しかし怯え戦慄く妻の愛に応える為――白き二人の赤ん坊を、巡業に来ていた見世物小屋に、二束三文で引き取ってもらった。 この二人さえいなければ――またもとの夫婦に戻る為の、ささやかながら幸せな家庭を築く為の――安易で短絡的な行為だったが、それがそのときの彼らにとって、最良の結末だった。 畸形のヒトを雇い、動物を集め、大陸や国の珍しい品の数々を手に入れ――そんな風に街から街へ巡業を行っていた見世物小屋の親方夫婦は、まるで猫の仔を育てるように二人の赤ん坊の世話をした――いや、ほとんどは下働きの下女に世話をさせ、三つの歳にでもなればもう金を生むことができると皮算用、髪を伸ばさせ、顔を洗わせ――見目だけは気を使わせて育てさせた。 そんな二人が二足で歩くことができるようになると――朝は雑用に使役され、昼間は檻に放り込まれ――人々の好奇の視線に晒された。白い子供を悪魔の余興とみるか、天の使いとみるか――檻の前で人々は眉を顰めたりその眼と肌と髪の色に驚いたり。手足の白さも見えるようにと、身につけることを許されていたのは、薄汚れた白や灰色の一枚布の襤褸切れと変わらないような辛うじて服と呼べるようなものだけだった。酔狂な貴族や商人が、見世物小屋の親方に二人を売らないかと持ちかけてくる回数も決して少なくはなかったが、親方夫婦は首を縦には振らなかった。 あと数年経てば白い双子を使ってもっと稼げることを、この強欲な男と女は知っていた――赤ん坊の頃に引き取った異色の双子は手にしたときから金の成る木で――その夫婦は双子に対して、執着こそはあったが愛情は欠片も持ってはいなかった。 見世物小屋の親方の所有物であった双子の首には、それぞれの瞳と同じ色の首輪が付けられていた。たとえ逃げても簡単には外れぬように――頑丈な革でできた、鍵付きの首輪だった。 満足に走れる年頃になると、小屋付近での朝晩の雑用の際にはその首輪に長い鎖がつけられた。彼らの世界は、巡業先の小屋と馬車の周りで鎖の長さの距離だけ――あとは昼間と夜に放り込まれる、無機質な石の檻が全てだった。 そして、自分と同じ姿をした片割れがいつも隣にいること――それが、すべてだった。辛いことも、隣にいるもう一人の自分が支えてくれたから乗り越えられた。親方に逆らうことはいつしか考えられなくなっていた。何か親方の意にそぐわないことをしてしまえば、隣にいるその大切な片割れも一緒に鞭打たれたから。 朝の雑役、昼間の見世物、日暮れの片づけ、日に二回だけの食事……――それだけ終わってしまう灰色の毎日が十年と少し続いたが、双子は隣にはいつも自分の片割れがいたのでこんな悪条件の中でも二人の心は黒く染まったり捩じれたりしなかったのかもしれない。 けれどいつか…… いつか一緒に、もう少し歳を重ねて強くなれたら――何処か遠くへ行こう……――そして青い空の下、緑の草原を一緒に――足が動かなくなるまで駆けてみよう……―― その頃は、そんな夢が二人にもあった――いつかきっと、自由になれる――自由になろう――そんなあまりにもささやかな夢が。 しかし双子の望みは間もなく潰えた。その夢を忘れさせられるくらいの絶望が二人を襲ったから。 もうきっと自分たちは――この輪廻から逃れられないと――そう肌で感じさせられる、おぞましい絶望が。 「……………」 ブラウは杯を握る自分の手を見つめた。 この白い手は今でこそ、敬愛する主人の為に彼の好みの味の珈琲を淹れ、夜食を作り、寝床を整え、靴紐を結び、バンダナを直し、ペンを走らせ――そして武器を持ち、守ることも覚えたというのに―― 「……………」 「 あれは秋の夕暮れ刻だった――いつもなら小屋の撤収作業をさせる為に二人を檻の外へ出しに来る親方が、その日はロートの腕だけを強引に取り、寄り添っていたブラウから引き剥がした。 ブラウとロートの手は離れまいと互いに向かって懸命に伸ばされたが、しかしついにロートは檻から連れ出され――二人は初めて内と外に別れてしまった。 檻の柵に手をかけ弟の名を呼び続けるブラウに、親方の乾いた声が投げかけられた。 「心配するな、お前は“保険”だ」――そのときはまだ、それが何を意味するのかブラウにはまるでわからなかった。 そして腕を掴まれながらも 「大丈夫だ、ブラウ。数時間で戻ってこれるって……」 それでもどこか不安そうに震える声でそう呟いたあと、ロートは親方に引きずられるようにして連れて行かれ――月が真上に上がった頃に、ブラウの元へと帰された。 一度離れてしまったら、もう二度と会えないのではないのだろうか――そんな不安に押し潰されそうになりながら涙交じりに雑役をこなし、檻に戻された後もひとり膝を抱えながら出入り口の柵をジッと見つめて待つことしかできなかったブラウは、親方に檻に放り込まれるようにして戻ってきたロートの姿を見るなり彼の名を呼びながら破顔した―― しかしロートから返ってきたのは、ブラウに向けられた安堵の眼差しと――何かを堪えるように無理に微笑もうとする、痛々しい表情。 「ロート……?――!!ロート!!」 大丈夫、だから……―― そう呟きながら石の床に吸い込まれるようにして倒れた片割れをブラウは寸でのところで支えると――苦痛に歪められているロートの表情を見て半狂乱になりながら親方を呼んだ。 ブラウの助けを呼ぶ尋常ではない声を聞いて移動家屋から煩わしそうに出てきた親方はしかし、ロートの様子を檻に入るでもなく確かめると、彼はブラウに向かって傷薬が入った小瓶を放ってきただけだった。 ロートが下肢から流していた血の存在に親方の視線で初めて気がつき、その有様を確認したブラウの碧い瞳からはとめどもない涙が溢れ出した――そして彼は咽び泣きながらロートの手当をした。下肢の裂傷と、白い身体に浮いた打撲や欝血の跡――首輪も強く乱暴に引かれたらしく、首にも痛々しい掠り傷が赤く浮いていた。 どうして何もしていないロートがこんなになるまで折檻を受けなければならなかったのか――どうしてこんな目にあったのか――ブラウは彼の手当をしながら幾度も弟に問いかけたが、彼は力無く首を振るだけだった―― それでも苦しい息の中、ロートはブラウを落ち着かせるように声を絞り出した―― ブラウ、明日親方に呼ばれても、お前はいっちゃダメだ……俺が行くから……―― 絶対に、いっちゃダメだ……―― ブラウの腕の中でロートはそう何度もうわ言のように繰り返した――ブラウは訳がわからないまま、震えるロートをただただ抱きしめることしかできなかった。 その日、檻の外側から二人を照らす月が呪われたように黄色かったことを、よく覚えている―― まるでそこから始まる二人の地獄の日々を暗示するかのように。 「……………」 喉を潤す薬湯の熱が心地良かった。 ブラウは自身の体重を隣に座っていたロートに肩越しに預けた――彼の頑健な肩はブラウの肩が寄りかかってきてもビクともしなかった。 ロートは何も言わず、自分の方へ流れてきたブラウの月に煌く銀髪に目を落とし、それを長い指先で戯れに弄っていた―― 次の日の夕方、見世物小屋の興行が終わる少し前に親方はやってきた―― 「碧いの、今日はお前だ」――ブラウが親方に手をとられると、「俺が行く!ブラウはダメだ……!」ロートがいつにない剣幕でブラウの腕にしがみつきながら親方を止めようとしたが、昨夜の後遺症のせいか足もとの覚束ない彼を親方はあっさりと突き飛ばし、昨日と同じ台詞を吐いた。 「今日はお前が、“保険”だ」――そんな身体じゃできない“仕事”だって、お前もよくわかっているだろ?―― 親方は下卑た笑みを浮かべながらロートを見下ろすと、一人訳が分らないでいるブラウを無理矢理檻から連れ出した。そして昨日ロートにしたのと同じように、ブラウにも囁きかける。 安心しろ、夜には戻してやるよ。ただしお前が 何か裏を含んでいるような悍ましい声音とロートが自分を呼ぶ悲痛な叫びに挟まれる中、ブラウは懸命に笑顔を作り弟に向かって安心させるように言った―― 大丈夫だよ、ロート……夜には戻ってくるから…!!―― そのとき――ロートは泣いていた。幼いころからブラウに比べると辛いときも悲しいときも滅多に涙を流さないその紅い目から零れた大粒の涙は、ブラウの生涯において忘れえぬ記憶となった。 鉄柵の隙間から手を伸ばし、涙で枯れそうになる声で名前を呼び続ける僕の片割れ―― やがてブラウはロートの声すら届かぬ移動家屋の裏へと連れていかれ、服を剥ぎ取られ石鹸水を浴びせられると、下女によって乱暴ながらも隅々まで洗われた。 そういえば昨夜帰ってきたロートの髪からも微かに石鹸の匂いもしたけれど、それよりも何だろう――ロートのものではない、 冷たい水に震えるブラウにもう一度無造作に水がかけられ、泡立った石鹸が完全に落とされた――そしていまだ震えているブラウを、若い下女がやはりぞんざいに拭いていく。彼女は何故か苛立っているようだった。 「……これを着な」 ――その後タオルから身を解かれたブラウに下女から放り投げるようにして渡されたのは、上等な布で作られ、フリルをあしらわれている少女が着るようなワンピースだった。 訳が分からず服を見つめながら呆然としているブラウから下女が苛立ちを隠さぬままその愛らしい服をひったくると、彼女は彼に無理矢理その服を着せた。 そして鏡の前に座らされ、濡れた髪に何度も櫛を通されて髪を整えられた。 「……………」 鏡の中にいるのは、自分ではないような気がした――親に連れられ時折見世物小屋を見に来る裕福そうな商人の娘たちが、こんな恰好をしていたような気がする。いつもより身体を綺麗にされて、女物の服を着せられ――それがいったい何の為か、ブラウには皆目見当もつかなかった。 「………?」 髪を整えられているとき不意に――ポタリと温かい滴がブラウの手に落ちた。その滴が落ちてきた方を見上げると、いつも無表情な下女が何かを堪えるようにして唇を噛みしめたまま静かに涙を流していた。 「……どうして泣いているの?」 ――不思議そうに目を瞬かせるブラウの問いかけに、下女は慌てて袖口で涙を拭った。 「……なんでもない。ほら、綺麗になったろ?」 櫛を置き、下女は白い秋桜をあしらった小さな髪飾りをブラウの耳元につけてやると、珍しく小さく微笑んだ――しかしその微笑みがあまりにも悲しかったので、ブラウは何と声をかけたら良いのかわからなかった。 支度が済むと、ブラウは親方に手を引かれるまますっかり暗くなった裏道へと連れていかれた。履きなれない少女向けの青い靴は痛かったし、夜風は剥き出しの脚に妙に冷たく感じられた。 ――裏道で待つこと数分。パカパカと軽快な音を立てながら一台の辻馬車が二人の目の前にやってきた。親方はもう一度ブラウの肩を強く掴むと彼の背後から低く囁く―― 「いいか、お客には絶対逆らうなよ……何をされても言う通りにしろ。そうしねぇとお前は二度と此処へは戻れないし、ロートとも永遠にサヨナラだ……」 ――ブラウが親方のその言葉に竦む前に辻馬車の中から長い手が伸びてきてブラウを暗い馬車の中へ引き込むやいなや彼の蒼い目に眼隠しをした。 外からは親方の謙った媚びるような声が聞こえてきたが、馬車はその声を無視するかのように再び馬の足音を響かせたはじめた。 ガラガラと車輪が鳴る音と馬の足音――ブラウは真っ暗で底の知れない恐怖を紛らわす為にひたすらそれらの音を頭の中で反芻した。馬車が揺れ始めてから三十分程経ったそのとき、車輪と馬の蹄の音がピタリと止まった。そしてブラウはまだ顔も見ぬ無言の同乗者に目隠しをされたまま手を引かれ、長い石畳の上を数分歩かされ――辿りついた玄関先で、自分だけが受け渡されたようだった。新しくブラウの手をとったその人は、手袋をはめていた。 ブラウは目隠しをされたまま、また見知らぬ手袋の人に手を引かれ――階段を上り、長い廊下を歩き――やがて重く鳴って開く扉の音をブラウは聞いた。 「お待たせ致しました、ご主人様」 ――ブラウの手を引いていたその人は扉の向こうの人に恭しくそう告げると、ブラウの目隠しを外した後、彼だけを残してそのまま出て行ってしまった。 急に明るくなった目の前にブラウが眩しそうに眼を擦っていると、 「あぁ、噂通りの可愛い子だ……」 「言っただろ、まるで少女のようだと」 「これは……楽しみだな……」 ――三人の男の声がした。 ブラウが目を開き周りの様子を見ると――見たこともないような目映い豪奢な部屋に、身なりの良い三人の壮年の男達がブラウを品定めするかのように見つめていた。 その男達の年齢は、親方より少し若い位だったように思う――ただし彼らが着ているものも、彼らの身のこなしも、その言葉遣いも、そしてその眼差しさえもが――まるで別世界の人達のようにブラウには見えた。 貴族の人たちだ……――見世物小屋の檻の中からでさえ、ほんの数える程しか見たことがなかった身分の人達だと、ブラウは反射的にそう思った。ただぼんやりと彼らを見つめていると、そのうちの一人がブラウの前にやってきた――栗毛色の柔らかそうな髪に、ブラウンの優しそうな瞳――首元を寛げた真っ白なシャツにテパードのスラックスを履いている彼はその上品な指でブラウの白い頬に触れると穏やかに微笑んだ。 「綺麗だね……まるで白磁のようだ」 ――男はブラウの肌を掌で堪能するように撫でると、彼を部屋の中央にあるティーテーブルまで連れて行った。そして少し高い椅子にブラウを座らせてやると、温かい紅茶を繊細な造りのティーカップに自ら淹れ――「お飲み?」と言いながらブラウに差し出した。 「……………」 ――逆らうな――親方の言葉が耳の奥で再生され、ブラウは恐る恐るティーカップを受け取った。既に目の前に座っていた少し癖のあるブルネットの髪の男がテーブルに頬杖をつきながら人懐っこい緑色の瞳を細めてブラウに微笑みかけてくる。ティーテーブルから少し離れところには濃紺に金糸の模様を施された大きく立派な天蓋付きのベッドがあり、その深く茶色く光る支柱に寄りかかっていたのが、金髪に氷のような目をした最後の男だった――その男だけがブラウに微笑みかけず、まるでその冷たい瞳で観察するかのようにまだ幼さが残る彼を見つめていた。 初めて飲んだ“紅茶”は、想像していたよりも遥かに甘く美味しいものだった。香りの良い温かさがブラウの喉に彼の緊張を和らげてくれるかの如く柔らかく広がった。 「クッキーもあるよ、どうぞ?」 ――ブルネットの男がブラウの目の前にチョコレートやマーブル色のクッキーがのった皿を差し出してきたが、ブラウは黙ってそれを見つめるだけで手をつけなかった。 「どうしたの?遠慮しなくていいんだよ?」 ――他の二人よりもやや若い緑色の瞳の男が不思議そうな顔をした。 「……弟に悪いと思っているのかな?大丈夫、帰りに土産で持たせてあげよう……」 ――いつの間にかブラウの背後に立っていた栗毛の髪の男は彼の長い銀髪を一房掬い上げると、その色を愛でるようにその銀糸に接吻した。ブラウの背筋にゾクリと冷たいものが走ったが、彼は栗毛の男の言葉を信じ、差し出されたクッキーに手を伸ばすことで自分の気持ちを誤魔化した。 煌びやかなのに、四人もヒトがいるのに――奇妙なまでに静かなこの部屋。彼らの慣れぬ優しさも得体のしれない恐怖となりブラウの心に迫ってはいたが、彼はクッキーの欠片を零さぬように咀嚼することにひとまず集中することで、その恐怖を紛らわした。 「……ジルの奴も大層執着したんだろうな。」 ――それまで黙っていた金髪の男がおもむろに口を開いた。ブルネットの男が小さく笑う。 「 「彼も酷な性格だからな……ローレンスは午後のお茶の時に、アレは機会があればぜひ買取りたい代物だったと言っていたよ……」 私も同じ気持ちだがね……――栗毛の男はブラウの白い首筋を猫の子でも愛でるように撫でながら話した。 「あのがめつい親方は 「あんな奴らは早いとこお縄になってしまえばいいのさ……そしたら僕らのような奴らの誰かがこの子達を保護するだろう?」 「いいね…… 「……ッ……ぁ………」 ――意味の分からない大人たちの会話はブラウの耳を素通りしていたが、不意に燃えるような熱がブラウの華奢な身体を駆け抜けたかと思うと、彼らの声が徐々に歪んで聴こえ――それに反するように自分の心臓の音がやけに高く早く彼を襲い、先ほど飲んだ紅茶の甘酸が侵食するようにブラウの全身を犯していった。 「……ッゴメンな……さい……ッ!」 ――ブラウはやっとのことで食べかけの菓子を皿に戻すと、何か粗相をする前にまずはこの部屋をでなければと椅子から降りようとしたが、身体を動かせば激しい眩暈が彼を襲い、椅子から転がり落ちる寸前に栗毛の男の適度に鍛え上げられた腕に抱きとめられた。 あぁ、やっと君の声が聴けたね……――愛らしい、良い声だ……―― 「………!!」 そう感慨深げに呟きながら栗毛の男は椅子から受け止めたブラウを軽々と横抱きに抱きあげると、今はすっかり紅潮している彼の頬にキスを落としてきた。栗毛の男の腕の中で、ブラウの身体がビクリと小さく跳ねた。栗毛の男から離れたくて手足を動かそうにも、いまだ感じたことのない緩慢な熱がブラウの全身を襲い体の自由がまるで利かない。 薬が効きすぎているのかな……辛いだろう?可哀そうに……もうすぐ楽にしてあげるからね……―― ブルネットの男の甘い声と手がブラウが着ているワンピースの襟元を寛げながら揺れた。そしてブラウはいつの間にかあの天蓋付きのベッドの上に横たえられていた――生まれてこのかた感じたことのなかった、柔らかなベッドの感触が刹那ブラウを感動させたが、次に襲ってきた恐怖がその感慨を吹き飛ばした。 「や……っ……!!」 ――前が肌蹴られたレースのワンピースの隙間からブルネットの男の手がブラウの胸元を触れた瞬間、まるで熱い電気が爪先まで走るような感覚がブラウを苛み、自分でも聞いたことのない悲鳴が口から洩れた。 随分とそそる声を出してくれる……―― シャツを脱いだ金髪の男がブラウの背後にまわり、鍛え上げられた自身の躯を背凭れ代わりに彼を支えた――たったそれだけの所作だけでも、肌に何かが触れるたびにブラウの息は荒く苦しくなり、彼の手は無意識に背後の男に縋った―― 「―――!?」 ――それに気をよくしたのか、ブラウはまだ少女のような頤をその金髪の男の無骨な指に捕らえられ、背後から深く貪るように 「ほら、ちゃんとこっちも反応している……おや、どうしたんだい?そんなに怯えて。――そうか、やっぱり君も初めてなのか……自分で触ったこともないのかい?」 ――ブラウのワンピースを捲り上げ、彼自身に触れながら栗毛の男はそう言うと、初めて他人に触れられる違和感に蒼ざめ思わず腰を逃したブラウのまだ幼さが残る小さな楔を手で扱くことで愛撫を施した。 「――ァア!!――ッ嫌だッ!!ヤメッ……ァ!!アァッ……!!」 感じたことのないおぞましい感覚に泣いて暴れるブラウの動きは彼の背後にいた金髪の男に封じられたせいで快楽を逃すことを阻まれ、ブラウの耳元を舌で嬲りながらそのまま感じろと囁くブルネットの男の吐息と声に思考まで侵され、彼はやがて栗毛の男の手に放つことを強制されるがままに堕とされた。 薄い胸を苦しげに上下させ、嗚咽しながら身体を震わせるブラウを見ながら、男たちは感嘆の溜息を吐いたり、クスクスと笑ったりしている―― 「こいつは……ハマるな……」 そう言いながら金髪の男が背後でゴクリと喉を鳴らす音が聞こえた。 「ほら、どうだい?君の、“初めて”の味だよ……」 ――栗毛の男の長い指がブラウの口腔に唐突に侵入し、先ほどブラウから絡め捕った青い臭いのする精を彼の舌に擦りつけた――その味に咽びながら懸命に首を横に振るブラウの髪を慰めるように撫でながら、 「今度は僕の番だね……」と、ブルネットの男の緑の眼が妖しく光った……―― 「…………………」 それからのことは、まるで他人事のように覚えている――下肢に塗りたくられた薬の感触も、男の指が体内侵入したときの異物感も、背後から腰を押さえつけられ貫かれたときの痛みと絹を裂くような自分の悲鳴も、大腿を伝った血の温かさも、男たちに代わる代わる身体を揺さぶられているときの絶望感も――すべてこの皮膚が、神経が、聴覚が、味覚や嗅覚さえもそれらのことを忘れずに覚えているというのに、そのときの己の心はあれからどうだったのかがまるで思い出せない。 しかし初めて壊された心が唯一つ、覚えていること――果てしないと思われる凌辱の中で自分は、 優しい、ロート――今なら君の気持ちが分かる――僕を守ってくれようとした、君の気持ちが……――昨夜流した君の涙と言葉の意味が……―― ロート、ロート、ロート………――君も昨夜の僕みたいに、ひとりでいることを不安に思っているのかな……――大丈夫、だいじょうぶ……もうすぐ帰るから……君のもとへ……帰る、から……―― 「…………………」 昼は見世物――夜は男娼――そんな強いられた生活はその日から当り前のように毎日続けられた。見世物小屋が興行の為に場所を移動するたびに、その土地の貴族―成金―金を出し合う享楽者達――新しいお客達が夜毎双子を檻から連れ出した。 ただし夜は日替わりで客の相手をさせられた――身体を申し訳程度に休める名目と、親方のもとに片割れを残しておくことで客を取る方の勝手な逃亡を阻止する事がその目的だったが、生まれてからずっと一緒だった双子に対してはたったそれだけの戒めが、見世物小屋に繋ぎとめておく何よりも頑丈な見えない鎖だった。 そして丑三つ時に、夜明けの鳥が鳴く前に、朝日が目覚める寸前に――身も心も穢されて石の檻に戻ってきた片割れを――もう一人は慰め、介抱し――そして朝までの束の間の時間を、互いに寄り添い抱きしめあって眠った――この腕の中の存在だけが、唯一信じられるものだったから――そして誰よりも己を信じ、守ってくれる――そして何よりも守りたい――最後の希望だったから。 そんな生活が、二年と少しばかり続いたある年、王国で数十年振りに黒死病が広まった――王国ではすでに予防薬も特効薬が出回っていたが、それでもしかし高価な薬――まずは貴族達の命を救い、富裕層が手にし、そして平民はそれらの支配層からの救いの手を待つか――すべてを売り払って手にいれるしか未だ方法はなかった。 黒死病が流行ったその年は、見世物小屋もさすがに閑古鳥が鳴いていた――それでも親方は双子の夜の仕事の方でたんまり金を稼いでいたのだが――そんなある夕暮れの薪割りの最中にロートが倒れた。昨夜相手をした裕福な商人の家から拾ってきたのだろうか、高熱で魘されるロートに縋るブラウを親方は急いで引き離すと、医者へ連れて行くといってロートを台車に横たえ、ブラウをそのままにして見世物小屋が立つ敷地から出て行った――しかし不安に唇を噛むブラウが薪割り場で立ち尽くすなか見たものは――街とは逆の方向に台車を引く、親方の姿。 その小道の先にあるのは、大きな河だ――ブラウは慌てて斧を手に取ると、自分の青い首輪と移動家屋を繋ぐ太い鎖目掛けて力の限り振り下ろした。手の豆が潰れるのも構わず、鎖が砕けるまで何度も何度も斧を振り下ろし――鎖が二つに割れた刹那、ブラウは親方とロートが消えた小道を駆け出した――力の限り走ったのは初めてだったが、足が石で傷つくのも構わず、ブラウはまだ新しい轍の跡を懸命に追いかけ――やがて水が流れる音を聴いた――その中で何かを引き摺る音も……―― 「――!!親方!!」 「――ッ!?テッメェ!!何しやがるッ!!」 ――ブラウは麻袋を担いで今まさに大河に放り込もうとする親方に飛びつき、彼を川辺に引き倒した。乾いた土の河原の上に麻袋が投げ出され、熱で意識が朦朧としているロートの苦悶の顔がその麻袋の開いた口から見えた。ブラウは地面に腰を打ちつけ呻く親方には構わず、ロートの半身を麻袋から引出し彼の無事を確認すると安堵の溜息を吐きながら今は力無き片割れを抱きしめた。 「そいつから離れろ!!お前にも病が遷るじゃねぇか!!」 「――医者に連れていくって言ったじゃないか!!なんで……なんでロートを殺そうとするんだ!?」 ――ブラウはロートを抱きしめる手に力を篭めながらその青い瞳で親方を睨みつけた――ブラウは気がつかなかったが、そのとき親方は彼のその眼光に刹那脅威を感じていた。それはつい先ほど引き倒されたときに感じたものと同じものだった――あの時のブラウの力は、彼の同年代の少年達の力よりも遥かに強いものだった。鎖に繋がれ、檻に入れられていたとはいえ、見世物小屋における日々の力仕事はすべて双子に任されていた。よって彼らの体は知らず知らずのうちに鍛え上げられ――成長するにつれ、頑健なものへと変わっていったのだった。 ブラウは斧で鎖を断ち切ることでその力を初めて使った――誰でもない、 「高い薬がなきゃ死ぬ病だぞ!?そいつに払う金なんぞあるか!!」 「――ッ!!金なら、俺達が毎晩……」 「発病した後から治すのにゃ金も時間もかかり過ぎるんだよ!諦めろ!!これからはそいつの分もお前が稼げば済むことだ!!」 「〜〜〜〜ッ!!貴様ァァ!!」 ――親方が喚きながら腰元から抜いた小刀の先をロートの方へ向けた瞬間、ブラウの中で何かが切れた。 彼は河原に落ちていた流木の枝を手に取りそれを振り上げることで、小刀の刃から片割れを守ろうと必死に親方に立ち向かった――その碧い眼はいつになく爛々と輝き、明らかな殺気を双眼に宿していた。 「――ッ!!いい加減目を覚ませ!!貴様も刀の錆にしちまうぞ!?」 「ロートを助けろ!!そうしないと俺もアンタのところには二度と戻らない!!俺もロートと一緒に――!?ロート!?」 <――ッ馬鹿野郎!!小僧!!死にたいのか!!> ブラウが親方と対峙していたまさにそのとき、彼らが来た河原の道から地を揺らすような罵声と馬が数頭 御者の腕が良いせいか馬車を牽く二頭の黒毛の馬は身を大きく踊らせながらも、倒れ伏しているロートの身体をその蹄鉄で押し潰すことを避けた。馬の太い脚の間で土埃にまみれながら荒い息を吐くロートは、急な事態を 「……ブラウを、助けて………」 「――!!ロート!!」 ――ブラウは流木を投げ出し、一歩間違えば馬の脚の犠牲になりかねないロートを庇う様にして彼を抱き起した。そしてブラウはあらん限りの声で叫んだ――再び興奮し始めた馬を宥めていた御者でも、 「ロートを助けてください……!!」 ――お願いです……お願いです……!! 死なせないで……――蒼い瞳から零れた熱い雫が、すでに声を発する力すらなくただブラウの腕の中に横たわるロートの熱で上気した頬を伝ったそのとき、彼らの運命を変える“最初の声”が馬車の中から静かに響いた。 <答えはひとつ。紅と碧――どちらが欲しい?> 「……ラウ、ブラウ」 「――ッ……ロート……」 気がつけばロートの心配そうな紅い眼差しがブラウの深い蒼を覗き込んでいた。自分が両手で持っていたはずの杯はいつの間にかロートの左手にあり、それはコトン……と音を立て、ブラウの右手側にあるベッドサイドチェストに丁度置かれたところだった。 月はいつの間にかだいぶ傾いていた。 「……大丈夫か」 ロートの逞しい指がブラウの白い首筋を労わるように撫でた。ブラウの形の良い唇は微かに震えている――ロートがあやすように手の甲で彼の頬に触れると、ブラウはそっと目を伏せた。毛布の上で所在なさげな彼の左手にロートが右手を添えてやると、ブラウの長い指が躊躇いがちだがやはり縋るように絡んでくる。そしてブラウはロートの硬い首筋にその貌を埋めた―― 「……トーンフェーダ―嬢の苦しみは………」 私たちにも、理解できる……――ブラウの擦れた小さな声がロートの白い肌にかかった。彼は黙って頷いた。まだ何も知らぬ二人だけの世界にいた自分たちが地獄に堕とされたときと同じように、彼女も酷虐な日々と人の蛮行の最たるものをその痩躯に叩きつけられた身――しかも何の不自由もなく愛されて育った貴族の娘が人の心を捨てた獣たちに身も心も犯された衝撃は計り知れないものであっただろう。 「けれどなぜ……士度様が…………その罪を……」 背負わねばならないのか……その罪に苛まられねばならないのか……私には……わからない――なぜあの方が愛を手にいれるのにこうも苦しまねばならないのだろう……――ただただ幸せに……なって頂きたいだけなのに……―― あの方が苦しんでいるのに……私には何もできない……ただ見守ることしか……ロート、私はどうしたら……――!?―― いつになく震える声で嘆くブラウの唇をロートのそれが塞ぎ、言の葉を止めた。ブラウの碧い瞳が刹那見開かれ湖水のように揺れたが、やがて彼の白磁の瞼がその青を覆い隠した――冷えていた身体が 「ブラウ……」 碧い瞳から零れた熱い滴を大きな掌で覆う様にして拭いながら、ロートは 「ブラウ……士度様は強い方だ。士度様のお心を信じ、お傍で支えるのが俺たちの務めであり運命――俺たちは士度様のお心の強さを誰よりも信じている……そうだろう、ブラウ?」 どうした……月に惑わされたのか……?―― ロートは涙に濡れる碧く澄んだ瞳をあやすように覗き込みながら片割れの唇にもう一度 大丈夫だ……お前には、俺がついている……―― 「……ッロート……!」 ブラウは片割れの名を呼んだ――まるで救いを求めるように。 抱き締め、抱き締められている腕のぬくもりは昔と変わらない――否、それはロートの瞳の色のように灼熱に変わることをブラウは知っていた――彼の言葉と眼差しに今身体が火照り始めているのも、自分があの頃と変わってしまったからだ――救われ――守ると誓い――力を手にいれ――それでもどうしてだろう、自分の心は時折思い出したかのようにこんなにも脆くなる……――それを誰にも悟られぬままにいつもしっかりと受け止めてくれるのは、他でもない大切な 彼の心に甘えている――こうやって不安の発作に襲われ、彼の暖かさに縋るたびに途方もない罪悪感がブラウを襲うのだが、その都度ロートは だからお前は素直に感じて、啼いて、心の澱を吐き出してしまえ……―― 女も羨むようなブラウの白い首筋の、今ではすっかり薄くなった忌まわしい痕にロートは舌を這わせながら、所有の印を彼の ビクリと震えるブラウを木の床に横たえ、ロートは彼のシャツを寛げる――床に散らばる月に照らされた銀糸の髪が彼を誘う星のように煌めいていた。 戯れに触れたくなるようなその銀糸も、指に吸いつく肌理の細かい白い肌も、一つになるときに強張り縋ってくる指先も、羞恥からか押し殺すような耳に心地よい喘ぎ声も、愛撫に震える姿態も――目の色以外は自分とは寸分違わぬ容姿であるはずの片割れは、身体を繋げるときはまるで違った生き物であるかのようにロートの瞳には映った。 「――ぁッ……!!ロート……!ロートッ……もう……ッ!!」 やがて そして絡み合う二人の銀糸のように互いの存在を何よりも近く深く感じ、同時に達する刹那の瞬間にロートはブラウの耳元で偽りなき心を告げる―― あぁ……あぁ……私もだ、ロート……―― 一筋の涙とともに返されたその言葉に、ロートも深く安堵する――そして双子はその白く長い指を硬く繋ぎ合い、二人は共に思考を白く染めた。 「………………ッ……」 腕の中で弛緩し、胸の鼓動の早さを背中越しに伝えてくるブラウを抱きながらロートは思う―― このような切ない想いを、あの言葉を……そして真実を――あのお方が想い人に届けることができるようになるには、あまりにも遠く厳しい 「……………………」 自分たちは今、こんなにも倖せだ――尊敬する方に仕え、片割れと共に生きる―― これ以上望むものといえば、今はただ……あのお方の幸福を――切に、切に……―― 「……………………」 月から降るの透明な光の中、ロートの胸に凭れながら気を失う様に夢の中へと旅立ったブラウに毛布を掛けなおすと、ロートも彼の首元に顔を埋め、座ったままの姿勢で目を瞑った―― 瞳を閉じる瞬間に映った夜空には月灯りの中、星々が皓々と瞬いていた。 明日の空の色はきっと――ブラウの瞳とよく似た色だ。 「67……68……69………」 夜明けの前の霧がローレライ号を包む中、船長室からそれほど遠くない甲板壁に立てかけられた巨大な的に大中小様々な大きさのナイフが次々と放たれ、その木の的を裂く音が静かな船上に響いていた。 的には外側にやや乱れたナイフの円が作られ――それは徐々に規則正しく中心へと狭められ、ナイフの群れは円を描きながら中央を目指している。 鍛え上げられた逞しい体躯がその少し陽に焼けた腕からナイフが放たれるたびに躍動する――手にナイフの柄が収まる瞬間に感じるその心地よい重さ――長く武骨な指を巧みに操りその柄を持ち変える際に重心を計り狙いを定め的に向かって放つ――刃が空を切る際に鳴る鋭くもいっそ清々しい透明な音。 シャツを脱いでいる上半身には汗が光り、彼の躯が動くたびに珠のように霧の中へと散っている――その眼光鋭く凛々しい貌は、昨日曇りがちだった様子を垣間見せない、いつもの船長の顔だった。 「……………」 まだ太陽の光が青白くしか届かない自室の窓に背を預け、ロートは 「……ン……ロー…ト、……何をそんなに嬉しそうに……――!?」 煙草を銜えているロートの口元が小さく弧を描いた。薄明かりの中でもこうやってブラウはロートの機嫌を表情ではなく纏う空気で読んでしまう。 「――この音……士度様がナイフの稽古を……。何をしているロート!急いでお湯の準備をしなければ……!汗が冷える前に身体を拭いて頂かな――!?」 言いながら慌ててブーツを履き、シャツを羽織りながら遽しく出て行こうとするブラウの手をロートが扉の前で引きよせ、軽くキスをすることで彼の動きを止めた――淡煙がブラウの貌を襲わぬよう、白く長い指が器用に煙草の位置を変えた。 「ロ……―ト?」 煙草の仄かな苦みがブラウの唇に伝わった――片割れからの珍しく 「――そう慌てるな。湯は 「あ、あぁ……」 彼にしては饒舌なこの様子――そして煙草を水の張った ブラウは気持ち気恥ずかしくなり、まだ途中だったシャツのボタンを留めなおすと小さく息を吐きながらロートの横から窓の外を覗いた。 「……85……86……87……」 無心にナイフを投げ続ける主人のサポートをしているのは范だった。的のスペースが徐々に小さくなり、終りが見えてきたのだろう――手元にナイフと他の武器しかないせいか、“彼女”の表情に少し焦りの影が見えた。朝の冷たい空気は運動後の刹那には心地好いが、放置は殊更宜しくないことは范にも分かっているだけに。 隣の窓が適度に曇ってきた――湯も心地よい温度に焚けただろう。サイドチェストの上に置いてあったシャツとタオルをブラウが手にすると、ロートが陶器の水差しと盥を手に取り、自室の扉を空いた片手で器用に開けた―― 94……95……96……―― やがて小気味よい音と共に百本目の小刀が的の中央を美しく飾った――大きな的には所狭しとまるで 「………………」 朝靄のなか、まるで雄々しく踊るようにナイフを投げる彼の姿は美しかった―― マドカが彼の数えの声に気がついたのはその数が四十を過ぎたところだった――昨夜啼いて濡れてどうしようもなかった自分の躰はまるで何事もなかったかのように清められ、ベッドの中にいた。悪夢に魘されることもなく自分は夢の中に入れたのも、直前まで彼が傍にいてくれたせいだろうか。 昨夜の有様と今の自分の状態からマドカの頬は自然朱に染まる――彼が身体を拭いてくれたことに、自分はまるで気がつかなかったのだ。そしてベッドの中にいつまでもいると、マドカの肌に触れてきた彼の指先、彼の声、彼女を翻弄した彼の舌の感触、快楽に啼く自分の声、脳まで侵すような淫靡な感覚――それらすべての記憶が全身に蘇りそうな気配がしたので、マドカは再び火照りそうになる身体を朝の空気の冷たさにさらすため、彼の静かな声が淡々と続く窓辺へと足を運びカーテンを開けた。 薄くなり始めた霧の中でナイフを放つ彼の眼光は、まるで獲物を狙う鷹のように鋭くまっすぐだった――それは昨夜マドカに見せたあの眼差しとはまるで違うもの……―― 全てが―全てが初めて彼に与えられた……泣きたくなるような優しい愛撫も、 マドカ――哀しみや寂しさを埋める為に……誰かに縋りたいと思う気持ちは、罪じゃない―― 「……士度、さん…………」 彼は哀しみや寂しさに押し潰されそうになる 彼はときに叱って、励ましてくれて……私に忘れかけていた大切なことを教えてくれる――そしてこの船で私のことを……守ってくれている……。 そんな優しい彼に、自分はいったい何ができるだろう……―― ひとりでいると全てを失った孤独の闇に蝕まれそうになるのに、士度の隣りに立つと心安らぎ、その闇が遠のくことをマドカは気づいていた。つい二週間程前に出逢ったばかりなのに、もう彼はずっと以前から自分のことを守ってくれているような錯覚に陥ってしまうこともある――王都に着いたら、きっと離れ離れになってしまうのに……――けれどそうなる前に、私を何度も救ってくれた彼に……公爵様と文を交わす機会すら与えてくれた彼に……私に、できることはいったい何……?―― 「………………」 朝の静謐な空気がマドカを包んでいるというのに、彼女の身体は僅かに熱を帯びていた――“彼”のことを考えるとこうやって胸が熱くなって、切なくなって……―― それはとてもふしだらな事のようにマドカには思え、彼女はとりあえず早く彼のもとへ行って朝のご挨拶をしよう……と着替える為に窓のカーテンを再び閉める。そして着替えを用意し、ネグリジェを脱いだ時に初めて気づいた、胸元の 「あ………」 不意に眼の奥がツンと熱くなり、マドカはその花弁に手を寄せた――その指先を掠めたのは、婚約者である公爵から贈られた青い星籠――トクン……と心が跳ね、伝わるのは、再びいつもより速く走り始めた心臓の音……――そしてまた、泣きたくなる。 それは海賊船で流した涙とはまったく別の、あたたかく柔らかく、彼女の心から湧き出てくる涙だったが、マドカはまだこの仄かな暖かさがいったいどこから来るものなのか、知らなかった。そして彼女は無理に涙を拭きながら――今日、彼の前できちんと微笑むことができますようにと、神に祈りを捧げた。 「おはよう、お嬢さん!東の国の林檎は如何かな?」 赤と青、どちらがお好み?―― 「……!?え…と……」 マドカが部屋を出るなり呼び止めたのは、昨日この船にやってきた東の国の美しい訪問者だった。彼は大きな袋を軽々と背負っている目元を布で覆った従者を随え、ローレライ号の朝当番に清清しい差し入れをしているところだった。 マドカの目の前に差し出された赤と青の艶めく林檎は、どちらもトイフェルドルフのものよりは優に二倍は大きく立派で美味しそうで……しかし女性が食べるにはどちらも大き過ぎることこの上ない――丁寧に断るべきかどちらかを手に取るべきか――いかにも貴族のお嬢さんらしいマドカの逡巡を花月はむしろ楽しんでいるようで、それをからかうように「はい、どっち?」と意地悪な質問をもう一度わざとしてみせ、マドカをますます困らせる。 「両方やってくれ、花月……!!」 するとデッキの先で士度の声がした――マドカと花月が顔をあげると、士度は丁度湯で汗を拭き終わり、洗いたての白いシャツに袖を通しているところだった。彼の傍には碧と紅の二人の従者と黒衣を纏った小柄な范が付き従っている。 「――ということだから、はい、お嬢さん!」 「え……あ、あの……!!」 「またあとでね、士度……!!」 東の国の若君はにこやかな笑みを浮かべながら至極マイペースにマドカに二つの林檎を押し付けると、士度に手を振りつつデッキの反対側の見張り小屋の方へと従者と共に足を向けてしまった。 「………………」 「……マドカ!」 「は、はい……!!」 士度に呼ばれたマドカは両腕にやっと抱えられる大きさの二つの林檎を抱いて、士度の方へと駆けて行った――旭がようやく、ローレライ号の甲板を照らし始める刻限だった。 「すみません……あの……私なんだか、欲張っているようで……」 思えばぐずぐずと迷っていた自分が悪いのだ――マドカは顔を真っ赤にしながら、青と紅の林檎を二つとも士度に差し出した。すると士度は青い方の林檎を受け取りながら、事も無げに言った。 「別に……これでいいんだよ」 そう言いながら士度は手にした青い林檎をブラウにの方へと放る。 ロートが刹那、懐かしそうな表情をして主人と片割れに視線を流した――穏やかな表情で林檎を受け取ったブラウはそれを素手で綺麗に二つ割ると、当り前のように片方をロートに渡す。 「二つとも手に入れらる そんでそれが、思わぬお宝になるかもしれねぇしな……―― クスリと軽く笑みをつくりながら、士度は紅い方もマドカの手からとると、ブラウがしたのと同じようにそれを二つに割った――そして腰のベルトからよく手入れをされた小刀を取り出すと、割った片方を再び二つに割り――それらをマドカと范に与えた。あっという間に乙女が食べるのに相応しい大きさに化けた紅いリンゴと士度を、二人は目を白黒させて見つめた。 「お前の両手に余ってた林檎も、これで丁度よくなったろ?」 「……!あ………」 涼しげに林檎を齧る士度の表情と重なり、父の言葉がマドカの脳裏に蘇った―― 貴族の子女はいずれ嫁ぎ、夫君が不在のときは城の留守を預かる身になるんだよ。沢山の人達を切り盛りしなきゃならん。だからマドカも……―― 父様……―― 何かを決めるときは自分の為だけではなく、周りの人々にも目を向けてごらん。なぁに、そのうち分かるよ……―― 「どうした?食ってみろよ……美味いぞ?」 士度の貌を驚いたように見つめ続けているマドカに、彼は少し首を傾げてみせた。 「は、はい……」 零れ落ちそうになる涙を堪えながら、マドカはリンゴに歯を立てた――フォークを使わずに林檎を食べるのは初めてだったが、その爽やかな甘さと香りが彼女の心を癒してくれた。 「………………」 そんなマドカの表情を、目線が近かった范だけが垣間見ることができた――“彼”は貴族のお嬢さんを無表情に見つめながら紅い林檎を嚥下した。 喉を通る酸味は、范の心の中で疼く味とよく似ていた――彼はそのことに眼を瞑るように、もう一度林檎に齧りついた。 「いくぞ、マドカ。少しばかり早いが朝飯だ――ん?歩きながら食ったって別にいいだろう……船の上だぜ?」 言いながら士度はマドカの背中に軽く手を添え食堂までエスコートをする。途中、士度はロートに向かって左の人差し指と中指をスッ……と横一文字に宙に流すことで合図を送った。 「―― 「 畏まりました――そんな士度とロートのやりとりにブラウは目を細め、范は少し眉を顰めた。 この双子は士度様の側近中の側近――しかし先程のお湯にタオルに着替えといい、士度様のことに関しては何でも分かっていて隙がないのがたまに癪に障る。しかも武器の扱いも戦闘能力も――この船の上では一・二を争う程に長けているのもまた癪だ。いや、それは士度様にとっては至極重宝することなのだがしかし――彼らの前では自分は劣等感を禁じ得ない――そんな自分に対しても范は半ば子供染みた腹を立てていた。 「士度……さん……?」 「あぁ、マドカ……来いよ。」 客人の数も多いせいか、朝食の席はそれはそれは賑やかなものだった――マドカはへヴンと亜紋に掴まり、そこに笑師も加わって果てしないお笑い講義にわけも分からないまま耳を傾けざるを得なかったのだが(そしてそこで得たものは何もなかったわけだが)、劉邦と薫流と花月と――比較的静かな朝食を先に済ませた士度が、食堂を出る際にマドカに後で来るように指定したのが、ローレライ号の甲板の――ハンモックが揺れるこの特等席だった。 まるで集合場所のようにデッキの中央に飾られている風見鶏の屋根の下のハンモックに身を横たわらせながら、士度は珍しく紙巻煙草を吹かしていた。屋根の柱に備え付けてある台の上では、碧い眼の従者がお茶の用意をし、紅い眼の従者は水が薄く張ってある陶器の灰皿を丁度持ってきたところだった。始めてみる彼の嗜好にマドカは目を白黒させながらも、士度の手招きに応じてハンモックの傍に駆け寄った――「ほら……よ!」「キャッ!!」――すると士度はマドカの手を取るなり、煙草が片手にあるにも関わらず彼女を器用に掬い上げ、あっという間に同じハンモックの住人にしてしまった。 彼との距離が急激に近くなり――寛げてある彼のシャツの胸元から香る彼の匂いと体温が、マドカの貌を桃色にした。宙に浮いているような不慣れな感覚も、彼が隣にいて支えてくれていなければもっと恐ろしく感じていたことだろう。一方士度は機嫌良さげにマドカの肩を抱くと、彼女に上を向くように促してくる――仰向けになるように見上げると、眼に入るのはよく磨かれた 「ここは良い風が吹くんだ。上を見れば紫檀だが……ほら……」 「……!!綺麗………」 士度が抱いていたマドカの肩をデッキの方へ向けるとハンモックが揺れ――マドカの視界に飛び込んできたのは、黒い船体に堂々と靡く白く目映い大きな 「…………………」 マドカは強ばっていた肩の力を抜き、目の前に広がる鮮やかなコントラストに心洗われる心地に酔いしれた。こんなにも晴れやかで爽やかな視界――この蒼い海の世界で何度も目にしてきたかもしれないのに、こんなにも安らぎをもたらしてくれた船の景色はまるで今日が初めてのよう。それはやっと自分の心が――父の死や海賊船での出来事や……それらの耐えがたい現実を受け入れようとし始めているからだろうか……――今日はこんなにも素直に景色が、心に入ってくる。 最近ようやく艶を取り戻し始めたマドカの黒檀色の髪を、士度の長い指が彼女の背後から戯れに梳いた。マドカはこの景色を見せてくれた彼の配慮に感謝するように、その背をそっと士度に預けた――彼女の肩を抱く彼の指先が応えるように微かに動いた。 ――二人は暫くそうやって暫くハンモックに揺られながら船と空の景色を眺めていたが、やがて士度が煙草の灰に気づいたのか、腕を伸ばし彼の背後の灰皿に灰を落とす気配がマドカにも伝わってきた。そして珍しい香煙がマドカの鼻腔を擽った。 「……煙草、お吸いになるんですね?」 戯れにマドカが訊いてみると、「なんだ、臭いが気になるのか?」――そんな答えが返ってきたので、マドカはフルフルと首を振った。 「いいえ……父様はよくパイプを吸ってらっしゃって……時折いらっしゃる父様のお客様も、葉巻やパイプを……男の方がリラックスするときに吸うものだと聞いたのですが、小さい頃から思っていたんです、いったいどんな味がするのかなって……」 だって、味が違うとか良いとか悪いとか……なんだか楽しそうにお話してたんですもの――そんなマドカの好奇心に士度は苦笑しながらすっかり短くなった煙草を持ち変えると、庇の方へと高く紫煙を吐き出した。 「ま、確かに女が吸うシロモノじゃねぇよな……」 そして吸殻を灰皿の水に投げ入れると、腕の中のマドカに向かって囁いた――「試してみるか?」「え……?」「煙草の味……」 「――ンッ……!」 士度は彼女の返事を聞かぬまま、その体位を入れ替えると彼女の唇を素早く奪った――差し入れられた彼の舌から、濃いハーブのような苦味と匂いがマドカの口腔にも染み入るように伝わってきた。 人がいるのに……!――マドカは貌を朱に染めながらも慌てて彼を引き離そうとしたが、気づけば二人の従者はいつの間にやらその場から消えている。 「……………」 彼女はもう一度、身体を力を抜いた――どうしてそうしてしまったのか、自分でもまるでわからないままに――彼女は士度のキスに身を委ねた。 「ん……っ………ァ……」 クチュリと時折音を立てながら、士度の舌はマドカをひどく優しく蹂躙する――口蓋を弄り、彼女の舌を絡め捕り、頬を内側を嬲り、歯の裏側をなぞり――マドカが震えるその華奢な腕で彼の背に縋らざるを得なくなるほどに、彼は唇と舌先で彼女に淫美な感覚を濃厚に伝えてきた。 「……ッン……あ……ァ………ん………」 マドカの息が徐々に速くなり、その愛らしい眦に涙が溜まりはじめた頃になってようやく、士度はマドカの唇を解放した。二人の照らう唇の間を一筋の透明な糸が繋ぎ、やがてプツリと途切れた。どちらともなく上がる吐息の熱が、やけに煽情的に二人を包む。 「………………」 士度は涙交じりに息を上げているマドカを無言のままもう一度背後から抱き締めるようにしてハンモックに身を沈めた――彼女の痩躯が強張ったのは、ほんの一瞬だけだった。 「昼過ぎに……南都に着く……」 そしたら降りて、港街を歩いてみよう……きっと良い気分転換になる……―― 「はい……」 それまで、少し……―― 煙草の味の感想を訊かぬまま、士度は彼女を腕におさめたまま目を閉じた――マドカも煙草の感想を云えぬまま、回された逞しい腕にそっと手を添え眼を瞑る。 心臓の鼓動が――あぁやっぱりどうしようもなく速い……――彼に気付かれているかしら……――私はどうして……彼の身を振りほどかないの……?―― 神様……神様………この気持はいったいなんですか……?彼はどうして私を……私に………――そして私は……私は……… 午後の穏やかな光と風がハンモックに揺られる二人を柔らかく包んだ―― 主人を探しにきたアマデウスが二人をみつけたが、やがて面白くなさそうに傍らのベンチの下に潜り込み、ふてくされたように彼もまた午睡に入る。 まるで二人を起こさぬようにと、ローレライ号は静かに海原を往く―― 船首の黄金の歌姫が見つめる先には――二人の運命を変える殷賑の南の街が、青い空の下で華やいでいた。 「――そうそう、ローレライ号がそろそろ 大きな鍔を持つ漆黒の帽子を手にしながら立ち去り際に告げたジャッカルの声はどこか楽しそうだった。 「ほう……それはそれは……」 宝石に繊細な細工を施す為に顕微鏡を覗いていた男装の麗人がその秀麗な貌を上げて静かに微笑んだ。 「 あれからあれ以上の作品はすっかりご無沙汰なのでね……―― 短いソバージュの銀の髪が可笑しそうに揺れ、彼女は口元に自嘲気味な笑みを作った。 「ビーストマスターが過保護過ぎなければ……」 そろそろお散歩にでも連れ出すでしょう……?―― では、また……――眼を限界にまで細めた独特の笑みを残しながら、ジャッカルは空気のように工房から夜闇へと消えていった。 「あの星が……戻ってくる………」 彼女は鋭利な 薄暗い工房のショーウィンドウの中央には、青い星が籠に捕らえられている首飾りが飾られている――しかしその輝きは暗くくすんだ、どこか寂しい青――今はトーンフェーダ―嬢の胸元に慎ましやかに隠されている、至高の青とは似ても似つかぬ紛い物。 クレイマン――そう呼ばれた彼女は蝋燭の薄明かり中、手元にあったとあるスケッチを広げると感慨深げな眼差しでそれを見つめた。 それは宝石細工に関してはまるで素人が描いたものであったのだが―― 「愛とは……やはり才能に勝るものなのかね……?」 やがて彼女は短くなった蝋燭を吹き消すと、今宵最後の客人が去った店の札を裏返した。 ――closed―― & to be continued.... |
いわゆる双子の過去編(1)でございました。
馬車飛び込み事件の後もいろいろあるのですが、(2)etc.はまた本編終了後にでも。
後ほど幕間話にも出てきますが、ロートは女も抱きます。単に戯れに。男はブラウだけ。
そのことについてブラウは特に嫉妬心はありませんが、彼は女は抱きません。男もいりません。
ロートがいればいいんです、的な。
第九章から事件があったり二人の仲に変化があったりでやっとこさお話が進みます…。