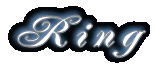
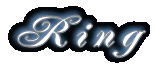
――大晦日――
新宿のコンサート・ホールで行われた盛大なニューイヤー・コンサートは大盛況のうちに幕を閉じた。
その日のマドカは舞台の上でも至極ご機嫌だった――
前から三列目の貴賓席には大好きな彼の気配が。
彼女がその優美な音を奏でる度に揺れる胸元の銀の鎖には、
クリスマスにプレゼントされたばかりのホワイトシルバーの指輪がステージ・ライトの中で柔らかな光を放っていた。
劇場の時計が午前零時を回ると、オーケストラが奏でる高らかなファンファーレと共に観客席に金銀のリボンや紙吹雪が舞い、
会場は大きな感嘆の声と、新年を祝う喜びの声で溢れる。
舞台の上でも――演奏者と指揮者が互いに抱き合い、握手を交わし合い――互いの健闘を讃えながら、新しい年の挨拶が飛び交う。
そんな華やかな喧騒の中で――
マドカの見えない瞳は確かに、貴賓席で一人こちらを見つめている士度の姿を捉えていた。
ホール全体が祝い事に賑わぐ中で、今日は正装姿の彼が座るその空間だけはとても静かに、しかしいつになく穏やかに佇み――
髪を後ろに撫で上げている彼はアームレストに片肘を突きながら、舞台の上の彼女に優しい視線を送っている。
マドカはそんな彼の眼差しを心地よく感じながら――まだ弓を持つ右手でそっと――今はペンダント代わりの指輪に触れた。
そして幸せそうに目を細めると、上品なルージュが輝く可憐な唇が愛らしく言の葉を――音無く奏でた。
――明けまして、おめでとうございます・・・・士度さん――
そして彼の眼が――珍しく細まる気配がして――
――おめでとう、マドカ――
彼は――唇を動かしただけなのかもしれない――もしかしたら、照れくさそうに、小さく呟いたのかもしれないけれど・・・・
どちらにせよ――神に愛されたマドカの耳は、彼の言葉を優しく彼女の心に運び――その美しい丹花を薔薇色の微笑で彩った。
そんな二人の刹那の通い合いは、指揮者がマドカの肩を抱きながら異国の言葉で新年の挨拶をし――
今日の彼女の演奏を褒め称えはじめたことで、唐突に途切れてしまったけれど。
それでもマドカは幸せだった――
今年もきっと、彼と二人――温かく素敵な思い出を沢山つくれるだろう――そんな確信めいた春色の想いが、彼女の心に緩やかに浸透していく。
そして新年最初に奏でるアンコール曲は――彼が好きだと言ってくれたメロディーを。
愛の挨拶を――この胸の高鳴りを、貴方への想いを、音にのせて。
彼が目を瞑り、心地よく聴き入っている気配も
数多の拍手の中で――ゆっくりと手を叩く彼の音も――
その全てがマドカにとって心躍らんばかりに愛しく、観客が思わず見蕩れてしまうような――
彼女の音色の如く優雅な微笑をその舞台の上で花咲かせた。
誰よりも何よりも――彼に向けて。
やがて割れんばかりの歓声と拍手の嵐の中、新しい年を祝う演奏会は幕を下ろし――
彼女の姿が真紅のカーテンの向こうに消えていったことを見届けると
士度もゆっくりと席を立ち――余韻と興奮冷めやらぬ観客に紛れて、一人ホールを後にする。
熱が篭ったホールを出ると、年が明けたばかりの澄んだ夜の空気はいつもより心地よく、彼の頬を撫でた。
それはきっと、この耳に、身体に――羽のように強く、しなやかでいてフワリと優しい軽やかな音と、何よりも美しいあの微笑が――心安らぐ音色を残しているから。
士度は白い息を吐きながら、心なしか足取り軽く――歩いて音羽邸を目指した。
打ち上げのパーティーが終われば、マドカは真っ直ぐ戻ると言っていた――きっと彼女は笑顔で、その疲れた体を委ねてくることだろう。
そして今日の演奏会のことを飽く事無く話して――久し振りに洋酒でも飲みながら、彼女の話を聞くとしようか。
いつもより静かな繁華街のネオンの中を歩きながら、士度は思い出したようにコートのポケットを探ると――
柔らかな羊皮の手袋を取り出し、手を通した。
クリスマスの夜の、少し恥ずかしそうな彼女の貌が、士度の脳裏を再び過ぎる――
そして指輪を薬指にはめてやったときの、驚いたり喜んだり泣いたりして忙しかった、彼女の表情が――彼の口元に控え目な笑みを浮かばせた。
今年も彼女と二人――新たな刻を刻みながら、穏やかに歩んでいければいい――そんなささやかな願いが、自然と士度の心を通過する。
やがて士度は、どこか浮かれているような自分に自嘲気味に唇を歪ませたが――それもこれも新年のせいにして、夜目に近くなる風見鶏の姿に目を細めながら
ほんの少し、歩みを速めた。
「いかがでしたか?――お嬢様の初演奏は・・・・?」
エントランスでチェスターコートを脱ぐ士度に、執事が穏やかな声で訊ねてきた。
「ああ・・・・・」
士度は刹那、思案するような面持ちをつくった後、ただ一言
―― 良かった ――
そう呟くとコートを執事に渡し、シャツの第一ボタンを外しながら居間へと脚を向けた。
「そうでございましたか・・・・」
相変わらず寡言な居候殿に執事は密かに苦笑したが――今夜もお嬢様は素晴らしい演奏をされたのだろう――
それはいつもよりどこか静穏な彼の表情から伺い知ることができる喜ばしいメッセージ。
「後で軽食をお持ち致します。」
廊下を歩きながら袖のカフスを外している士度に執事がそう声をかけると、軽く手が上がる返事が返ってきた――
暖炉の火は
遅番のメイドと共にカナッペを作り、居間まで運んで――そしたらお嬢様をお迎えに上がるのに丁度良い時間になる――
執事はエントランスの掛け時計を見ながら、手にしたコートを持ち直した。
コートの外側はすっかり冷えてしまっていて――居候殿はまた、常人ならタクシーを使う距離を歩いてきたらしい。
(先に温かい珈琲でも・・・・)
差し上げよう――執事はエントランスのクローゼットを開けながら、
そんな
車が音羽邸に入る音がして・・・・ソファの上でその大きな体躯を投げ出していた士度は、
居間の電気は消されたままで――しかし暖炉の薪はまだパチパチと音を立てながら心地良いぬくもりを奏でている――自分はそんなには眠っていなかったらしい。
「・・・・・・・・」
士度は炎に淡く揺れる天井を仰いだまま髪を無造作にかき上げた後、そのまま身を起こし――
目の前のガラスのテーブルに置かれてある、ワインクーラーに視線を流した。
暖炉の火のオレンジに染まる氷の中で――きっとこの赤ワインは程好く冷えている。
コンサートの成功に上機嫌で帰ってくるであろうマドカはおそらく――今夜だけは好きなだけ飲ませてとせがむことだろう。
そんなことを考えながら、士度が苦笑交じりにワインボトルに手を伸ばしたそのとき――
<落ち着いてください・・・!お嬢様・・・・!>
執事の、声を抑えながらもかなり困惑した声が屋敷に響き――
士度が目を丸くした刹那、バタン・・・!と居間のドアが開き――コートを着たままのマドカが、涙に濡れた顔で立っていた。
足元にはやはり困り果てたモーツァルトが――
「・・・・マドカ?」
「――!!〜〜〜ッ」
士度の声を聞いた瞬間、マドカの漆黒の瞳からポロリと涙が零れ落ち――彼女は士度に抱きつくと、そのまま必死に声を殺しながらシクシクと泣き出してしまった。
彼女を難なく受け止めた士度であったが、自分の想像とはかけ離れた様相で帰宅した彼女に彼の頭も混乱をきたすばかりで――
「なぁ・・・・どうしたんだ、マドカ・・・・」
士度が訊ねても、彼女は
<ごめんなさい・・・ごめんなさい・・・・・>
と涙ながらに呟きながら彼のシャツに顔を埋めるばかりで。
士度がふと顔を上げると、居間の扉の前には執事がやはり悲しそうな表情で立っていた。
士度はチラリとモーツァルトに視線を落とす――
すると、彼もクゥ〜ンと切なげに鼻を鳴らし・・・士度を見上げながらいつもより控え目な声で、呟いた。
<マドカ・・・落トシタッテ・・・・>
モーツァルトの声を聞くなり――士度に縋りつきながら、マドカはついに声を上げて泣き出してしまった。
「落としたって・・・・何を、だ・・・・・?」
泣いてばかりじゃ分かんねぇよ・・・・――そう言いながらマドカの小顔を覗き込もうとしてはじめて――
彼女の胸元にも、どの指にも――プレゼントしたはずの指輪が無いことに士度はようやく、気がついた。
すっかり泣き疲れて自分の腕の中で眠ってしまったマドカを士度は彼女の部屋のベッドまで運ぶと、そっと掛け布をかけてやる。
月の灯にキラリと光る涙の痕が、どこか儚げで痛々しかった。
あの後、ようやく聞き出したマドカの涙ながらの説明や、執事の補足によると――
コンサートの後のちょっとしたクローズ・パーティーも華やかに終わり、少々の美酒に酔いしれながら演奏者達が帰路につきはじめた頃――
モーツァルトと、同僚と共に、会場の長い階段を下りていたマドカの背後から、同僚の男性がポンッと背中を叩きながらオヤスミの挨拶をしてきた――
そのとき、彼のカフスがマドカの指輪を通していた銀の鎖に絡み――男が思わず腕を引いてしまった瞬間、真新しい銀の鎖は非情にもプツリと音を立てて切れてしまった。
そしてその鎖からスルリと指輪が滑り落ち――マドカが慌てて差し出した両手をもすり抜け、指輪はコツン・・・コツン・・・・と音を響かせながら、階段を転がり落ちていく。
階段からその痩躯を飛ばさんばかりにその身を乗り出したマドカを押さえることで、同僚たちやモーツァルトが彼女の転落を必死で止めたが、
その間もマドカの耳は指輪の軌跡をしっかりと拾っていた――
指輪は一段、また一段と階段を落ちていき――そして舗装されたタイルの小道をコロコロと転がり――
カツン・・・・!と何かの金属にあたる音、そして――
「アッ・・・・!!」
彼女の悲愴な悲鳴が深夜の新宿に木霊した――
指輪が――大好きな人から貰ったばかりの、大切な、大切な指輪が――何処かに吸い込まれるようにして消えてしまった――
周囲の人達の制止を振り切り、マドカはいつもより足早に階段を駆け下りた。
そして――
「モーツァルト・・・!!指輪を探して・・・!!」
泣き出さんばかりの声で、モーツァルトに指示をすると、自らも膝をついてタイルの上に指を這わす。
彼女の落し物に気がついた同僚たちも、慌てて歩道の上に目を走らせはじめた。
――確か、金属に当たって・・・・!?――
不意に――マドカの爪が、カツンと硬い金属にあたり――その下からはゴウゴウと暗く、水の流れる音が――
<マドカ・・・・コノ下・・・・・>
――タブン――
水デ匂イガ消エチャッタ・・・・――格子状の下水の蓋を見下ろしながら呟いたモーツァルトの申し訳無さそうな声に
マドカは大きな眩暈を感じながら、それでも懸命にその蓋を持ち上げようと硬い格子に指を通す。
すると
「マドカ・・・!何をやっているのよ・・・!?」
指が傷ついちゃうじゃない!!――彼女の行動を見かねた同僚達にまたもや止められてしまう始末で。
「離して・・・・!!大切な・・・・ものなの・・・・!!」
いつも落ちついた様相の彼女から出た思わぬ悲痛な叫びに、事の次第を目撃していた大人たちは思わず息をのんだ。
そして彼女はその場にペタンと座り込み、悲しみを堪えきれず――頬には伝う涙が。
執事が主を迎えに到着したのは、丁度そのときだった――
それから、二人は最寄の交番に寄って――遺失物の届出をしたのだが――
「・・・・流れる下水に攫われたのなら・・・残念ながら見つかる確率は・・・・」
――低いですね・・・・何せ新宿区30万の住民が使用する下水道が縦横無尽に繋がっているわけですし・・・・――
警察官の口から漏れた現実に、マドカの心は押し潰されるばかり。
そして応対に出たもう一人の警察官はとりあえず落とした指輪の形状を訊こうと、口を開きかけたが――
相手の少女が盲目だと改めて気づき、躊躇いがちにお付の執事に視線を向ける。
しかし――
「ホワイトシルバーの素敵な指輪だって・・・・周りの人達は言ってくれました・・・・」
マドカが涙声でポツリポツリと・・・指輪の特徴を語り始める。
「ハートに・・・・翼が片方だけ生えていて・・・羽は四枚で・・・・ハートと翼の間に・・・・小さなダイヤが・・・・」
――私の左手の薬指にピッタリの・・・・9号の・・・・指輪です・・・・――
ポロポロと零れる涙を拭う事無く、マドカは一つ一つ思い出すように言の葉にした。
そう、忘れるはずなんてない――嬉しくて、あまりにも嬉しくて――暫くは眠るときもずっとつけていた大切な指輪。
何度も、何度も、その形を指先で辿り、肌に、躰に記憶させ・・・・冷たいはずの銀なのに、どこか仄かなぬくもりさえ感じて・・・・。
時間をかけて、真剣な面差しで、一生懸命選んでいたって――後から卑弥呼さんから聞いて、再び目頭が熱くなって・・・・。
そしてマドカが我に還ったときはすでに、リムジンが音羽邸に到着したときだった――
士度は彼女の涙の痕をそっと拭ってやると――パタン・・・・と静かな音と共にその部屋をあとにした。
そして自室に戻ると、上等なベストとワイシャツをベッドの脱ぎ捨て――手早くジーンズとTシャツに着替えると――
途中、台所と物置に寄り道をしたりしながら
彼は静かに音羽邸を抜け出して――よく晴れた夜空の下をシャベルと袋を手に
裏通りへと消えていった。
元旦の朝の空気も清清しく――
眼鏡をかけたメイドはいつも通り、朝一で運ばれてくる牛乳を取りに音羽邸の正門の取っ手に手をかけた。
門の隙間からはいつも通りきっちりと―― 半ダース分の牛乳瓶が並んでいる。
そして元日の新聞がたっぷりと、音羽邸のポストの中を満たしている。
朝の寒さに白い息を吐きながら、メイドが門を開けた、そのとき――
ガラン・・・・!
と門前の道路から大きな音がしたかと思うと――
「――!?」
目の前のマンホールの蓋がいつの間にかずらされていて、中からまずは大きな――泥まみれの――白い袋が――
そして次に放り出されたのは、やはり大きな、真っ黒に汚れたシャベルで・・・・・・
(・・・・新手の泥棒かしら・・・?)
執事に知らせにいくべきか無視するべきかメイドが迷っているうちに、マンホールの中からヌッと現れたのは――
「・・・・!?士度様・・・・!!」
メイドは慌てて門から飛び出すと、すっかり疲弊した様子の居候殿の前に駆け寄った。
みると、彼は頭から爪先まで――顔も手もジャケットもジーンズも靴も――泥だらけで黒く墨がついたように汚れ――
――いったいどうなさったのですか・・・!?――
そうメイドが問い掛ける前に――
「・・・・悪ぃ、何も訊かねぇで・・・・風呂、貸してくれねぇか・・・・?」
シャベルと中身が一杯に詰まった袋を拾い上げながら、彼は掠れた声を出した。
「――!!は、はい・・・・!只今ご用意致します・・・・!!」
メイドは目を丸くしながらも、すぐに踵を返すと一足飛びにエントランスへと消えていった。
後には士度と、彼女が取りにきた牛乳と新聞が残されたが――
運んでいってやろうか―― 一瞬、士度はそう思ったが、伸ばされた真っ黒に汚れた自分の手が視界に入るなり、その腕を静かに引っ込めた。
そしてただ、シャベルと袋を手に――どこか重く感じる自分の身体を引き摺るようにして、音羽邸の門をくぐった。
音羽邸の一階にある広い浴室からは新しいお湯をバスタブに満たす心地よい湯煙が空間を満たしていた――
士度はその浴室の手前にあるやはり空間を贅沢に使った
汗と泥に塗れすっかり重くなってしまっていた黒いTシャツを煩わしそうに床に脱ぎ捨て、
目の前にあるやや大きめの二つのタブに栓をし――紅い印がついた蛇口を捻り、半ばまで湯を張った。
そして今は薄汚れている白い袋の中身を、片方のタブに入るだけぶちまける――
すると錆とヘドロにまみれた小さな金属がいくつも塊となって現れ――白い大理石のタブを黒く染めた。
――失礼します・・・――
そう断りながらミントのバスエッセンスと彼の着替えを持って洗面室に入ってきたメイドは、
逞しい上半身を晒しながら洗面タブの中身を睨みつけている居候殿の姿に、思わず頬を朱に染めた。
――確かに、優秀な鼠どもだ・・・・――
そんなメイドの様子を知ってか知らずか、タブの中身をザッと確認しながら、浴室と洗面室を満たす湯気の中で士度は眉を潜めた。
タブの中には穴の開いた古銭やナット、キーホルダーのリングに訳の分からない何かの部品――そして中には指輪らしきモノもいくつか混じっている。
士度はその真っ黒なタブに手を入れると――中に埋もれているそれらの金属をひとつひとつ確かめながら、それらをもう一つのタブへと投げ入れていった――
「なぁ・・・・泣くなよ・・・指輪なら新しいヤツを買ってやるからさ・・・・」
――それより階段から落ちなくて良かったじゃねぇか・・・・――
そんなことを言いながら――少し落ち着きを取り戻しながらも、相変わらず士度の腕の中でさめざめと泣き続けるマドカの背を士度が摩っていると、
彼女はフルフルと首を振りながら涙ながらに応えた。
「だって・・・・士度、さんが・・・・初めてくださった指輪で・・・・私、とても嬉しくて・・・・・」
――ずっと・・・・一生・・・・お婆さんになっても持っていようって・・・思っていたのに・・・・・――
また一滴、ポツリと・・・・温かい涙が士度のシャツを濡らした。
「せめて・・・・せめて・・・・・あの指輪が広い海に行き着いて・・・・」
ヒクリ・・・・と愛らしくしゃくり上げる彼女の頤を士度は優しく持ち上げた。
「射し込む・・・・優しい太陽に照らされながら・・・・静かに海の底で・・・・眠ることができればいいのに・・・・」
消え入りそうな声でそう言いながら、マドカは再び涙を零した。
士度にはただただ――彼女を抱きしめてやることしかできず――
そして気の利いた言葉の一つもろくにかけてやることが出来ない自分を呪いながら、彼女の涙を掬い取り、胸に泳がせ――
マドカが泣き疲れて眠るまで、士度は彼女の傍から離れずに――彼女の悲しみに震えるその小さな手をいつまでもいつまでも乞われるがままに握ってやっていた。
「静かに海の底で・・・・・」
――実際は、そんな浪漫的にはいかないものだぜ・・・――
マドカをベッドに運んでから数十分後――士度はシャベル片手に一人、暗い下水道の中に立っていた。
音羽邸を出るとき、厨房の冷蔵庫からありったけのチーズを袋に詰めて――棚に置いてあった大きな円いチーズの塊も一つ、拝借して。
物置から大きなシャベルを取り出して。
コンサートが催されたホールまで戻り――マドカが指輪を落としたと思われる下水溝の蓋を持ち上げ、水流を確認した後、最寄のマンホールの蓋を開けその中へ・・・・。
そして中の歩道を伝って、ホールから続いていた水の流れが一番緩やかな場所まで移動し、周囲をザッと確認した後――
彼はピィッ・・・!と一吹き、甲高い獣笛を吹いた。
するとあっという間に下水道の上下左右から――士度の周りに集う数多の鼠達。
最初士度は――“指輪”を見つけてきたら、この袋の中のチーズを一欠けらずつ持っていっても良いと鼠達に言ってみた。
しかし、鼠達は首を傾げるばかり。
――“ユビワ”ッテ・・・・ナニ?――
士度は一瞬言葉に詰まった後――言い方を少し変えてみた。
“真ん中に穴が開いた金属”を持ってくれば・・・・・――
すると鼠達は一斉に散らばり――歩道を這い、ヘドロに潜り、排水溝を行き交い、壁を齧り・・・・
銘銘これぞと思うものを――“穴が開いた金属”を口に銜えて白い袋に潜り込み、代わりにチーズを一欠けら口にしながら自分たちの寝床へと戻って行った。
士度自身も夜が明けるまでシャベルで周囲のヘドロを掘り返し、夜目を利かせながらマドカの指輪を探した――
水に攫われてからまだそんなに時間が経っていないのなら――もしかしたら、流れが緩やかなこの辺に・・・・・
泥を浚うこと数時間――やがて明けの烏が鳴く頃――士度はマンホールを開けて外へ出ようとしたが
日が出たばかりなのに、地上からは数多の人の声がする――
そうだ今日は元日だった――初日の出に初詣――休日の朝に、最も人が行き交う一日。
士度は仕方なく、下水道を伝ってそのまま音羽邸を目指すことにした――泥だらけの袋の中にはすでに一切れのチーズも残っておらず、
あるのは戻ってきた鼠と同じ数だけの金属の輪。
何の確証もないけれど、ただ――元日でも――たとえ泥やヘドロに塗れても――ほんのちっぽけな可能性に賭けてでも――
自分ができる、“何か”をしてやりたかった――彼女の為に。
そして自分が取り戻したかったのは――指輪ではなく――
彼女の――
もうそろそろ袋の中身も尽きかけてきた、片側のタブはガラクタで一杯だ・・・・。
途中、厨房からコックの悲鳴が聞こえてきたような気がした――
――チーズが無い!!――
悪ぃな、鼠に全部やっちまった・・・・。
庭の動物達が餌を催促する声が聞こえる――今日はメイドがやってくれるそうだ。
朝靄もとっくの昔に晴れて、明るく、はっきりとした朝日がこの部屋にも射し込みはじめる――もうそろそろマドカが起きてきちまう・・・・。
時折執事やメイドが心配そうに・・・・閉ざされた洗面室の気配を探りに来る――心配するな、倒れるなんてヘマはしねぇから――
「アッ・・・・!」
思ったよりも大きな声が出てしまったようだ――執事が珈琲カップを取り落とし、寝坊をしたメイドが慌ててベッドから跳ね起き、
コックは包丁を滑らせ、お屠蘇の準備をしていたメイドは屠蘇散の分量を間違えるところだった――
そして部屋でメイドと共に着替えをしていたマドカは目を丸くし――彼女の振袖の準備をしていたメイドは、小さな微笑を人知れずその口元に湛えた。
乳白色のお湯が張られたバスタブの中で、士度はすっかり凝り固まってしまった身体を解すかのように大きく首を回した。
そして真っ黒だったその姿を石鹸で綺麗に洗われ、匂い消しの為に薔薇の香料にも無造作に漬けられた――
今は小さなソープ・トレイの上で輝いている例の指輪に目を移し、彼は小さな溜息を吐いた。
こんな小さな装飾品の為に、
――だって、士度さんが初めてくださった指輪で・・・・――
「・・・・・少しは自惚れてもいいってことか・・・・?」
士度は自分の考えの甘さを洗い流すかのように、お湯を掬いあげると、そのままバシャバシャと顔を洗った――
すると、コンコン・・・・とバスルームの扉を控え目にノックする音が。
「あの・・・・士度、さん・・・・?大丈夫ですか・・・・・?」
――もう三時間近く・・・・閉じ篭りきりだと聞いたので・・・・・――
マドカの心配そうな声が、洗面室から美しく響いてきた。
「あぁ・・・何でもない・・・・今、上がる・・・・」
士度の返事に、マドカがホッと安堵の溜息を吐くのが扉越しに聞こえてきた。
――振袖・・・・着てみたんです・・・久し振りに・・・・・――
上がったら、見てくださいね・・・・?
そう恥ずかしげに呟きながら洗面室を出て行くマドカは、昨夜より少しは気を持ち直したようだった。
――あぁ・・・・何でもないさ・・・・――
指輪を片手に、バスタブから立ち上がった士度もどこか晴れやかな顔をしていた。
――お前の為なら・・・・お前の笑顔を取り戻せるなら・・・・――
泥に塗れることなんざ、なんでもない・・・・・・
小さな指輪を見つめながら、士度はそれを指先でクルリと回した。
(さて、いつ・・・・どんなタイミングで
――そして
そんなことを思いながら、士度は着替えたばかりのジーンズのポケットに、一時的にせよ再び彼の手に戻った指輪を滑り込ませた――
そして替えの黒シャツにゆっくりと袖を通し――もう一度、ポケットの上から指輪の存在を確認すると、
濡れた髪を後ろにかき上げながら
熱が篭るその空間を後にした。
Fin.
お正月話、2007年ver.でしたv
泥まみれの士度を書いてみたく・・・お正月から災難でございました、士度もマドカも;
関連話として「act as a Lover's proxy〜愛の代理人」も合わせてどうぞ☆
弊サイトのオリキャラに抵抗がない方は、オマケの◇New Years' present◇@士マド付もどうぞv