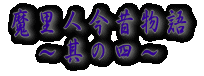
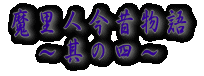
それは彼が「戦士」、と呼ばれる前のお話・・・・
目の前に居る彼女は何故、泣き出してしまったのか・・・・
まだ年端も行かぬ少年にはさっぱり分からない。
話しかけられたから、たった一言、返しただけなのに。
「・・・泣くなよ。」
途方に暮れながらも辛うじて発せられた少年の言葉に頷きながら、彼とあまり年が変わらぬ少女は自分の足元に散らばった菜の花を拾い集めた。
それでも涙はあとからあとから流れてくるばかり。
するとそこへ、背の高い、威厳ある風貌の男がやっきて、徐に少年の手を取った。
少年は顔を顰めながらも、手にしていたナイフと木の塊を懐に仕舞うと、黙って男に引かれていく。
少女は驚いたように顔を上げた。
「
――私が勝手に泣いただけなんです・・・!――
涙を拭きながら懸命に訴えてくる少女に、
俯く少年の手を引きながら、黙ってその場を後にした。
「俺は・・・熊を彫っていたんだ。」
少年はナイフの鞘を確かめながら、呟いた。
「そしたら、アイツがやってきて・・・」
ときどきその辺で見かける、顔見知り程度の一族の少女。
「“士度様、お花をどうぞ・・・”って言ってきた。」
―俺は、両手が一杯だったから・・・――
少年はナイフと、作りかけの熊の彫刻を小さく掲げた。
「“いらねぇ”って言ったんだ。」
長は困った顔をした。
「そしたら・・・」
少年は傍らで笑いを堪えている長の従者をチラリと見た。
「泣いた。」
――何でだ?――
そして不思議そうな顔をして、長を見上げる。
長は小さく溜息を吐いた。
――士度、
それが、どんなに強い
少年が首を傾げた。
長は話を続ける。
――
少年は眉を寄せながらも、長の言葉を聞いている。
――強い
少年は黙って頷いた。
――言葉の刃は・・・時としてどんな刃物よりも鋭く、残酷になる・・・そして守るべきものすら傷つけてしまう武器になる。
そのような武器は真の戦士に相応しくない。後は・・・分かるな、士度。――
長の問いかけに、少年は気まずそうに目を泳がせた。
長はそんな息子の様子に密かに目を細める。
「夕餉の刻までには、戻って来い・・・。」
そして少年の頭をクシャリと撫でながらそう言うと、従者と共にその場を立ち去った。
一人取り残された少年は――難しい顔をしながら、ガリガリと頭を掻いた。
「おい・・・」
泣き腫らした目を擦りながら、丘の上で夕日を見ていた少女は、気配なく近づいてきたその声に飛び上がらんばかりに驚いた。
「し、士度さま・・・!」
少女は膝に乗せていた菜の花を抱えながら慌てて立ち上がった。
しかし、僅かに背が高い少年と目がかち合うと、すぐに恥ずかし気に頬を染めながら俯いた。
「・・・その花。」
そんな少女の様子など気にする素振りもみせず、少年は菜の花に目を向けた。
「まだ寄越す気、あるか?」
少女は少年の無遠慮な問いに一瞬目を丸くしたが、
次の瞬間、赤くなった頬がますま紅潮したかと思うと、彼女は反射的に手にしていた花束を差し出していた。
「ど、どうぞ・・・!!」
「じゃあ、コイツと交換だ。」
少年は花束を受け取ると、空になった少女の掌に何かを置いた。
「――!!」
少女がその物体を認識する前に、少年は踵を返し、駆けていく。
「
去り際に小さく、そう言いながら。
少女の手には、出来上がった小さな木彫りの熊。口には魚らしきものを加えている。
「士度さま・・・・!!」
野原の向こう、既に小さくなった少年に届くように、彼女は精一杯叫んだ。
「士度さま・・・!私、これ・・・大事にしますから!!ずっと、ずっと・・・・!」
野の上で軽く菜の花が揺れた。
そしてすぐに、見えなくなった。
少女は手の中にある物を、愛しいそうに夕日にかざした。
荒削りの力強さの中、どこか優しげな表情をしている小さな熊の人形。
仕上げまで彫り上げた少年の手の温もりが、まだ残っているような気がした。
少女は夕日に紛れて女親が迎えにくるまで、その木彫りを熊を飽きる事無く見つめていた。
そして茜色に染まった空に、少年の面影を描き続けていた。
Fin.
![]()
![]()
士度は士度父=長のことを表に出さずとも、心から尊敬していたのではないかと思います。
彼の兄貴肌で真っ直ぐな気質も、そんな士度父教育の賜物でしょう。