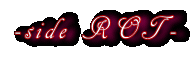
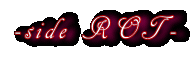
「―――で、結果タイヒザックで行方不明になった娘の数は十九人。領主の娘はゾンネンシャイン伯が家宝の宝石である緑の涙を差し出した結果攫われずに済んだらしい。一介の海賊と云えども、最近は侮れなくなってきてるね……。方や兵糧貯蓄が主な備蓄要塞とはいえ、海からの闇討ちにあまりにも弱すぎるのも問題だ。囚われた娘たちが売られたり病で死んだりする前に、海軍か奪還屋が蜥蜴を檻にいれることができれば良いのだが……」
たとえ戻ってこれたとしても、彼女達の蝕まれた心と体を癒すのには時間が要するものだがね……――
クレイマンは酷薄な笑みを浮かべながら煙管の紫煙を燻らせた――シャツ一枚のみを羽織ったスレンダーながらも高貴に煽情的な躰が真紅のベッドの上に横たわり、理知的な大きな瞳がいまだ壁に背を預けているロートをまっすぐに見つめた。そして彼女の艶めかしい指が彼にオイデと手招きをする――ロートの背がようやく、壁から離れた。
独りで喋り過ぎて、些か身体が冷えてしまったよ……――
「…………………」
クレイマンは既に前を寛げていたロートの白いシャツをスルリと片手で器用に脱がすと、煙管の灰を灰吹きに落とし、そのまま盆へと戻した。
――両手が空いた彼女は、無言のままのロートの精悍な顔に指を滑らせ、彼の紅い眼を覗き込んだ。
「――俺に興味があるといったな……」
この眼や肌の色からではあるまい――何故だ?――
「…………………」
強い口調ではないが誤魔化しを許さないその声音に、クレイマンの目が優美に細まる――彼女は体位を入れ替えるとロートの肩を押してベッドに背を預けることを促した。そうして彼女は彼の上にうつ伏せに身を横たえ、彼の首元に唇を寄せながら囁いた――
「九年前の、叡覧試合で――」
彼女の腰に手を添えたロートの指がピクリと動いた。
「“氷のジル”の耳を切り落としたのは、確か君だったね……」
あの頃は私もまだだいぶ若かったが……若いながらも
――ロートは身体の力を抜いてその身をベッドに預けた――そして紅い天蓋を見つめながら、感情の読めない声云う。
「――奴は……士度様のお供で街を歩いていた兄の後姿を馬車から見て、俺と間違えて声をかけた――」
茶褐色の髪を後ろで束ね、氷のような冷たい眼をした中年の貴族――ブラウはロートを
ジルはまずブラウに自分の
このとき士度は齢十三――伯爵ジルはその少年にこの二人の従者を売りなさいと金貨が詰まった袋を二つ差し出した。紅い眼の奴が先ほど目の前に現れたとき、私のブーツに泥をかけた。本来ならここで剣を抜き罰を与えてもよいのだが、子供の前ではそれは忍びない――こうやって買い取ってから私の好きにするから、君の二人の従者をこの場で売りなさい――この申し出を拒否するならば、従者の主である君が代わりに罰を受けることになるよ……――
伯爵ジルは薄い肌の上に爬虫類のような笑みを浮かべながら、少年が怯えた顔で金貨の袋を受け取るのを待った。
しかし少年は袋に手を伸ばすことも顔色ひとつ変えることもせずこう述べた――
この二人を売るつもりはない、その磨き上げられたブーツにかかった一点の泥の為に貴族様の名誉が傷つけられたのなら、自分が詫びて罰を受けよう。しかしそれなりに手続きは踏んでいただかないと。今すぐ役所に届けにいきますか…?――
――心の中で伯爵は舌打ちをした。思ったよりも頭の回る小僧だ。貴族が庶民の子供相手に罰だの制裁だのを振りかざすようでは、家名に傷がついてしまう――それならと伯爵はもうひとつ案をだした。
これは失礼、勇敢なる少年よ――君の使用人を思う気持ちには恐れ入った。しかし平民が貴族に対して、してはならぬことをあの紅眼はしたのだ。それならこうするのはどうだろう――
伯爵ジルはそう言いながら、はめていた手袋脱ぐとそれをロートに投げつけた――
ロートは刹那眼を見開いたが、彼は黙ってそれを拾い上げる――「身分を越えての決闘は禁止されているはず……」――少年はそう呟いたが、ジルは「――然るべきところにかけあって、それは私がなんとかしましょう……」――伯爵はニッコリと微笑んで、上質の銀のプレートでできた名刺を少年に差し出した。
「後で使いの者をよこしなさい。決闘の詳細と場所を記した証書を渡して戻そう……」
そう言い残してとりあえずその場を去ったジルには勝算があった――数多の戦場を駆け、剣の腕も貴族の中では引けをとらない自分が、奴隷上がりの従者に負けるはずはない。そして勝ちさえすれば、敗者をどうしようが勝者の自由――少なくとも紅眼は、再び我が手に。
しかしジルの思惑は大きく外れ、思いがけない方向へと堕とされていく――少年の使いは来なかった。その代りに伯爵が役所に圧力をかける前に身分違いの決闘の許可が下り、どこでどう聞きつけたのか、当時は健在で今は亡き前王が戯れにその決闘の証人となる叡覧試合という――貴族たちの祭りに発展してしまった。
そのことに対するジルの疑問はしかし、試合に対する動揺にはならなかった――王城の中庭に造られた闘技場に数多の貴族たちが鈴生りになり、これぞ舞踏会よりも刺激的な催しとばかりに好奇と興奮の眼差しを向ける中、ジルはこの試合こそが自らの名を国王陛下と上級貴族に売る格好の機会だと思っていた。
そんななか――声を大にすれば自らの性癖が露見してしまうので密やかなものであったが、一部の貴族達は噂をし合った――あぁ、あの白い双子は生きていたのか……六年前から行方不明と聞いてはいたが。ジルの話によると、なんでも今は商家の使用人になっているとか……――
ジルが勝てば、あの双子は再び夜の世界に身を堕とすのではないか――かつて彼らを買ったことのある貴族達は扇の下で、ワインやシャンパンの影で、期待に口元を緩ませた。
そして士度とブラウがロートの立会人として闘技場の外枠から身を乗り出しながら見守る中、試合が始まり――貴族達は息を飲む。
しかし――決着は貴族達が思ったよりも早々についてしまった。試合開始の銅鑼が鳴り響いてから十分も絶たないうちに、ロートがジルの剣を空に飛ばし、自らの剣の切っ先をその貴族の喉元に突きつけた――貴族達からは驚きの声と感嘆の声が上がり、当時の王からは<ほぅ……>と物珍しげな呟きが漏れた。
まだ青年の域には達していなかった現王であり当時は皇太子であったコウは眼を輝かせ、無邪気な笑顔を湛えながら身を乗り出して拍手をしている――
荒々しく人の命を奪うことを躊躇しないジルの太刀筋は相変わらず戦場の雄の姿を垣間見せたが、基本に忠実ながらも時折予想のつかない動きをし相手を圧倒するロートの太刀筋は、彼が奴隷上がりであることを微塵も想像させず、むしろ教育を受けた者のソレであった。
尻もちをついたジルの喉の皮膚と剣の間には、剣の先ほどの血の玉が浮かび上がり、ジルは小さな痛みとその血のと同じように赤いロートの睥睨の下、そのまま動くことができなかった。
ロートとジルが見合ってから刹那――試合終了の銅鑼が王庭になり響いた。「………………」――ロートは貴族達がざわめくなか、僅かに上がっていた息を整えながら無言のまま剣を納めると、まずは闘技場の外で安堵の表情を浮かべている士度とブラウに小さく微笑みかけ、そして今回の試合の主となった国王の玉座に向かって跪き頭を垂れた。
しかしロートの片脚が土についた瞬間――地獄の底からのような声がロートの背後から聞こえ、怒りに我を忘れたジルが腰から短剣を取り出し彼の背に振りおろしてくるのが、その狂乱の声に振り向いたロートの紅い眼に映った――ロートは咄嗟に身を捩ることで第一撃を避けることができたが、再び騒ぎはじめた貴族達のどよめきのなかで彼はジルと揉み合いながら闘技場の土に背を預けてしまう。
「――!?ジル・フォン・バートリー!!試合は終わっている!剣を納めよ!」――闘技場の中で一連の流れを司っていた王宮の功臣がジルの怪しい動きに気付くなりその狼藉を止めようと叫んだが、敗北に打ちのめされているジルにはその声も聞こえない。彼が二人の間に割って入る前にロートは片手でジルの右手を封じることで振り下ろされようとする短剣を止め、所構わず殴りつけてくるジルの左手には頓着しないまま、自らも腰のベルトから短刀を取り出すと不自由な体勢のまま下から上へと渾身の力で振り上げた。
その瞬間、断末魔のような醜い声と共に鮮血がロートの顔と闘技場に降り注ぎ、人の片耳が土の上にポタリと落ちた。貴族の女達の悲鳴と男達の歓声が宙を舞うなか、ジルは左耳があった場所を押さえ喚きながらロートから離れ、怒りに燃えた悪魔のような眼差しで返り血に濡れたロートを凝視している。
「~~~~!!!貴様ぁぁぁ!!!元は奴隷で……身を売る下賤であった分際で!!もはや貴様の主人共々生かしてはおけぬ!!」
「―――!!?やめろっ!!士度様に手は―――!!?」
ジルは腰元から投擲用の小刀を取り出すと、闘技場の外側で真摯な面持ちで事の成り行きを見守っていた士度の方へその刃を向けた――その瞬間、ブラウは士度を庇うようにして主人の視界を闘技場から隠し、ロートはジルの息の根を止める為に短刀を持ち直し心の臓をに狙いを定めた。
しかしロートの短刀がその手を離れる前に、ジルは彼方から飛んできた銃弾に肩口を貫かれ、あまりの痛みで悲鳴すら上げられぬまま闘技場の土の上に血塗れになりながら転がった。
「――もうよい。興が冷めたわ……」
どこからともなく鳴り響いた銃声にその場に居合わせた者達は固まり、そしてそれに続いた低い声の主に一同が凍りついた――
玉座で黙したまま試合を叡覧していた王が威風堂々と立ち上がり、彼が手にしていた銃からは一筋の硝煙がゆっくりと天に昇っていた。
「――ッ……国王陛下……!!」
誰かの震える声と共に、試合を見物していた貴族達が畏怖と敬意の念と共に一斉に頭を垂れ、貴族の身分に列せられていない者たちは皆慌てて跪いた。
耳と肩口から血を流し続けているジルは仰向けに倒れ伏したまま起き上がることができず、恐怖に顔を強張らせながらただ青い空を見つめるしかなかった。
怖ろしいほどの静寂の中――国王が合図したのだろうか、数名の兵士が闘技場に入場し、血塗れのジルを何処かへ連れ去ってしまった。
闘技場内に残されたのは、乱れた土と、散る血痕、そして中央で一人頭を垂れ跪くロートだけになった――
「――よい、一同面を上げよ」
貴族達はおそるおそる顔を上げた――しかし居並ぶ彼らの面には笑みはない。瞬間的に爆ぜた国王の苛立ちを彼らは全身で感じ、恐怖していた――そして、その恐怖の中には誇らしい思いもあった。近隣諸国によくいる、飾り物ではない――我らの国王はその力と叡智と恐れの天与の才で国を統べる、我らの王は絶対的な存在なのだということを、改めて思い知らされる。
「白き者よ、良い腕であった……」
国王は玉座につきながら、ロートに言葉を投げかけた。闘技場の中央でロートは跪いたままさらに深く頭を下げる。
褒美を与えてつかわす。何か一つ望みを申せ……―――
「―――ッ………」
ピクリと畏れるようにロートの体躯が僅かに動き、場内全体から息を呑む気配がした。国王自らが褒美を与える――それは貴族に対しても滅多にあることではなかった。今、この闘技場にいる元奴隷が望むなら――王宮に仕える地位さえ手にいれることができるだろう。
「………恐れながら申し上げます。私の望みはただ一つ……」
「――そして、君の願いは叶い――今も“士度様”と共に………」
ロートの唇の端にキスを施しながら、クレイマンは彼の身体の上で優しげな表情をした。ロートは無意識に彼女の銀糸を弄りながら、ふと懐かしい表情をした。
「それ以外に俺が望むものは……」
「君の片割れの幸せ?」
「…………」
続いたクレイマンの言葉に、ロートはその紅い眼を驚いたように見開いた――分かりやすい肯定だと、クレイマンの口元は緩む。
「大分前になるな……いつかやはり士度のお供で君の片割れがココに着たとき――彼は君よりも、ほんの少し饒舌だったけれど……」
「―――ブラウと寝たのか?」
表情を感じさせない声と瞳がクレイマンの声を遮った――あぁ、やはり
「私のことは満足させてくれたけどね……彼は私では………ッ……ん………」
「――それで、いい………」
不意に――ロートの白く武骨な指がクレイマンの蜜壺に潜りこんできたので、彼女は彼の身体の上で身を捩じらせ甘い吐息を音にした。
眼を瞑り――体内で蠢く指からもたらされる快楽を追うようにクレイマンはロートの厚い胸板に手をつき身を起こし騎乗の形になると、下の彼がポツリと呟いた。
「アイツは……それで、いいんだ……」
「―――ッ………」
そんなロートの声に瞼を開けるとクレイマンはベッドに沈められ――彼女は上から注がれるどこか柔らかな紅い眼差しに、柄にもなく刹那見惚れた。しかし彼女はその先にあるものが自分ではないことに直ぐに気が付き眼を瞬かせる――思い出されるのは、いつかこの部屋で向かい合った、サファイア色の瞳の白き人――あぁ、彼もあのとき――自分の分身の話をするとき、今目の前にいるこの男と良く似た貌で、ひどく優しい表情をしたではないか……――しかしやはりそれは唯一、自らの片割れに向けられるものであった――また、だ。この二人は女にとって酷な存在だとクレイマンは思った。その類稀なる白き見栄えと観る者を捉えて離さない稀有で美しい瞳の色で、おそらくどんな女の心も攫むことができるはずなのに……――当の本人達の心は、常に主人と片割れのもとに……――あの碧き人もそうだった。彼の方は紅き人よりも饒舌に自分との会話を楽しんでいたようだった――そして、やはり良く似ているその手で、唇で……彼女の躰を熔かしていった……――ただ、碧き人自身は、本当にまるで
この館で相手をする以上、愛を求めているわけではない――しかし碧にせよ紅にせよ、こうもあからさまに目の前のこの宝石のように美しい瞳の向かう先が目の前の自分ではないのは、やはり、どこかチリリと心を焦がす。
彼女は仕方のなさそうに頭を振ると、小さな溜息と共にロートの頬に手をあて、実に彼女らしく微笑んだ。
「まったく、妬けるね……――お喋りはここまでにしよう……さぁ、今度こそ………」
煖めて―――
彼女の言葉を最後まで聴くことなく、ロートはその鍛え上げられた腕でクレイマンの細腰を抱きしめると、彼は彼女の吐息を呑みこんだ。さぞかし冷たいであろうと思われた彼からの
「――アッ………!」
何かを確かめるように鷲掴まれた乳房から感じたのは痛みと快楽の狭間の感覚――自然と眦に溜まる涙の向こうに彼の貌を捉えようと思えば、ロートは彼女の耳元にその貌を移動させ、さきほどまで二人の唾液で溶けていた舌で、彼女の右耳を嬲った――ゾクリとクレイマンの躰が跳ねた――身を放そうと無意識に伸びた彼女の両手は、いとも簡単に彼の右手で一纏めに彼女の頭上で拘束されてしまう。そして戦慄く彼女の躰を這っていた彼の左手は何の前触れもなく彼女の秘芽に爪を立て――背を弓形に反らせながらもたらされる声にならない悲鳴を女の喉から引き出した。
「いいものだ………」
平素は涼しげなお前の貌が、朱に染まる姿を観るのは……――
耳元で低く囁かれた声と吐息に、思考を奪われそうになる――身を竦めるようにすると、彼の指が数本、再び彼女の体内に潜り込み――今度は水音を立てながら内壁と外壁に刺激を与え彼女の白い腿を震わせ、彼女の爪先は指を立てながら強張り、白いシーツに皴をつくった。
「――ン……ッ……!!」
久し振りだ……――悦楽に溺れはじめている脳裏でクレイマンは思った。冷めた想いを胸に抱きながら躰だけを男に抱かせるのではなく、自分から“欲しい”と思い身を委ねるのは。今日はそれを一瞬、士度に期待したのだが、思わぬ相手となったその腹心もどうしてなかなか……。
「―――!?ふッ……アァ……!!」
急に下肢からロートの指が引き抜かれ濡れたそこが空虚になったかと思うと、彼は何も言わぬまま彼女の秘処に楔を突き立ててきた――腹部を内側から圧迫するようなそれにクレイマンが苦しそうに身を捩ると、最奥へと身を進めていた彼の動きがピタリと止まった。
室内の揺れていた空気も止まり、彼女の荒い呼吸だけが灯色の空間に小さく響いている――両手の拘束もいつの間にか解かれ、ロートの右手が彼女の少し癖のある銀糸の髪を気のせいか――どこか労わるように梳いた。
「…………………」
身を繋げているのに――自分の躰は火照り、彼自身はこの胎内で硬く脈打っているというのに――ひどく穏やかな刻だと彼女は思った。
目の前に流れ落ちてきた彼の白に近い銀の髪を戯れに、彼女は細く繊細な指先で絡めとった――そしてふと見上げると、濃く深く――血の色のように映える紅い眼が、静かに自分を見つめている。その眼差しは今度ははっきりと――彼女自身に注がれていた。
「――美しい、な………」
きっと至高の作品ができるだろう――この瞳と寸分違わぬ彩の紅玉を使えば、自分は精の全てを注ぎ込み――世の宝とのなる逸品を創りだせるだろう……――
ロートの瞳のすぐ下の皮膚を指先で辿りながら、クレイマンは夢見るかのように呟いた。
「――笑わせるな………」
彼は相変わらず無表情のまま――しかし、かといって虚け言と馬鹿にする風でもなく、貌を辿る彼女の指先を手に取ると、自らの手に絡めながらそのまま枕元へと沈めた。
「いいや……お前は――……」
――続くクレイマンの言葉は、再び動き始めたロートからもたらされる淫蕩な熱に熔かされ堕とされ――声にならなかった。
身を深く穿たれ、淫靡に濡れるような感覚を躰中で感じ、自らの喉からただ啼くように漏れる嬌声と繋がる個所から聴こえる卑猥な音、そして時折聞こえる彼の息使いに耳すら犯されながら――彼女は彼の熱にどこか安堵していた。
そしてそれは良く似た者同士が久し振りに感じるであろう、それこそ戯事の中に咲いた華なのだと彼女は瞼の裏でそう思った。
そしておそらくは彼も――そう感じているであろうことが、彼女には何故か手に取るように分かるのだ――それは繋がる男の熱が語る、愛でも恋でも友情でもない――しかしそれはどこか心地の良い
「――ッ……!!はっ……ン…ッ……」
不自由な体勢のなか唇を求めれば、そのぬくもりは与えられる――そう、後に想い焦がれるのではない、いつかふと懐かしくなるような――そんな陽炎のような束の間の熱を今だけ、互いに求めあっている自分たち……――この二人はこの部屋を出れば再び氷に戻れるような、そんな
彼女の手が快楽に耐えるように縋るのは、彼の人よりも白く逞しい鋼の体躯――その上を大理石を流れる露のような汗が時折輝き、自分の喉から自然零れる喘ぎ声の向こうで彼女の唇が微かに弧を描いた。
あぁ、まるで……――
月に抱かれているようだと、クレイマンは思った。
夜闇に浮かぶ、白く冷たい月――
しかしそれは極稀に、妖しげな紅にその身を変える――凶事を予感させる紅い月は漆黒の帳の上に静かに、禍々しく君臨し、それを目にした人々は恐竦とともに脚を止める――しかし私は……
(――やはりそんな月を、美しいと思う……)
そして、私は知っている――その月の裏側は、灼熱の炎が燻っているということを……――
闇を守り、青い月と共に生きる為にその炎はときに何よりも美しい光焔となって寇敵を呑み込み、焼き尽くす……――
その月が、今宵刹那の間だけ――我が腕の中に。
「……ッ………!」
不意に――ロートがその端正な貌を顰めながらクレイマンから身を離し、身を繋げたままではあったが彼の片手は反射的に彼女の首を抑えつけながら褥に縫い付けた――血こそは流れてはいないものの、彼の首筋には赤い痕が……――
一方、再びベッドに縫い付けられたクレイマンは、彼の手の下でしてやったりと目を細めている。
「土産だよ……青き月に………」
彼女からのそんな言葉にロートは僅かに眉を上げただけで、クレイマンが少し期待したような――困惑や怒りの表情は微塵も見せなかった。
「…………」
やがて彼は無言のまま身を倒し、いまだ力を失っていない自身をそのままさらに、彼女の最奥へと進めてくる――内側へ与えられた擦る感触にクレイマンの秀眉が切なげに寄せられ、その快楽から無意識に逃れようと動いた脚は彼に抱えられることで動きを封じられ、彼女の身体をさらに熱くさせた――
「………ん……ッ………!!」
目の前で揺れる紅い情事の痕を目の端に収めながら、揺らされ、与えられる淫志な感覚に身を沈めながら――クレイマンは彼の吐息を求め――そして嬌声を飲み込まれながらその中で――堕とされた。
そしてほぼ同時に躰の中で迸った温かい飛沫――それはいくら男装をしようとも女故に時折求めたくなる、男の痕跡。
引き抜かれる感触にクレイマンが刹那眉を細めると、ロートはベッドから離れようと身を起こした――しかしその白い腕を彼女の細い手が引き留めるように掴む。
「……まだ少し時間があるよ。いいじゃないか……」
珍しく、そんな気分なんだ……―――
横たわったままのクレイマンが微笑みながらシーツを捲り、隣に来るようロートに促すと――彼はそのとき初めて少し呆れたような貌をしたが、それでも彼女の希望に応えてその身を再び褥に戻す。
「………それにね、とっておきの寝物語があるんだ……」
「――――?」
煙管を手にしながら火をねだるクレイマンのそんな言葉に、マッチを擦ってやりながらロートは怪訝な貌をした。
口から香りの良い紫煙を燻らせると、彼女は艶めかしい微笑みをロートに向ける――
そして横たわるロートの鍛え上げられた逞しい肩に頭を寄せると、事後の余韻に微かに啼く躰の力を抜きながら――
彼女はもう一度、その美しい口元に笑みをつくった。
ロートの方はそんな彼女の様子に、しかし大して気にした素振りを見せるでもなく――煙管盆から紙巻を取り出すと、自分で器用に火をつけた。
とっておきの寝物語――それを聴いた瞬間のこの紅き者の貌はきっと……滅多にお目にかかれないものになるだろう――
「―――………?」
クレイマンはロートに寄り添ったまま至極機嫌良さげに煙管を吹かしている。
ロートはもう一度、刹那不思議そうな表情をしたが――紙巻煙草の煙を吐き出しながら頭を枕に預けると、その視線を天蓋に向けた。
あぁ、気付かなかったが、綺麗な青の天蓋だ――
自分と良く似て異なるあの白い肌の感触が、ふと恋しく彼の脳裏に蘇った。